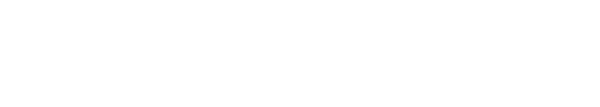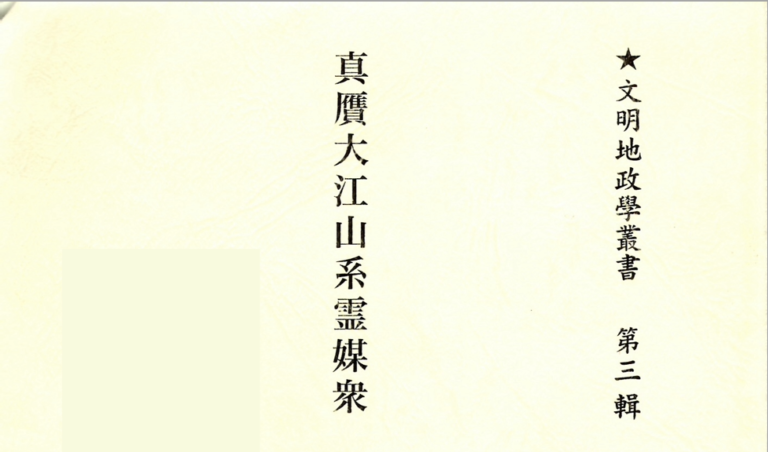●錯綜する辰吉郎の個人情報
昭和一六年(皇紀二六〇一)真珠湾攻撃の三ヶ月前に生まれた筆者は終戦まもない頃から父と父の知友すなわち旧軍部の膝のうえで多くの大言壮語を聞かされて育った。その影響やら甚大で、正月と天長節とに行われる皇居一般参賀が慣例となる。その体認を続けるうち神格天皇と天皇制の間に違和感を持ちはじめ、その違和感を抱いたまま死神に取り憑かれて生き様を左右されるようになる。
さて辰吉郎に関する個人情報として、他にもGHQ統計局長カーペンターの滞日中、前夫との間に産した双子の女児を抱えた芳子がカーペンターと婚姻して、カーペンターの本国帰還に際し双生児の在米永住をめぐって大騒ぎとなった顛末は米国でも広く知られた。その理由は、芳子の父が堀川辰吉郎とされたからで、全米ジャーナリズムを挙げての喧噪となったのだ。つまり、知る人ぞ知るのが堀川辰吉郎であり、この騒ぎを機に辰吉郎の個人情報は検閲管理下に置かれたが、すでに操作不能の情報もあるため、逆に情報錯綜を利用して、実子との確証がない子も出現することになる。辰吉郎の情報はその抹殺が企まれる現実のなか、勝手に独り歩きしていくのである。
●大宅壮一手記の王仁三郎
戦後ジャーナリズムの日本言論界を見るに、大宅壮一(一九〇〇〜七〇)には慈悲の念を禁じ得ない。辛口評論でマスコミの王者に君臨したために、その生贄とされて媒体を彷徨う運命を免れなかった。大宅の代表的遺言は、自戒を含め「日本人一億総白痴化」と見る捨台詞だが、もっとも憂慮したのは自らも在籍するマスコミの為体であり、口先や筆先の虚しさを痛感していた。現在では何を勘違いしたのか、大宅の自戒を解せない夜郎自大(やろうじだい)が尖兵となり、自らの白痴化を晒しつつ民主化の波間に浮き沈みしている。
好奇心の旺盛な少年期に大宅は出口王仁三郎(一八七一〜一九四八)を見ており、その異様な布教活動から受けた思いが去らず、すでに還暦を越えた王仁三郎の寿命を考えてか、予約ないまま講社大本の本部綾部を初めて訪問したという。
大宅壮一は大阪府の茨木に生まれ、昭和二年(二五七八)に『文壇ギルドの解体期』で論壇に華々しくデビューした。筆名「猿取哲」の活動期(昭和二〇〜二五年)を含め、流行語を多く生み出し、『炎は流れる』で菊池寛賞(昭和四〇年度)を受けた。
この大宅に従えば、本名上田鬼三郎は神秘体験を重ねつつ病気治療を伴う布教活動に勤しみ、二八歳で稲荷講社所属の皇道霊学会の創設を行うなかで綾部に住む「出口なを」と出会い、翌年「なを」を教主に「金明霊学会」の創設も仕上げる。以後、日刊新聞を発行するなどマスコミを利用した布教により全国的に教勢を広げるも、弾圧(昭和一〇年)を受け翌年解散する。この組織が再び世に出るのは改称した大本愛善苑(昭和二二年)としてであり、のち旧称皇道大本に戻って復活するが、大宅が王仁三郎と対座したのは弾圧直前のことであった。
以下その手記を損なわないよう心掛け、大宅の王仁三郎観を要略しておきたい。
大本布教で聖師(王仁三郎)が茨木に来たとき、少年大宅は友に誘われて一里の道を歩き会場入りした。聖師は「天地壊滅の予言」と題し講演したが、まず大宅はその盛況ぶりに目を奪われ、胸の動悸を抑えることできずにいたが、後に友が信徒になり宣伝使にまで昇ると大宅の訳書『共産部落の研究』を読み、その講説が大本教、天理教、金光教に共通することを理解した。大宅が聖師を訪ねるべく思い立つのは、当時センセーションを起こして世間の注目を浴びる反宗教闘争に立ち向かう聖師と会うのが動機であった。アポもなく丹波綾部に出かけたと嘯く書き方で始まっている。
大宅が綾部に着くと、「綾部大字本宮町一番地 出口王仁三郎」の標札があり、門前にはコンクリート造りのキリスト教会が建っていた。付近の人に聞くと、聖師は亀岡での夏期講座に出向いて留守だという。大宅にも亀岡に向かうが、綾部と亀岡は町の大きさも印象も似ており、明智光秀所縁の亀山城跡に陣を取る「天恩郷」が、大本教第二本部と銘打ち使われていた。銀杏の老樹を中心として、大祥殿、明光殿などの大建造物群が立ち並んでおり、聖師の養子では日出麿(ひでまろ)や宇知麿(うちまろ)が控えていた。紹介状もアポもない面会申し入れに対して事もなく聖師は大宅に会うという返事があり、宿をとった大宅は自ら手紙を認めて番頭に使いを頼んだ。番頭は聖師が散歩中と告げたが、やがて宿にいる大宅に電話があり、今夜は疲れが出ているため、明日午前中に明光殿に来られよと約束が交わされた。このあと大宅は意図的に自分を著名人と思わせる書き方をしている。
聖師は浴衣の上に絽の羽織をかけ、頭に烏帽子の如きものをかぶり、長身肥大は顔も声も大きく、還暦を過ぎたとは思えないほど若々しく元気溢れていた。聖師は自分の歌集一万を自撰するため、五十〜六十万種を詠むと言い放つが、例えば一日に一〇首とすれば、年三六五〇首、三年で一万首、五十万首詠むには一五〇年かかる計算と大宅は詰問した。それに聖師は一日に二〇〇〜三〇〇首を詠むと応え、全国短歌結社八〇余に載せるほかに数種の機関雑誌があり、それらに寄稿すると言い放った。大宅が調べると、実は、短歌結社や機関誌が自社の会計一部を聖師に負担させるべく取り憑く単なる利殖行為にすぎないことが分かった、とも述べている。
また、聖師の小説は予定一二四巻の長編であり、当時七二巻まで完成し、総題『霊界物語』のもと全体を一二部に分け、さらに各部は一二巻から成り、各冊平均で四六版四〇〇ページと見積もれば、全部で四万九六〇〇ページに及ぶが、これを聖師は一冊三〜四日で仕上げるという。その分類一二各部支別の標題を、「霊主体従」「如意宝珠」「海洋万里」「舎身活躍」「真善美愛」「山川草木」などと大宅は記している。
どうあれ、大宅も書紀を職業とする身ゆえ、王仁三郎の速記力に驚嘆を隠せないが、筆者にしてみれば別に驚くに値しないことで、古来伝承に基づく翻訳など器用達者であれば聖師程度の技芸は幾らでもあり、その工房も古くから存在している。
大宅は聖師が使う多数の筆名について、特に次の如き名前を記している。出口瑞月、月の家和歌麿、月の家風宗、井出王川、石山秋月、十和田勝景、三国一峰、嵐山桜楓、保津渓流、室戸岬月、琵琶湖月、静波春水、山紫水明、寿翁無塵、出雲八重垣、仙史万公、亀山万寿、水呑玉子、福禄寿翁、和知漁水、大江山風などだが、これらの筆名を如何なる理由で選んだかには大宅は触れておらず、筆者も邪推は慎もう。他に聖師が行う余技として大宅は絵も上手いと書き加え、我流の自由画みたいに見えるが、それらは武者小路実篤よりも伸び伸びしたユーモラスがあり、仏画もあれば俳画のように武士が城の上から小便する絵もあり、他に楽焼きや書道も素人離れと記している。
人の評価を年齢で測る気はないが、大宅三〇歳半ばの評論であり、ここまで紹介すれば筆者が何ゆえ本項を書くのか、史家を任じるのであれば、すでに気づかなければ史家とはいえまい。その理由は後述するとして、もう少し大宅の手記を加えておく。
聖師いわく「大本は宗教にあらず、大本教とは新聞辞令みたいなもの。大本とは、政治、経済、芸術みな引っくるめて、宇宙の大本を説くことにある」と。これは大宅が聞きたい最重要課題すなわち反宗教闘争に関して聖師の本音を引き出す経路に通じていく。この言に続いて、聖師は本願寺その他の既成宗教に巣くう腐敗堕落を罵るが、大宅が取材方向をマルクス主義宗教論に切り替えると、その手の理屈は興味なく「議論をしたけりゃ宣伝使とやるがよい」と躱(かわ)される。大宅は宣伝使と議論する気が毛頭ないため、これにて落着と引き下がることになる。筆者の要略はこれで十分と思い終えるも、結びに聖師すなわち上田鬼三郎の本音が潜む歌三首を大宅の手記から抜粋し、その補足としておく。
宗教は数多あれどもおしなべて 営利会社の変名(かわりのな)なり
宗教の美名にかくれ曲神は 人の汗すいあぶら飲むなり
宗教は牧師僧侶をふりすてて 人の心の奥底に棲む
上田鬼三郎と大宅壮一は同じ族種に属するが、この種の特徴は常に内訌を繰り替えす点にある。戸籍編入の後にも、例えば前述した細川氏と同じく異相を好む癖がある。皇道大本を標榜しつつ、門前にキリスト教会を建造してその混淆を隠そうとせず、来るモノ拒まず、去るモノ追わずを装うパフォーマンスは、聖師を訪ねる大宅の偽り方も同じことである。
上田家の家系の中で広く知られるのは立体画法を初めて用いた円山応挙だから、鬼三郎が上手い絵を描くとか、上田の結縁の武者小路実篤と比較するなど、大宅は先刻承知のことを書いたに過ぎない。聖師と大宅はすでに互いが同族だと心得ており、大宅の本当の目的は、綾部に弾圧の手が及ぶことを告げることにあったのだ。
何ゆえに上田が綾部に移住したのか、それには清和源氏海野氏流の海野幸隆が信濃国小県郡真田庄松尾城に住して真田氏を名乗るまで遡る必要あるため、本稿では省くが、ここでは綾部大本教が大江山講社の一つとだけ記しておく。
●紫禁城内に辰吉郎の小院
読者の趣に沿わず辰吉郎の成長記録は省く。それは筆者の如き器は神格の成長記録を記す何ぞの資質を持たないからである。明治二五年(二五五二)、出口なを教主が担がれて綾部大本教が興ったとき、出口清吉は二一歳、上田鬼三郎二二歳、日野強二七歳に当たる。日清戦争が二年後に始まり、それぞれの消息については好事家の注目の的にもなるが、辰吉郎についてはほとんど関心が持たれることはない。
それは辰吉郎本人の意志と関係なく、辰吉郎と直接関係した時代の重役たちにとって、彼らの使命に比して辰吉郎が測りえない存在であり、表現すべき言葉を持たなかったからである。だが、宇宙生命の一端を担う人の使命は過去と未来の連続性がなければ、現人神といえども要求を満たすことはできず、その連続性に順えば神格に達しない命ほど、通史の接ぎ穂としての辰吉郎の事績を知る必要がある。筆者はすでに神格天皇が行う超克の型示しに触れ、その威徳に順う自らの使命を明らかにしているため、言葉に不足は生じても、辰吉郎が混迷極まる大陸で貫き徹した型示しについても、本稿の課題を完遂するため明らかにせねばならない。
明治四三年(二五七〇)に辰吉郎が三一歳で支那大陸入りしたのは、明治天皇崩御二年前、皇太子嘉仁親王三二歳の時に当たる。すでに皇家には裕仁親王(昭和天皇)、雍仁親王(秩父宮)、宣仁親王(高松宮)と相次いで降誕され国体安堵定まるも、支那は辛亥革命が勃発(一九一一)する前夜にあり、朝鮮半島にも韓国併合条約で日本の総督府が設置された年である。当時、北京紫禁城の威容は外郭の東西約七〇〇メートル、南北は約一〇〇メートルが高い城壁で囲まれ、城内を二分して南半が公式政治の場として、北半が皇帝の私的生活の場に使われていた。建造物八〇余を設けた皇宮は、宣統廃帝溥儀の退出(一九二四)翌年、内務部古物陳列所の場を故宮博物院の名称に変え、支那五〇〇年来の禁制地が初めて公開された。当時の情勢に関しては別冊『歴史の闇を禊祓う』にも記しているが、この紫禁城北半の皇宮の一つを寓居とするのが堀川辰吉郎である。
日清戦争講話後の独仏露による三国干渉(一八九五)は日野本に書かれるように清朝人民の遺憾とするところ、清朝皇帝の中華思想にも反するところであり、爾後の日露戦争(一九〇四〜〇五)を踏まえ、支那は日本に勝手な期待を寄せるようになるのだが、政府の政策は方向性が異なるため、清朝重役は辰吉郎に救いを求めたのである。
日本政府は三国同盟と三国協商の利権闘争を視野に捉えつつ、その津波のメカニズムが判らないまま、日露戦争勝利という勘違いのもと、大西洋戦争すなわち第一次世界大戦(一九一四〜一八)に巻き込まれていく。三国同盟(一八八二)に対する三国協商の成立(一九〇七)を冷静に解析したのは、大江山霊媒衆であり、その頂点に据えられたのが辰吉郎である。植民地化の波が襲う海外に分布した大江山霊媒衆による情報分析を参考とし、その活動分野に広く潜入し得るのは、相手の信任なくしては成り立たない。そこに働くエネルギーの源は権力とか財物とかの問題にあらず、悔いなき仕事に一命を投ずる覚悟であり、況や、先の戦争終結に貢献した覚悟の代表は無礼にも神風特攻隊の異名で呼ばれる若き命に尽きるが、この覚悟あればこそ、歴史が支えられているのだ。
紫禁城内に辰吉郎の小院を準備したのは杉山茂丸ほか在野の志士であり、清朝皇帝の信任がなければ成立する話でもなく、ましてや力尽く何ぞ有りうるわけもない。しかもその入城が辛亥革命一年前という共時性が重要である。何ゆえにか、辛亥革命は南京という地を選んで中華民国臨時政府を樹立し(一九一二・一・一)、宣統帝退位(同年二・一二)、北京では袁世凱が臨時大総統に就任(同年三・一〇)する。こうした共時性に伴う場の歴史に基づけば、清朝重役が辰吉郎に救いを求めるのは歴然だろう。
同年六月八日に日野中佐は「陝西省方面ニ到リ諜報活動ニ従事シ、特ニ該方面ニ於ケル共和制反対党ノ動静ヲ偵知スルヲ勉ムベシ」との辞令により、再び特務活動を展開していく。
日本政府はドイツに宣戦(一九一四・八・二三)、まず青島を占領すると同年一一月七日に軍政下へ置き、対支特務工作の中心とした。この第一次世界大戦の終結後パリ講和会議で日本は山東省ドイツ権益を獲得する。このとき、日本政府は青島を含む膠州湾の租借権も手に入れ都合勝手な支那を怒らせる。北京大学生の通称五四運動を機に支那大陸には日貨排斥などの抗日運動が広がり、同じく都合勝手な日本政府の迷走図も加わると、ヨーロッパの飽和を象徴するインターナショナル思想に絡め取られる破目に陥るのだ。
●紫禁城皇帝と辰吉郎入営
辰吉郎の寓居が紫禁城内に定まり、宣統帝溥儀(一九〇六〜六七)五歳と辰吉郎が触れ合えば、それはすなわち王子と神格との出会いゆえ、瞬く間に溥儀が辰吉郎を慈父と慕うのは、至極当然の位相であった。こうした経緯を瞬時に感得する者こそが、真の霊媒衆である。乱世にあって、生誕の二年後三歳で皇帝の座に就く溥儀と比するに、袁世凱(一八五九〜一九一六)五〇歳が双肩に担う課題は余りに重すぎた。新疆探査のため、日野が北京を南下(一九〇六)していち早く訪ねたのは多賀宗之であり、多賀は袁世凱の招聘で軍は上原多市、呉禄貞、升允らとの交渉も含めすでに触れたところである。
溥儀一七歳(一九ニニ)の師傅に王国維を推挙した升は、溥儀が一九歳(一九ニ四)で紫禁城を出るに至ったとき、行を共にして天津の日本租界で没した(一九三〇)と、岡田は記している。この時すでに、支那の象徴たる袁世凱なく(一九一六年没)、孫文も没していた(一九ニ五)。だが、溥儀ニ九歳は満洲帝国創建(一九三四)をもって自ら皇帝に就き、支那自立の道へ第一歩を踏み出した。わが皇紀歴が肇国の基となった歴史に鑑みて年号を定め康徳(こうとく)元年と称した。