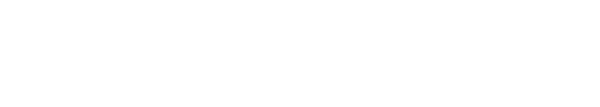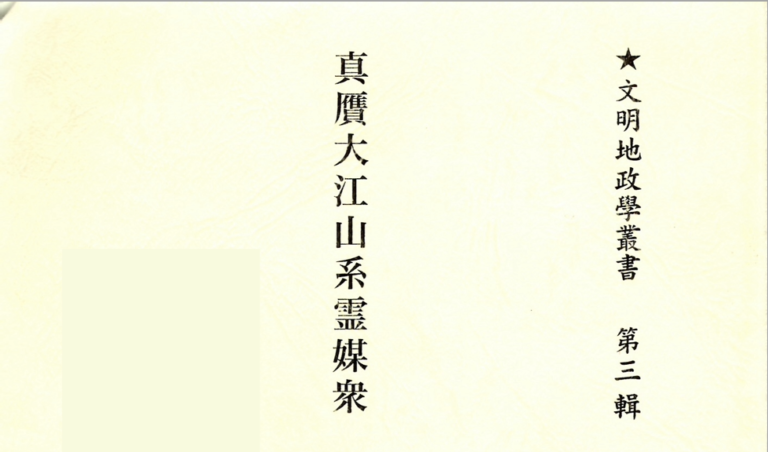●満洲建国への道程①
張作霖爆殺と同じ工作は戦史の常であるが、政党間抗争と軍閥抗争に揺らぐ日本は私が公を司る本末転倒の下、支那反日感情の対策に追われ錯綜する自虐史観と圧政史観の呪縛に絡め取られる。大正天皇崩御三日後、すなわち元号「昭和」の公式発表の日、政府の首班加藤高明(本姓服部)が没して、若槻禮次郎(内相)が首相を臨時兼任、三日後に若槻政権が正式に発足するも四ヶ月を持ち堪えず、後継の田中義一政権が二年三ヶ月弱で退陣するのは、張作霖爆殺の約一ヶ月後であり、次の浜口雄幸政権(二五八九〜九一)は大恐慌、ロンドン海軍条約、佐郷屋留雄襲撃事件などに揺さぶられ、再登板の第二次若槻政権も八ヶ月しか保たず、これを継ぐ犬養毅政権は約五ヶ月後の海軍青年将校の五・一五事件によって犬養が倒れ、蔵相高橋是清が首相臨時兼任(一一日間)となる。以後、斎藤實政権(二年一ヶ月強)、岡田啓介政権(一年八ヶ月)の終末に発生するのが二・二六事件(二五九六)であった。
つまり、昭和の幕開け早々から戒厳令布告まで重大事件には事欠かないが、共時性を伴う場の歴史は何れも、国際外交と切り離せず、そこに潜む情報を掘り起こさないと最も卑劣な私利私欲に公は骨の髄までしゃぶられるのだ。そして現在、その私利私欲が飽和状態にまで達している。
浜口は満洲事変の前夜に没したが、その七月に満洲万宝山(長春近郊)で支那と朝鮮の住民衝突事件が起こる。これが朝鮮に飛火して、全土で朝鮮人が支那居留民を襲い殺害も少なからず、その責任は何と日本総督府へ向けられ、今度は支那全土で日本製品ボイコット運動の広がりが急を告げる。
東京国際軍事裁判史観の暴走に政府が怯える始末ゆえ、田母神論文レベルで大騒ぎするわが国の為体であるが、過去と未来の連続性は何事にせよ正直な現実を生み出すのだ。
そもそも満洲事変の如きは歴史の常であり、各国政府と国際革命が互いに利己欲を競い争うなか、南京地方自治体の訴えを何ゆえに国際連盟理事会が受理する必要を生じたのか。その工作も必然であるが、それが読めない日本政府も乱世を透かす能力を持ち合わせていなかった。連盟理事会は日支双方にケロッグ=ブリアン協定を発動し、日本に同年一一月一六日を期限として占領地撤退を求める議決を行った。以後、関東軍から満洲建国の話が持ち上がり、これに天皇も宮中グループも何らの異を唱えずとするのが通説だが、第二次若槻内閣も同年一二月一三日に総辞職している。
辰吉郎は入営当初に清朝再生を視野に捉えており、その意は皇統奉公衆を通じて東京の昭和天皇にも通じていた。通説の宮中グループはともかく、天皇が満洲建国に特段の異を顕さないのが、清朝再興について辰吉郎に絶対の信を託していたからである。
対日協力支那人らと関東軍司令部による会議は昭和七年(二五九二)二月一六日に奉天で開催、東北行政委員会を設立、この委員会が翌々日に満洲国の建国と独立を宣言した。翌月一二日に犬養政権は支那大陸内に満洲および内蒙古の分離、さらに独立国家建設の推進に承認の方向を明らかにし、その法的整備に当たる旨を発表した。
ここに至る具体的な経過は侃々諤々の議論あるも、甲説がああ言えば乙説もこう言うという詮ない話であって、都合勝手な歴史認識の下、閉じられた空間で競い争う理屈抗争に本稿は与さない。満洲事変は錦州占領からさらに上海事変へと至る流れの発端となるが、その節々で戦火を打ち消す超克は独り神格天皇のみ能くするところであり、余人を以て為しえないのは歴然だろう。その型示しが満洲建国であった、
犬養政権の閣内不一致は上海事変で極まって、高熱症状が若い純心に伝播した。前政権の大蔵大臣井上準之助、また三井合名理事長団琢磨が相次いで暗殺され、犬養殺害に止まらず政友会本部、日本銀行、警視庁の襲撃にまで及んだ。さらに内大臣牧野伸顕の官邸に投げ込まれた爆弾には宮中グループにも陰りを生じた。
共時性を伴う場の歴史においては、イタリア式のファシズムや、ドイツ式ナチズム、ソ連式ボリシェヴィズム、また英米仏の商業主義協商など総じて戦争体制に勤しむ準備に追われていた。特に米国ハーバート・フーバー政権は満洲建国に真っ向から反対を表明するや、大統領の経歴に相応しく諜報工作の限りを尽くし、支那代表団を囮にして国際連盟理事会で多数派工作の攻勢を強めていた。それは植民政策で成り上がった国家の宿痾であり、列強国の共有資質ゆえに、世界恐慌を脱するに当たり、日本に恨みはなくとも、支那における権益拡大に日本は余計と判断したのだ。
●満洲建国への道程②
昭和五年(二五九〇)を機に、宮中グループに登場するのは世襲貴族三代目の近衛文麿(公爵)、木戸幸一(侯爵)、原田熊雄(男爵)らで、牧野内大臣の秘書官長時代の木戸の『木戸日記』は広く知られている。
昭和八年一月一四日、閑院宮参謀総長が昭和天皇に「満洲への部隊増派」を奏上した時、牧野や木戸の記録によると天皇は「満洲に付ては此れまで都合好く進み来りたり、誠に幸なり、今後功一簣(こういっき)を欠く様の事ありては遺憾なれば、熱河方面に付ては特に慎重に処置すべし」と仰せられたという。
この伝が核心を得るか否か、解釈に様々あるも答は歴然であり、書記官の能力が問われても天皇の語録には成りえない。すなわち、この伝は辰吉郎の進める満洲建国に支障など生じぬよう、意が通じる閑院宮載仁親王に十分な配慮を要請したのである。先には、日清戦争後の台湾平定で北白川宮能久親王が薨去され、その行啓で得た公に臨む大御心の実践覚悟があり、三国干渉で遼東半島を清国に返還するなど、神格の透徹史観には微塵も私が入り込む余地などないのだ。
さて、満洲増派の原因を見てみよう。ケロッグ=ブリアン協定を名分に日本包囲網を狭める各国の動きを見ると、すでにソ連は極東軍再編のため、対欧空軍部隊を移動、さらに太平洋艦隊の強化も急いでいた。曰く因縁の断続性があるも、米国は支那侵攻の再後発国ゆえ、手詰まりと焦りを打開する捷径(しょうけい)は日本を狙い撃ちにするのが最も手早いと作戦を組んでいた。北平(北京)の紫禁城(現天安門)と天津の日本租界を結ぶライン、また北京・奉天の鉄道ライン上に錦州があり、満洲建国に熱河省との交通は必須の条件であり、日本は早くに南満洲鉄道を敷設した。つまり、清朝復活に熱河を抑えるのは最重要課題ゆえ相応の準備を要したのである。
これを通説は日本軍による熱河侵攻というが、後年の歴史が証明するように、南京政府は国共合作など経るや、最終的に支那八路(露)軍と国民政府の戦となり、大陸は支那八路軍が収奪して、国民政府は台湾略奪の植民地化を果たし、現時は敗戦国日本の賠償で成り立つ現実を享受している。
似非教育下に巣立つ史観では勝てば官軍と逆上せ、負ければ賊軍と自虐に酔い痴れ自ら矜恃を喪うが、戦後日本の政策たるやまさに典型と言わざるをえない。
杉山茂丸没二年前、内田良平没四年前、清吉没六年前、それぞれに死神を背負う公には相応の遠心力を伴う働きがあり、それは溥儀の側辺にも働いていた。辰吉郎の意は皇統奉公衆が代行するも、そこには何ら合議の場を要しないまま、核心を出て核心へ戻る物質恒久化リサイクル・システムの運動が保たれていた。それが公の原義である。これに比する私のメカニズムは核心が知で成るため、常に意を尽くす禊祓を欠かせないのであるが、不規則運動を常とする機関に慣れてしまうと、独りに堪えられず、赤信号みんなで渡れば恐くないという不良に化けていく。
かつて筆者は高松宮宣仁親王殿下に問うを許された。それは青年将校蹶起の五・一五事件に加わる在野の志に関する問いであったが、高松宮は「当時、海軍一部に第二の同様事件を醸す空気は消えておらず、その目的の禊祓は重大ゆえ・・・」と思し召され「通常ロンドン条約に係る問題を第一段といい、社会改造は第二段という考え方が広まるが、第一段は軍内首脳に向けての不平不信を何とかして一糸も乱れぬよう整備する目標を抱えており、第二段は政党の腐敗、財閥の横暴、農村の疲弊、道徳の堕落、為政の態度、等々の社会問題であり、条約問題は副とも思えるが、大部分の純心を汲み取る公が法に適わぬは、我が身の不徳かな・・・」と諭された。
この事件は将兵が軍司法機構で裁判を受けるが、民間人は一般法廷で裁かれ、刑の軽重に大きな違いを生じた。筆者は高松宮の思し召しを賜るまでは、独り国賊たらんも可なりと己の死処を模索していたのだ。
克己自立すなわち禊祓が不足していると、皇統奉公衆の生き様は理解できず、杉山らの生き方に接しても意味はなく、たとえ想像を巡らしても単なる幻覚しか浮かぶまい。図書を渉猟して自分の好みに惚れるのは勝手だろうが、誰が何して何とやらより、自分自身が先人の遺訓を超克する行為を為さねば、先人に苦笑されるのが精精だろう。
どうあれ、南京自治体と列強勢力に潜む算段合致の結果は、支那八路軍が革命ソ連と結びつき、中華国民(党)軍が米国方と結び、その接合は国際連盟に剥離現象を引き起し、大戦後に綻びを繕い化けた国際連合が現在を賑わしている。
日本の国際連盟脱退(二五九三)は斎藤政権下の二月二〇日に決せられ、同月二四日の連盟会議で満洲国否認が議決されると、三月二七日に日本政府は連盟脱退を正式に通告した。
つまり、満洲建国記念日の決め方については、史家の解釈も様々あるが、暦法は総じて皇紀暦に比するものなく、万世一系また比するものない歴史認識が重大なのである。通説では溥儀執政年間を皇紀二五九二年(一九三二)から翌年までとして大同と号し、溥儀が皇帝だった二五九四年(一九三四)から二六〇五年(一九四五)までを康徳と称するが、かかる算段こそが歴史の千切り取りに他ならない。
●満洲建国の大義は死なず
溥儀二七歳(二五九二)の執政を傀儡政権と見なす発想は神格の振舞いと型示しを解せない民主化一念ゆえに仕方ないが、溥儀は行年六二歳で没するまで、すなわち堀川辰吉郎没の翌年(二六二七)にその生涯を閉じるまで、辰吉郎を慈父と仰ぐ姿勢に微塵の揺るぎもなかった。
視界を広げ満洲建国と国際連盟脱退の時空を見ると、列強文明は世界恐慌により内政の動乱に晒され、在来保守思想と革命思想が混濁していた。こうしたとき、国内の目を外政に振り向け逸らす政策が歴史の常道である。その典型が戦争であるのは論を俟つまい。
ナチズムやファシズムはベルサイユ体制の破壊に勤しんだが、英国はその経歴、すなわち東インド会社ロンドン設立(一六〇〇)、同社広東商館設置(一七一五)や同社による英政府統合(一七八四)さらには対支アヘン戦争などの歴史を踏まえ、満洲建国へ向かう清朝再生に強い警戒を抱いていた。その証が保護貿易主義への転換であり、特恵的な関税障壁たるスターリング・ブロックを設ける決議に顕れている。
他方、米国は新大統領フランクリン・ルーズヴェルトの政権下、経済復興をニューディール政策で講じながら、より低い関税で相互貿易協定を結ぶという背反の矛盾を冒している。かかる手前勝手な孤立主義は南部黒人差別を放置したまま西半球およびフィリピンに対日輸出削減を促す策に顕れる。これら欧米の都合勝手を遥かに上回るのが革命思想である。
帝国ロシアを破壊した民主勢力ソ連は何とも奇怪な強権運営を行うが、似非教育下の論説はこれ共産党独裁と称して民主化に対峙させたり、資本自由主義と単一統制市場に対峙させたり、未だ本末転倒の屁理屈を止めない。どうあれ、東西冷戦構造という理屈はダブル・スタンダードであり、互いに民主化を進める点では何も変わらず、違いはその主権を機関投資家にするか、労働組合にするかだけだろう。
また、経営支配権の行使と言っても、その実態は投資家と操り人形の談合で決まった方向を労組の専従委員が認証する仕組みでしかなく、社会も政権も会社も、誰のモノが何ぞと議論しても意味はない。それを侃々諤々の議論に仕立て上げる化け物がジャーナリズムであり、その情報を高値で買うか安値で買うか、それを買手が決めようとも、内容は天気予報と同じ当たるも八卦の占いと変わらない。
ソ連の計画経済を支える予算の裏付けは、満洲という地の利を活かした場の簒奪が主体である、これ他人のモノを自分のモノと思い込む労組の性癖に通じている。つまり、過去と未来を結ぶ連続性を読むには不連続線が生じる気圧メカニズムも把握する必要があり、満洲建国に伴う場の共時性を見渡すと、天気予報レベルの情報では済まないのである。
昭和一一年(二五九六)二月二六日、陸軍青年将校の決起事件が発生した。先の海軍青年将校決起の四年後ゆえ、如何なる理屈を講じようとも、高松宮宣仁親王殿下の思し召し以外その的確さを顕すものはない。その原因たる五・一五事件の裁きは官民を差別する不合理な司法措置を講じたのであるが、その禊祓となる二・二六事件の裁きは官民の別なく死刑銃殺という司法措置が執られた。
先に筆者は宮殿下の諭旨を「・・・・・・」に止(とど)めたが、それは司法公正を念じる奉公の祈願であり、神格天皇が御心痛され超克の直裁を降す導きによって、たとえ在野の奉公が思い込みにすぎなくとも、純心は鎮魂冥土に達して救われるのだ。銃殺刑に処せられるに際し北一輝が「天皇陛下万歳」と叫んだとの伝あるが、奉公の立場に立てば官民を分け隔てなく裁く法務は理想であり、死神を背負う奉公の本懐なのである。もはや祖国平定は神格の禊祓以外にはなく、天皇は民を救うが、民に天皇を救う何ぞできるはずのない現実がある。明治政府は西郷を賊としたが、天皇の国会開設詔書は西郷の汚名を打ち消す浄化の禊祓となり、昭和天皇の戒厳令発布は官民公正の裁きとなった。もとり、死神を背負う奉公は神格天皇にのみ救われるが、その覚悟を支えるはただ「天皇制護持」の一念であり、先の大戦における「総玉砕」にも通じて、現在が生かされるのだ。
弛緩が著しくなるとき、天意は必ず人為を戒めるが、その天変地異もまた人為の結果であり、原因探求を怠ると歴史は再び繰り返される。岡田政権を継いだ廣田弘毅政権は一年弱、次なる林銑十郎政権四ヶ月二日、第一次近衛文麿政権一年七ヶ月、平沼騏一郎政権八ヶ月弱、阿部信行政権二年九ヶ月、米内光政政権六ヶ月、第二次・第三次近衛政権一年三ヶ月六日、東条英機政権二年九ヶ月、小磯国昭政権八ヶ月半、鈴木貫太郎政権四ヶ月八日の短命。
つまり、大正天皇崩御後二〇年間に歴代首相二四〜四二代の組閣あるが、同様に昭和天皇崩御後二〇年間も歴代首相七四〜九二代の組閣ゆえ、両時代ともに一八回もの組閣を要している。
損傷も著しい二〇年間の節目を刻むに際して、唯一の救いは新天皇の即位と大嘗祭にあるが、通史一貫する連続性においては、満洲建国の道程も重大な痕跡であり、現時と今後を透かす史観にはその検討が必須となるのである。