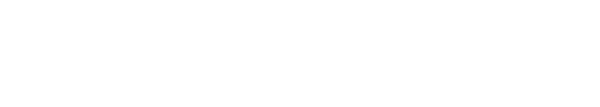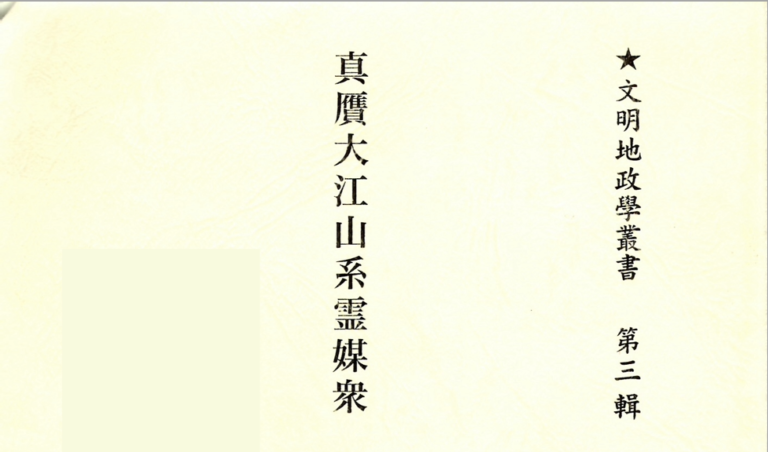●日野本の渉猟を終えて
以上で日野が著した『伊犂紀行』の検討を一応終えたが、日野本には当時の写真のほか、地図を含むスケッチなど、日野の潜在的な職能を窺わせる材料もふんだんに盛りこまれている。史家を自負して図書渉猟の旅をする者は参照されたい。
さて、真贋大江山系霊媒衆を禊祓するため、日野本から宗教と人種を跋渉して、現在および未来を透かす旅の準備を済ませたが、共時性に伴う場の歴史を整えないと本義は浮かび上がらない。透徹の本義は超克の型示しにあり、神格は微塵も揺るぎないが、自ら地獄を彷徨う大衆の現実には慈悲の念を禁じえない。人畜一体化の未来展望は民主化という寄せ鍋に群がり、単なる情知の一喜一憂は毒も薬も弁えず、残り汁から具材を割り出す能力もないジャーナリズムに振り回されている。
例えば、皇太子妃の神格に嫉妬して自らの愚痴を恥じない者が片方にあれば、皇太子妃の振舞いにミーハーしてアイドル視する者も他方にあり、日野説を当てれば「奇と感じ珍と観ぜし事柄は、全く宗教上より来たれる結果にして、未だ宗教を知らざる人の奇も珍も、既に宗教を知れる人に在りては、何らの奇も珍もなく奇とせし珍とせし以外に、真に奇なり珍なる」だけで、真贋大江山霊媒衆を解けば今時を透かす何ぞは造作もない仕事である。
以下、本題の旅立ちに際し共時性に伴う場の歴史から、他の人種についても補足を加える必要がある。語族分類法は文明開化を示す常套手段のひとつであるが、スキタイの如く明らかな痕跡を刻みながら文字の類を遺さない種族も少なからず。すでに死語となるも、「文明」の語に劣らぬ遺跡も多く発掘されている。すなわち、語族分類が決して万能に非ずを認識のうえ、以下、通説の語族分類法に従って、日野本の枠外にある人種を含めながら、真贋大江山系霊媒衆を禊祓していくことにしよう。
●通説の語族分類法①
例えば、古代エジプト移住の祖は大凡三万二千年前ころ、西アジア方面から来るとの有力説から想定されて、定住は約一万二千年前ころ始まり、のち比較的に流出は少ないと伝わる。また文明最古と目されるメソポタミアは、古代ペルシアの一部(現イラク)から起こるが、初期シュメールと呼ぶ族種不明の民が中心を占めたとされている。アッシリア南部のバビロニア北方部はアッカドの地に含まれ、シュメールが巣立つバビロニア(バビロン)ほか、アッシリア、エジプト、ヒッタイト、エラムなどもシュメールに劣らず栄えた同流と見られている。
ヒッタイトはアナトリア半島(現在のトルコ)を拠点に青銅器主流の時代に鉄を用いており、製法は滅亡期まで秘匿されたとの説が有力である。
エラムはメソポタミア東方の地を指すが、現フーゼスターン地方まで含むイラン高原の南西部、ザグロス山脈に沿う地域とされる。
情報の広域化を文明とするならば、情報交換の具を言葉ゆえ、そこに語族分類法が生まれても不思議ではない。そして現在の国連は条約に基づく公用語として英語、フランス語、ロシア語、スペイン語などを主流とし、これらを印欧(インド・ヨーロッパ)語族に入れ国際間を征する。
この語族と混交しながら並立するのがアフロ・アジア語族で、前記の古代都市を支配したという考え方もあり、似非教育下の現代史観に大きな影響を与えている。
まず印欧語族の変遷を略述すると、ヒッタイト、トカラ(トルキスタンやウイグル)、ガリア(ケルト)、西バルトの源流は干上がり、ラテン語の如きはイタリア、フランス、スペイン、ポルトガル、ルーマニアの言語をロマンス化した。また多くの派生語を生じて現存するサンスクリットや、イラン、ゲルマン、スラブ語などあるが、このうちゲルマン語は北欧系スウェーデン・フィン、デンマーク、ノルウェー、アイスランド、西欧系イギリス、ドイツ、オランダ、東欧系にゴートなどの新興語族を生み出しており、スラブ語では南方系ブルガリア、スロベニア、セルボ・クロアチア、モンテネグロ、マケドニア、西方系ポーランド、チェコ、スロバキアほか、東バルト方面にリトアニア、ラトビアなどの振興語族を生み出している。さらに単独語派のギリシアを加えると、印欧語族は現在一〇〇カ国に及び、人口二五億人に昇るとの報告もある。
●通説の語族分類法②
印欧語族と混交しながら並立するとされるアフロ・アジア語族の代表格はセム系といわれるが、ヘブライ語族、アラブ、マルタ、アラムなどを指しており、またコプト(古代エジプト)を含むエジプト系を軸とする分流も多くの痕跡が刻まれる。その系には、ベルベル系のモロッコ、アルジェリアほかハウサ(チャド)系のナイジェリア、ニジェールまたはソマリ(ソマリア)族や、クシ系と呼ばれるエチオピア、マリア、ジブチ、ケニアなども含まれている。
以上の二大語族と列(なら)ぶのがウラル・アルタイ語族で膠着語を使うとされるが、地域的特性も共有する言語連合として束ねられる。
さて人の生命活動において、言葉とはいったい何であろうか?例えば、おおよそ五千年前にカルデヤのウル(現イラク)を発してカナンの地(現パレスチナ・イスラエル)へ移動するアブラハムの群があり、彼らの子孫を他称ヘブル人またはヘブライ人と呼んで、彼らが使う言葉をヘブル語またはヘブライ語とする仮設がある。
ヘブライの由来はユーフラテス川を越えて移住してきた民の総称イブリムから生じたともいう。またユダヤ教、キリスト教、イスラム教が共通し重視する言葉はテトラグラマトン(神聖四文字)とされるYHWH(ヤハウェ)で、これは唯一神を表すヘブライ語を推定し音訳したものともいう。
因みにギリシャ語テトラグラマトンは「四つの文字」と訳される。日本ではヤハヴェ、ヤーウェ、エホバなどの別称を使うが、ユダヤ教成立以前のヤハウェ信仰に絡む訳し方の違いだけで、今や言葉は生命活動の本義を惑わす具でしかない。
●人の生命活動と語彙
語彙は単語の総体とか、ある単語の集まりに属する谷戸とか訳され、近代日本では明治四年(皇紀二五三一年)に神祇官編輯遼寮から『語彙』が出ており、上田万年・樋口慶千代の編纂した『近松語彙』など一定の順序に単語を集録した書物のことを表す言葉とされている。
また、日本語の語彙を出自から分類するとし、大きく和語、漢語、外来語、これらが混ざる混種語に分けることも定説に成り得ている。さらに、こうした出自から分類する言葉を「語種」といい、和語とは日本古来の大和言葉で、漢語とは支那渡来の漢字の音を用いた言葉で、外来語とは支那以外の海外から取り入れた言葉であると説かれる。例えば日本語の語彙は構成面から単純語「あたま、かお」「うえ、した」のように語源にまで遡らない限り、それ以上は分けられない単語と、複合語「あたまかず」「かおなじみ」「うわくちびる」「しもはんしん」のように、単純語を幾つか組合わせた語を用いるが、現代では言葉の氾濫が止まることを知らない。
現代日本語の表記においては、平仮名や片仮名の表意文字と、漢字を以て表意文字とする字種表記法が併せ用いられる。必要あれば、アラビア数字やローマ字(ラテン文字)などの併用も加わり、漢字の読み方では、支那式とされる音読み、大和言葉の読み方とされる訓読みが結び付くこともある。また日本語の方言には固有の表記体系がなく、書き言葉として使う頻度も少ないため、実際上に不便を来すことがないともいわれる。
日本語の歴史に、奈良時代以前は母音八種説が有力とされ、記紀や万葉集などの万葉仮名の表記では、「き・ひ・み・け・へ・め・こ・そ・と・の・も・よ・ろ」に仮名二種類(甲類・乙類)が存在するとし、音韻の区別を表すとの指摘も生じている。そして平安時代になると八母音は消え、固定語五母音に改められるともいう。上代日本語の語彙は母音の出現仕様がウラル語族やアルタイ語族の母音調和の法則に類似するとも言われている。何事も体系化し、その仕様を高める人の性癖は善しとしても、言葉の世界では日本語に限らず、いまだに人の生命活動を説明しきれないのが現状だ。
元来日本に文字と呼べるもの無しとする説があり、言葉の表記に支那渡来の漢字を用いたという暗愚に基づき、いわゆる神世の文字は後世の偽作だと斬りすてる。この妄説は皇紀六六〇年代(西暦一世紀)頃の遺物とされる、福岡市出土の「漢委奴国王印」などに依拠したり、応神天皇を描く『古事記』を解読できないまま、百済の王仁(帰化人)が持ち込む「論語十巻、千字文一巻」などを頼るものである。政府御用の学徒と称する筋や似非教育下の有識者と称する筋が嵌る陥穽は、まさに大江山霊媒衆の真贋と同じく語族分類を奉じる幻覚としか言いようがない。これ偏に、人の生命活動の何たるかを弁えず知に溺れる因果であり、日野本に潜む情報を読みほどく力などあるまい。
●霊操と霊媒について
霊操については、本誌連載の拙稿が文明地政学協会刊の『超克の型示し』としてすでに刊行されており、その中でキリスト教団イエズス会をモデルとして持論を展開しているので参照されたい。ここでは、霊媒について述べる。抑も自然界の営みは各種同様の場(環境)を形成して、場の営みは安定しようとする物質の要求に見合う振動をもつメカニズムから、各種各様の周期性(サイクル)を生み出していく。この周期性をもつメカニズムは、分解と復元を可能とする結合法に即して、各種各様の活動を生み出すようになる。すなわち、生命の始原は宇宙の営みであり、宇宙は時空の間を行き交う電磁波が交接しつつ、各種各様の場つまり地球も生み出したが、地球生命の特質的主成分は水であり、水の物性電磁波と共振する電磁波との相互関係を解明しない限りは、宇宙と地球生命の活動メカニズムを剖判しようがない。
剖判とは、剖(わか)れることが判(わか)ること、すなわち分解と復元の結合法を知ることにある。サイエンスは科の学という日本文学の目論見はともかくとして、サイエンスの訳「知ること」はいまだ水の結合法についても仮定・仮説から脱していない。これは実証現場と論証現場の市場原理の違いに要因があり、前者は物性の究明に偏り、後者は天性の究明に偏って互いの結合を急ぐため構造不全による剥離は免れず、剥離のとき、互いは相手の性質を千切り取り、もはや素の性質に戻れない宿痾を抱えたまま、更なる接合を求めるため、結局は玉虫色的な生き方を謀るほか仕様がなくなるのだ。
言うまでもなく、市場原理とは需給関係にあり、互いに求め合う清算方式に狂いが生じるとき、互いは競い争うことで、勝組と負組を生み出して格差を生じる。この格差は統治能力で安定を保てるが、統治能力が不足すると、不安定の極限では戦争さえ免れず、鎮定の究極は統帥能力を以て問われる。
水の物性が主成分たる地球生命は、天性と共振する遺伝情報をもつ核様体(細胞)から様々な生命を生み出して、もっとも新種の人名まで生み出したが、多細胞生命体である人の物性は天性との調和を求めて遺伝情報の限界を知らされる。この感覚から自然界を畏怖する信仰が芽生え、直流回路を主とする精神的な感応が研ぎ澄まされていく。これをテレパシーと称する現代であるが、それは表情や身振りを含め言語を整える原動力となり、原始的アニミズムに基づく音律に通じると、象形など模写する芸能が盛んになり、結局は場の営みに伴う言葉(ロゴス)を作り出しシャーマニズムが生まれる。
因みに、遠感現象を司る直流回路は電荷移動の向きが時間的に変化しないため、電圧は変わらない。
ゆえにアニミズムの主体は電波伝播であり、アニミズムとシャーマニズムとが合流するプロセスに働くのが交流回路である。交流直列回路は電圧の発生のほか、R=レジスター(抵抗)、C=コンデンサー(蓄積)、L=コイル(螺旋)、波の伝播など、各種各様の媒介エネルギーが働いて地場の強弱作用と深く関わる。すなわち、直流型エネルギーが強く働くとき、人の物性もまた精神的感応を強めるが、交流型エネルギーの費消を高めると、前記の媒介作用を受けて、電圧や磁場の強弱は人名そのものを左右することになる。
例えば電気抵抗率の指標を示すものに、抵抗温度係数(TCR)、変化値(ドリフト)、雑音(NF)の物理量計測法があるが、これらの数値が高まると停電より恐い脳障害さえ免れない。こうしたメカニズムが霊媒衆の真贋を見極める際の筆者の拠所であり、霊操(マインドコントロール)を祓い清め、実証および論証の統一場としての以下の史観に通ずるのである。
●神託という奇跡物語の正体
通説に従うと、シャーマン(霊媒衆)の語源はツングース族に由来し、シベリア、アメリカ、アフリカなどの先住民の間に出現したと伝わる。日本では巫(かんなぎ)の字が当てられ、神に仕える未婚の少女を指す場合は巫女、また男の場合は巫覡(ふげき)といい、神楽を奏し、神慮を宥(なだ)め、神意を覗い、託宣を告げる呪術を使う職能もある。祭政一致を旨とする社会では、神託が国家の命運を左右することもあり、神界、霊界、自然界などと霊的な交信を行うときには、大別して二通りのトランス(恍惚)状態が見られるという。一つは神霊(みたま)がシャーマンに乗り移る型、もう一つはシャーマンの魂魄が新霊界または自然界を行き交う型とする。これらのシャーマンを尊信して、神霊あるいは死霊などの霊的な存在を認める風潮がシャーマニズムである。また大和言葉で界を「サカ匕(イ)、シキリ」と訓(おし)え、霊を「ミ、チ、ヒ」と訓えた名残が、現代日本語にも生き続けている。
古代ギリシアの都市デルポイを賑わせたシャーマンの物語が広く知られる。この物語は都市デルポイでシャーマンがアポロンの神託を告げることが要点だが、この神託を聞くため集まるのは各国の大公使はじめ、情報を求める衆生(迷う世界に留まる全ての生物)が主流となり日ごと増す賑わいの中、いつしか都市デルポイは情報交換の場として国際市場の中枢を占めるようになる。その繁盛記が擬似バブル崩落に行き着く顛末は歴史に常に繰返されるパターンゆえ、多くを記す必要はあるまい。神託授受に関して、その人選と交接信号をはじめとして情報化されるプロセスほか、そもそも神とは何ぞやが判明しないままに、何ゆえ人は神を叩いて集まるのかが問題である。
前記の通説に従えば、シャーマンの霊的交信はトランス状態と見なされ、交接信号の公式も証さず、直流(テレパシー)と交流(情報化)の関係も解かずに当たるも八卦で占うため、神託は単なる詐術か仮設にしかならないのである。
神界、霊界、自然界を自ら行き交うシャーマンが神の正体も証せないまま、独りで神託に酔う遊びは善しとしても、その神託が大規模な権力を形成すれば、現時国際法では独占禁止法の網に掛かるが、通称九・一一事件後に米大統領が発した声明は独禁法などを突き抜けて結果は進退きわまる状況に難渋している。大統領本人がシャーマンなのか、あるいは側近にシャーマンがいるのか、その所在が何であれ悪の枢軸国を指定した大統領に開戦決行を促したのは、大統領自身の「神託による」との声明であった。
さて、神託が絶対的な正義とすれば、シャーマンの言い分もまた正義でないと「奇また珍なり」ということになる。神に託されたと装って衆生の迷いを切り離せば、その邪気を集め暴走する。すなわち都市デルポイの神託物語は殷鑑遠からずで、現代でも常に繰り返され、多数の自称シャーマン(占い師)が実在しているのだ。
人脳が電脳を頼る電子社会において、その要衝路は情報を電波にて伝播するロードマップに示されるが、問題点は通路が構造不全で成立していることにある。電気デバイスが雑音を出す代表的な原因は熱であるが、その過程では電荷の発生と消滅による雑音のほか、パワースペクトルの密度が周波数に逆比例する雑音も生じる。生命細胞の内部は外側に対して、負に帯電する性癖をもつが、心臓は収縮に先立ち、心房上部の洞結節にある細胞から電気的パルスが心室筋に届くと、心筋細胞は次々に脱分極を始めて、先端が波面の如く広がり、結果的に身体表面に電位分布が発生する。これを利用するのが心電図であり、その装置を狂わすからとして、電子端末は設置場所の近くで使用しないように警告が行われる。すなわちシャーマンの交接信号は波が実相であり、その波長と波形は相対性理論と量子論の確執として、いまだに実証も論証も統一場に達していないのである。
●アリアン説とノーベル・ショー
さて、日野はアリアン人種について「纏頭回は『アリアン』人種なるも、現今はほとんど清国人に類化せり。・・・その特徴なお全く消滅せず、男子は鬚髯(しゅぜん)ともに密かつ美に、眉目の間は自ずから白皙人種の骨相に酷似する所ありて、女子は殊に然りとす・・・」と言っているが、そのアリアン人種に触れておきたい。西欧中心主義の我田引水によれば、アリアン種は彼らの流儀の仮説つまりギリシア語の「愛智」に基づき、西北印度に根ざす印欧語族を誑かし、世界と人生を客観的・理性的に追求し、インドに侵入した白皙人種が現地の古代宗教を借り彼らの流儀に改変のうえ、人の本能的属性たる知を刺激したことは間違いない。後世この刺激に誘われ、彼らの死生観を哲学と訳すのが、西洋にかぶれる日本の知性派である。
哲学も所詮は宗教の亜流であって、白皙(白色)人種とは形而下的特徴の分類により、直毛または波状毛、その身長は比較的に高く、狭く長い鼻、豊富な体毛など挙げられ、頭の形や皮膚の色、毛髪の色においてかなりの変異も生じてくる。この人種は更なる分類として北欧人、アルプス人、地中海人、ヒンドゥー人などに分けられる。このうちヒンズー教の聖典ヴェーダを改変のうえインドの民を南北に分断すると、上層階級と下層階級の間に分裂と敵対と感情を醸成して、植民地分割統治を進めたのがアリアンといわれ、軽佻浮薄の言論を通じてアリアン学説なる暴論が普及していく。この妄説を覚醒させるには国土を王と定めて、最高位の人を副王と決した、史上最初の帝国アッシリアの代まで遡る必要あるが、当面のテーマたる真贋大江山霊媒衆に則って別の方法で解くことにある。
本年(皇紀二六六八年)ノーベル・ショーは物理部門三名、化学部門一名日本人授賞を決し、商業メディアの動向調査を終えたが、「オワンクラゲ」と同じ傾向を示す化学部門において、素粒子研究から派生した分野に量子色理論がある。古代ギリシア語アトムを日本では原子と訳して、陽子、中性子、電子の粒三種を素元的粒子という意味で素粒子と訳す。今ではさらに小さいフォトン(光子)や、ニュートリノ(中性微子)、陽電子(電子反粒子)の発見を通じてクォーク説が提案され、点状の粒子クォークは紐の如きものに結ばれると仮定、これを力尽くで取り出そうとすれば紐が千切れるため色を配したという仮説が生まれて、量子色理論と名付けられる。つまり、赤、青、緑の三色を合わせれば白色になり、白色ならクォーク単独の出現はないと、説明さえできれば何でも有りの現状がノーベル・ショーの実相である。
素粒子間に働く相互作用四種とは、重力、電磁気力、弱い力、強い力と知られる。うち重力は軽い素粒子レベルだと、非常に弱く精密測定に掛からないという。電磁気力は化学反応のすべてに不可欠の支配力をもつという。弱い力は極めて短距離の作用をして陽子を中性子に変えるため、当初は電磁気力と異なると見られたが、統一理論の出現で両者の力の源を同じとする方向に転じられた。強い力はπ中間子が、陽子と中性子、陽子と陽子、との間に交換される核力のことであり、一〇のマイナス一三乗センチメートルの距離に限り働くという説の下、サイエンスが現時の国際社会をリードしている。ただし、これに政治が応じるか否かは全く別物であって、東インド会社を例に引くまでもなく、白色の性癖は歴然であり、勝ち戦を企む知の暴走も詳しく論ずれば論ずるほど底が割れてくるのだ。