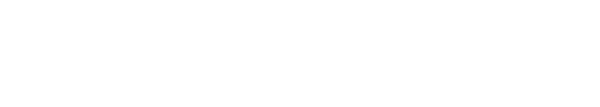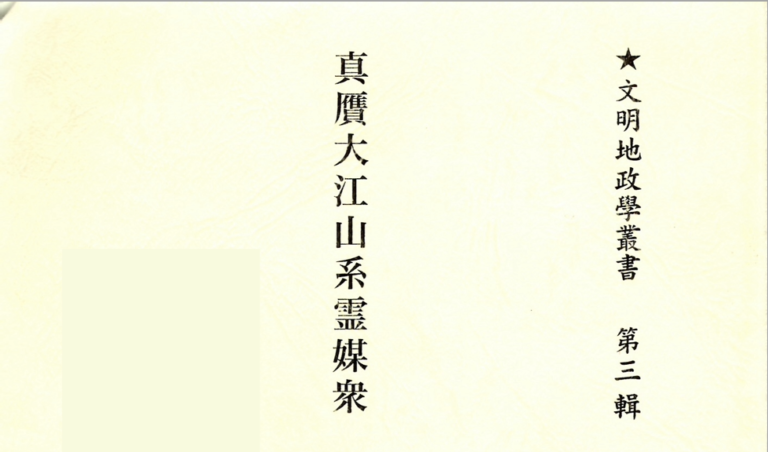●道義を喪った政策の陥穽
通説では西郷と大久保を対立させて共時性を伴う場の歴史を誤魔化すのを常とするが、これは現今の政治も踏襲する性癖であり、道義の廃れた権力が政策に行き詰まるとき、必ず言い訳に使う方便にすぎない。神の子と仰いだキリストを十字架に晒す思想は、その祟りを畏れて西暦を定めるや、百年を一世紀として節目ごとに「チェンジ」を装うのだが、その内実は分派分立に根ざす異種混淆の移動民国家が興じる賭事でしかないのである。たとえば、現時の日本社会を率いる暴走勢力も、「百年に一度の・・・」と鸚鵡返しする伝染病に冒されながら、日本の百年前の歴史は一顧だにしない。
百年前、すなわち大陸二国との戦役を済ませたころ、日本は戦費を調達するため海外資本に国債や社債を委ねていた。赤字財政は今も変わらないが、現在は債務を国民貯蓄が上回るため、脆弱な政府を支える体力を有するのだ。問題は物質的心配はなくても、精神的な強靭さが百年前に劣ることにある。再び世界が御破算に願いましての便法に揺らぐなか、同盟依存の政府は戦争も回避できず、いつか来た道をたどる不様を晒すことになろう。
個人情報を弄ぶ現時の千切取り思想は迚も百年前の比ではなく、構造不全の電脳回路に宿る雑菌が世に横溢して、先送り政策の「チェンジ」で御破算を繰り返している。もとより人は五十歩百歩の生物ゆえ、男が女に化けたり、女が男に化けたり、それを職能とし、それに憧れたりする風俗を払拭することはできないが、この「チェンジ」も千切取り思想の為せるところである。それもこれも、飽和状態を脱するため、道義を喪った政策が生み出す落とし穴であり、その通史には慈悲の念を禁じえない側面もあるが、人として連続性を断つ私的行為は常軌を逸している。
歴史上にも、たとえば男装して公に身命を投じた女傑に玄洋社を設立する先駆けとなった高場乱あり、その意を継いだ出口清吉の娘羅龍は馬賊の棟梁として、満蒙間を結ぶために尽くした川島芳子などを育てたが、現今の道義廃れた政策が生み出す「チェンジ」は私利私欲で連続性を断つ行為を恥じず、その流行病を弄ぶ現実に興じるのみ。敬天愛人の公は道義なき政策に殺されたが、その志は辰吉郎を求心力として結集され、その遠心力は古くから世界各地に潜在する在野の日本精神を刺激したのだった。
平成二一年(皇紀二六六九)という時空を百年前に巻き戻せば、現在の世界的状況を写像して余りある通史の連続性が浮かび上がる。史家は自らを鍛錬するチャンスゆえ、日々の世相をリアルタイムで解けば、現時の政策に歴史を読む力が働いているかどうか、答は歴然だろう。そうなれば、霊媒衆の真贋を見極めるのも、大した労苦は伴わない。ただし、表層現象は結果であり、その結果は何が原因で生じたか、その真相構造に潜む連続性を証すには力量が問われる。
つまり、戦争に勝つ手段が科学へと転じ、その兵器は後遺症を伴うこと、情報は欺(だま)し合う社会構造を生むこと、その原因は百年前に盛んとなり、その結果が連続を保つどころか様々な現象を生み出すことを弁えねばならぬ。
他方、その後遺症は似非教育に浸透し、日本の場合は無気力無責任な知的障害の官民がはびこり、神格を人格に貶めて恥じないまま、伝統に根ざした貯蓄性向を担保とし、公金の私的流用が当たり前の総白痴化も表出された。それは道義なき政策に群がる官民すべての性癖であり、似非教育制度を脱しないかぎり、決して改良には至らないが、性癖は意に従えば誰にも改良可能なことである。
在野に潜む情報を掘り当てるには、国際政治に必須の条約すなわち玉虫色ワードを解く能力があれば、誰にでもできる。条件は誰にも取り憑く邪気を祓えばよく、難儀に屈せず敬天愛人の公を貫くことだ。猟官運動に公は存在しない。邪気を孕まぬ子のハーモニーを開くとき、その音は凛と韻(ひび)く風雅を醸し澄み渡るが、その音域に行き交う霊言は開かれた空間の自在性を有して、私一切を放擲し超克の公へと導く力を備えているのだ。
これこそ紫禁城に入営した辰吉郎の道義であった。それゆえに、溥儀五歳に備わる忘我と韻き合ったのである。溥儀二〇歳に際し支那五〇〇年に及ぶ禁制地が開かれ閉じられた空間を出る歴史の旅立ちもまた、辰吉郎の道義のなせる業である。
人の本能的属性が厄介なのは、自ら閉じられた空間を好んで立身出世欲に駆られるからである。その都合勝手な立身出世欲を操るのが玉虫色ワードを多用する似非教育であり、結果として科学は蓋然性の閉じられた空間へ逃避するし、国際政治は兵器の開発に熱中するという現実となる。歴史を読む能力が問われる最大の職能は政策だが、公(道義)の不在を自白して余りある政策は官から民へとすべてを委任して恥じることがない。かかる発想こそ、在野で貫かれる敬天愛人に対し、道義不在の国際政治が自ら呪縛に陥った証といえよう。
●深層構造に潜む在野の情報
考古発掘が進む中で必ず浮かぶのは政府が歴史を改編するかどうかの決断を迫られる事態であるが、歴史改編は政策にも関わるため、優柔不断に陥るのが常であるが。そのために社会は世代間の疎通を陥落させたまま、似非教育だけが独り歩きすることになる。この現実が核家族化の拡散を増大させて、生活コストを支えるべきプライマリー・バランスも保てず、政府も果てしない財政悪化に右往左往を続けるのみ。かかる政府の描く未来図にとても信は集まらない。議会民主主義のもと、与党だ野党だと騒いでも、現実の社会構造は国民全体が生み出すのだから、経世済民を唱えれば唱えるほど、責任は自分に跳ね返ってくる。
さて、この現時に勝る塗炭の苦しみを再生に導いたモデルこそ、深層構造に潜む在野の情報であり、常に改めを繰り返す情報とは完全に種類が異なる。人は人たる生き方を欲しつつ、人たる所以を知性に求めるのを常とするが、その知性が病んでいれば使命の行末も儚く終わる。これが乱世と治世の違いで、日本の修羅は今後が本番である。
古来ジャーナリズムはシャーマンに発するも、現代ジャーナリズムはその本能自体が似非教育に蝕まれていて、病に気づいても免疫力が脆弱なために自ら命を投じる取材も成果は得られず、深層構造に潜む情報など掘り起こせるはずもない。それを象徴するものこそ「チェンジ」を持て囃し酔い痴れる衆生の姿であるが、寄生本能も露わな現代ジャーナリズムは自らも壊れゆく儚さに気付かない。
乱世において、辰吉郎を求心力とし、その遠心力により働き動かされた奉公こそ治世を狙う原動力だったのであり、治世の猟官運動は寄生体の駆動力ゆえ、常に保身の私利私欲が付きまとい公が遠のく危険と共存している。つまり、物質一種類が対で成るという原則は、治世を担う知性にも当てはまり、物証主義が高まるほど、政府の賞味期限も縮むばかりという惨状にある。
維新改革制度は西洋の行政を輸入して和魂洋才という妖怪の教育に公金を費やしたが、似非教育下に巣立つ妖怪は昭和の大戦を潜り抜けると占領政策に便乗して、玉虫色に化けていく祖国運営の要となり、国権最高機関を弄ぶ存在とは相成った。その結果、現時の日本社会は賞味期限を誤魔化す食品と同じく、国権の最高機関も賞味期間が短くなるばかり・・・。
閑話休題、古来日本の奉公に生きる在野の情報を掘り起こそう。皇紀歴を刻む前の日本列島は先住民集落のほか、渡来の移動民が加わるも、依然不飽和の状況にあり、それぞれ崇拝・信奉する宗教間に起こる争いも互いの生活を脅かすまで至らないでいた。ところが天は異常気象をもたらし、地殻は下部マントル層の活動で津波や地震を引き起こし、結果的に生じる衛生劣化が生命メカニズムまで破壊した。人知を越えた大変動に慌てふためく本能的属性は不飽和を求めるために、却って飽和状態を生み出すことになったのだ。その淘汰の過程を通じて自然発生的に求められたのが神格の統治能力であり、かくして飽和超克の型示しを以て肇国の基が据えられ、かつまた皇紀元年と定められたのである。
奉公の神格モデルは皇紀暦制定前にも存在しており、先住民も渡来人も、その威徳に順い奉公を身に帯び各種の姓(家業)を設けていた。この姓に巣立つ異能の先達こそ、皇紀元年から世界各地に配置されて、天文気象ほか場の歴史を情報化のうえ、生涯を奉公に尽くし悔い無き人生と自覚する達人である。この先達は男女問わず幼年三歳ころから世界の結界領域を修験の場とし、成年一五歳に達すると、その動向は広域に及んで、一旦緩急あれば義勇奉公これ天壌無窮の皇運に身を委ねて惜しまない。以下、この先達を「皇統奉公衆」と仮称のうえ、大江山霊媒衆や在野の浪士と区別、必要のとき書き加えていく。
辰吉郎を核心の陽子とすれば、皇統奉公衆は中性子に相当し、在野の浪士が電子軌道を埋めていくなか、大江山霊媒衆は陽電子の役に相当しよう。問題は放射性元素の如く自ら壊れるを恥じない政府にあり、その不規則運動は原子核88ラジウムが86ラドンに化けて目を眩ますように、妖怪の立身出世は私利私欲に塗れていく。ゆえに在野の規則的な運動が政府に使役されるなどという事態は起こり得るはずもなく、因子が異なる奉公は種の違いの歴然を証明している。こうした原則に気づかぬ史観こそが似非教育の産物なのだ。
さて、道義不在の乱世に当たって、袁世凱は溥儀一一歳の時に没し、孫文は溥儀二〇歳の時に没するが、その間に溥儀は辰吉郎を慈父の如く敬い成長する。溥儀一七歳に際して、王国維を師傅に推挙した升允六五歳は没八年前に当たり、その生涯に一四歳年少の出口清吉を深く信頼し、杉山茂丸とも強い結び付きのもと、日蒙親善の運動にも大きく寄与貢献している。日野強は辰吉郎の入営前年に没するが、出口王仁三郎に入蒙経綸を促した第一人者である。在野に潜む情報を知らずして玉虫色の歴史本を渉猟しても、過去と未来の連続性に道義は通らないのだ。
●辰吉郎入営三五年の要路
明治四三年(皇紀二五七〇年)から昭和二〇年(同二六〇五年)にかけて、堀川辰吉郎の神格は皇統奉公衆を通じ神格天皇三代の禊祓に順って働いたのであるが、それは単に日本政府の頽落を補うだけに止(とど)まらず、敗戦後の外地乱世を緩和するため、世界各地に重大な痕跡を刻んでいる。この皇統奉公衆の勇躍は潜在性を原則として、それがまた奉公の本義であるために、霊媒衆やあるいは在野浪士の働きに同化しても、その連続性を保つ伝承法は完全に一線を画しているのだ。
筆者が何ゆえに彼らとの所縁を結びえたのか、論じても詮ない話であり、この起稿途中で死するも、それが筆者の命運ならば、仕方あるまい。本稿の特徴は政府御用達の疑史に重複しないこと、さらには史家を装う売文情報に与しない点にある。個人情報が知りたければ日本の住民基本台帳を編纂する霊媒衆を取材すればよく、玉虫色通史の粉飾を解きたければ実証現場に潜む機密情報を取材すれば事足りる話だ。いずれにせよ分解と復元を繰り返していけば、千切取りの剥離は必ず偽物と判明し、本物は剖(わか)れることが判(わか)るように教えてくれるものだ。
皇統奉公衆は多国語を自在に操るが、日本語で話すときは、重要部分は必ず大和言葉を用いることを特徴とする。無駄口は一切なく、その仕種は柔和であるが、大胆な所作のなか、時々その気配を断つ場合があり、俊敏と持久という相反する両極を備えており、修羅を知る筆者も脱帽するほかない。
日露戦争五年後から昭和大戦終結の年まで三五年間であるが、これは人の平均寿命に受容可能な年数であろう。共時性を伴う場の歴史が如何に多種多様であろうと、支那大陸をターミナルとして、世界的ローカル線が入り込む状況を剖判していけば、その立体構造が過去と未来の連続性に通じるのは歴然であろう。
日本の場合、政策を蹂躙する猟官運動の増長は止まらず、軍閥が頽落していく様は改まらず、天誅は関東大震災という形を以て顕れるのだが、政府は神格天皇の禊祓に頼るだけで、青年将校が発起した二・二六事件すら神格天皇の直裁を仰ぎ御心痛を患わす始末となる。
支那大陸では、列強勢力の欧米露が利権争奪の丁々発止を展開しており、すでに植民地化されていたアフリカやアジアを巻き込み、いかにも西洋式風俗ならではのインターナショナリズムまで吹き荒れるなか、肝心要の北京には自立政府が不在という為体であり、辰吉郎の入営なければ、あるいは満洲国建国なければ、現在の北京政府などは夢また夢の幻だったであろう。
前稿中「敬天愛人の道義は死なず」に記載した人物たちは、堀川辰吉郎以外は史家の知るところ少なからず。彼ら自身が得た情報の解析に際して、その情報と解析を補うため、大江山霊媒衆が加わることもある。だが皇統奉公衆の場合、その身に帯びる情報の価値観はまったく異なっており、神格以外に判断不能の事案が多くある。つまり、皇紀暦以前の不飽和状態に巣立つ彼らのネットワークは不飽和を保つ遺伝子が備わるとともに、飽和状態の到来と超克のプロセスも遺伝情報に組み込まれており、その伝承一貫性は連綿して、厳しい環境下で育まれるため、奉公の心髄が骨身に徹している。
たとえば、未曾有の天災などが起ると、人の本能的属性は天災に人災を加えるものであり、そのとき、政策を預かる職能の杜撰さとか日常の危機管理不足などが表面化するが、皇統奉公衆は危険を日常的に体認しているため、公私の分別を瞬時に透徹して、至高の行動成果を挙げる。それは悠久不断の遺伝情報とともに、その情報の普遍性を保つ日常生活がなければ、瞬発的に出会う緊急事案に対して奉公の神髄を極める結果などは生まれまい。辰吉郎の入営三五年の要所には皇統奉公衆が不可欠の存在であり、それがゆえに、辰吉郎を求心力として遠心力を強めて働いた杉山らも、辰吉郎に関する情報は表現しようがないのだ。
論壇が賑わう思潮は何処より生まれたか。これも発祥はシャーマンにあり、その神託が功を成すと信仰が広がり、やがて神の正体は不明のまま、宗教化されるのである。人の都合勝手を統治するために統帥権を伴う議会が生まれ、論壇の場が賑わうようになる。これら場の歴史を掘り起こすとき、共時性を粗末に扱う史観は道義が通らず、必ず歴史認識の違いから争いの火種が燻るようになる。燻る火種が燃え盛るのは天変地異により人体の本能的属性が暴走するときだが、これが同時に飽和状態に陥る始まりともなる。
誰もが知り得ることであるが、これを天変地異ではなく、人為的に企むのがマッチ・ポンプであり、かくて放火と消火を仕掛けられた支那大陸は、世界列強の戦場地となったのである。その火種は中華思想と西欧中心主義にあり、その根が互いに絡み合い縺れ合うようになれば、閉じられた空間の中で養分を奪い合うのは必至であり、思想とか主義などは開かれた空間の千切取りでしかない。その結果、養分を枯渇した根はうら枯れを免れず、それが地上に浮き上がり天日に曝され風が吹き荒べば摩擦で火がおこり、山火事のように燃え盛って火種が散るのも当たり前ではないか。この火種を最小限に鎮めるのが辰吉郎の紫禁城入営の要諦であり、そこにこそ皇統奉公衆が活動する素地もあったのである。