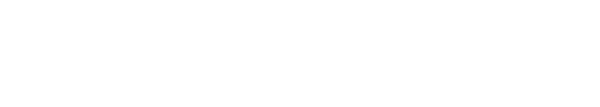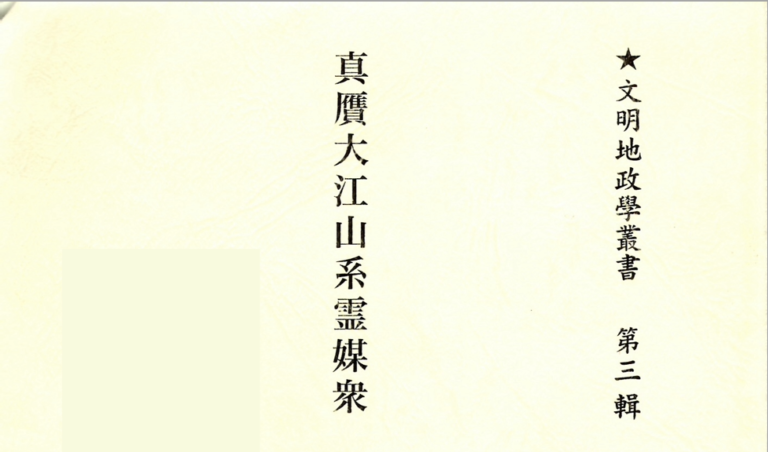●漢人について
日野本の監修によれば、漢人が中央アジア移住民という支那説は古い空想であり、ホタンの人が周囲イラン系の人に比べて、支那人と似ているのは、ホタンがチベットからの出口ゆえに混血の度が高まるだけで、ここを漢人の現在地とする証拠はないという。これ尤もらしい註で筆者も意に含むが、日野本の禊祓が終るまでは、筆者も持論を封じることとし、あえて日野の記述を要約しておきたい。さて、漢人はアジア系統中の蒙古人種に属して、その発生地は葱嶺山麓すなわちパミール高原の付近なりという、と日野は書き始める。約五千年前パミール東方渓谷に沿い降る漢人は、ユイテン(于闐)すなわち現時ホテン(和闐)に来たり、付近の広漠な沃野を遊牧して土着したるなりと。されば和闐には、なお子孫が多いと北史は述べる。古名を辿ると、ホテンはユイテン(ウテン)またホータン(赫探)とも称されたが、ホータンは回語ゆえ漢人部落の意義を含むという。けだし新疆中ひとり和闐のみは、最も古くより開けて、農工業、文学、技芸、宗教など夙に発達、その範を他に垂れること多きのみならず、遠く西蔵やインドに及ぼしたるの形跡も見られる。これ数千年前の古銭、古器物を発掘できるため、歴々これらを考証し得べきもの少なからざるをや。彼ら于闐にあること数世、東方の美土を知るや大部分が于闐を辞して、秦嶺を超え、黄河、揚子江に沿い行く行く支那中央に出て土着したり。当時その地にロロまた苗族など土蛮の棲息あり、これを彼ら駆逐すると黄河、揚子江の付近に大帝国を建てたり。爾来、彼らは人口増殖を促すために、家畜を飼い農業を盛んとし、市街を作り、文学、技芸、宗教など奨励して工業の開発に勤しむ施策を推進した。これ支那帝国の基礎で新たな独立語を生み出すや、支那を本部として、蒙古、満洲遠くマライまた南洋諸島に及び、果てはアメリカ大陸にまで蕃植を広げる。この東洋史上に稀なる人種は、支那歴代の帝王、宰臣などを寡占する市場を形成して、帝国の文明開化を振起したり。帝国創肇以降、彼らは幾多の興亡変遷を経過するが、宋末蒙古に滅ぼされ、祖衆以来の政権は全く他種族の手に落ちたり。彼ら漢人種の来歴を知るため、日野は北史など文献のほか、伝承を含め当時新疆に住む漢人の素性を調べた。新疆南北路に散布せる漢人種は何処より移植したるか。新疆の地はインドや中央アジアと近接するため、早く開けし于闐より分布したる種族の経歴とは、アラビア宗教軍侵略に続いて、匈奴また蒙古などの攻撃があり、ついに異種族が占拠する所となり、既に先住人種の原型を残す形跡が見られない。伝承これ于闐住民のみ語るところ。
于闐住民のみ祖先の基盤に立ちて動かず。アラビアの宗教軍に抗し、二五年あるいは一三年間を互いに勝敗ありしが、衆寡は遂に敵しがたく降伏したり、その改宗やむなきに到りしもの。後に天山北路ウルムチ以西は凡てジュンガルの牧場、盛時は人口百数十万人に達するも、うち大凡四割は痘疫のため祓い去られ、三割は西暦一七六〇年の兵乱に死して、二割は露領を遁走したり、清兵戡定(鎮定)後の北路は残一割の生存者にすぎず、広漠の沃野は空虚に帰するところ。このとき清国が施したる策、歩騎兵および各種人民を移住せしめる屯田拓殖なり。歩騎兵として支那本部より移住したのが漢人種である、農工商の民を形成して、イリその他の都城に広がり、現時南北両路に居る漢人はこの種族なり。
●満人について
アジア系シベリア種族に属するのが満人なり。いわゆるツングス(通古斯)族にして、通常これマンジュリヤ(満人)とも称して、もと蒙古族より分かれ、のち他種族と混血したる種なり。かの異名に東胡、靺鞨(ばっかつ)、契丹、女真と称するが、みな同じ種族を指す。言語の特質は日本と同じで「て、に、を、は」を使う漆着語であり、宗教は往時シャーマン教を奉じて、古くからブリヤーツ種族が住む東北地方を占有し、満洲吉林付近を主部に、北は北氷洋、東はアムール地方の東方にまで分布した。彼ら一朝勢力を得るや、支那本部に侵入して、漢人を征服すると清朝成立を成し遂げる。満人種は宛然(えんぜん)大堤の潰決して水の卑きにつくが如く波及して、本拠の吉林付近は逆に空虚の有り様となれり。彼ら言語風俗に八〇〇万と算するのが現状なり。そもそも彼らが新疆に遷移したる要因たるは、康熙征西の際に討伐軍に従い、平定後に駐防隊となり北路に永屯したるを初めとす。由来各都城の文部官附あるいは農工商に従事して、この地の祖先たる形跡を刻んで現時を形成したり。され、漢人は由来異種族を同化する妙あり。満人は元来特異の文字言語を有するも、全く漢人化するや漢語を話したり、漢字を用いて、固有の言語文字を喪うも惜しまない。風俗習慣もまた漢人化しており、多年旗人として、清廷からの殊遇を受け、徒に自尊の心を長じて修養の念を欠き、武芸を練らず、殖産を勉めず、安佚を貪り、勤労を厭い、かくして漸次国家の藩屏たる素質を消失するにいたれり。これに大いに矯正訓練の法たるを講ぜずんば、時勢一朝を凌ぐ辺警あるに会せば臍(ほぞ)を噛むも及ばざるなり。
●漢回について
ハンホイは帰化人にして回教を奉ずるのほか、言語風俗の漢人化したる部族いわゆるトンガン(東干)なる、即これなり。物の名称は往々その沿革を語ること多く、トンガンとはトルコ語でトルガンともいい「残りし人」のこと。出所について諸説あり、次三点は例示したり。先ず一は「唐代、ウイグル(回鶻)を征するや、族一〇〇万余戸を、支那本部西方の広野に移住せしむ。トンガンは実にその後裔なり。ウイグル人は新疆土民と交通し、マホメット宗に帰依するも漢人と接近してのち、婚姻を重ねて次第その風に化し、ついにカシガル地方の同種族と差別される」。第二は「トンガン人の一揆は、初め甘粛トンホワン(敦煌)で起こり、最初謀反の伝報その地名使いたるもの、後には叛民の称号に変ずるなり」。第三は「初め元のチンギスハン支那に侵入して、トルコ、トルキスタンからマホメット宗を奉ずる人々、多く従軍し来たりて、この時漢土残留の人々これなり」。出所がどうあれトンガンの称これ地名の転訛とするは全く誤謬だと、日野は以下のように説く。
各記録また古老の言を借りて考えるに、トンガン種族は唐がウイグルを滅ぼしたとき甘粛辺に移住、後チンギスハンに従軍したが、居座り漢化したる西トルキスタン人で、いわゆる帰化した漢人の謂(いわれ)なるべし。トンガンの称は既に叛乱以前から存在しており、唐以来ウイグルの辺民や帰化人など種々混交する民族となりしも、大部は露領サマルカンド地方より帰服して、祖先がトルコ種族たるは疑いなし。日野は以下その来歴を記すが、監修その来歴を誤りだらけといい漢化の祖はイラン系ソグド人と註する。本稿これを承知のうえで、日野説に註を補足しながら以下要略するが、その義は本稿の後半で明らかとなる。さて、遠く春秋時代の中央アジア・アルタイ(二台)山付近において、広大なる面積を有せしトルコ種族の居住地あり、これ次第に中央アジア一帯および天山南北路もしくは南方アジアトルコ国に分布して、かの獯鬻(くんいく)、玁狁(けんいん)、匈奴、柔然、突厥、黠戞斯(キルギス)、回鶻などの種この種族なり。元来中央アジアの歴史は錯雑いわゆるモンゴリアンの移動経路等は明瞭ならざるあり。ことに獯鬻、玁狁はモンゴリアン種一つのトルコ族は確かなるも、その遷移する沿革は詳らかならず。されど匈奴が秦時代に大運動を起こし、秦や漢を侵すこと度々にして、かつ中央アジア各国を侵略したるは広く知られる。匈奴は漢宣帝の代に南北二派に分かれ、南匈奴は微弱で漢に帰服したが、北匈奴は勢い強く辺境に冠(こうぶり)せしも章帝に被る所。その一部は、遠く裏海の浜へ遁れ、残余の多くは所在各国に走りたるが、東漢の代に再び勢いを恢復して突厥(トルキ)国を興したり。ここで註があり、突厥(テュルク)が匈奴系という根拠はなく突厥国が興るのは南北朝末で、東漢(後漢)では未だ突厥は現れていない。
突厥国(トルキスタン)は世々アルタイ山の南にありて、柔然に属したりしも、南北朝のころ以来、東のキタイ(契丹)を撃ち、西は柔然、エフダリツ(嚈噠)、キルギスなど各国を侵略し、一時は東に満洲を見て、西はアラル(阿拉爾)海に連なり、北にバイカル(貝加爾)湖を包むがごとし、南は遠くの青海を合わせたが、内訌あり、東西二国に分立して、西突厥は東ローマと通じてペルシャに攻め入り、東突厥は当初支那(隋)に服せしが、次第に領土を広げて、唐代高宗の如きは、執政これ兵を借りるに至りしも、驕奢に耽り、終に太宗の膝下に跪き、滅亡後その地に興るのがウイグル国で、西突厥国もまた次いで滅ぼされる。元来ウイグルは漢滅亡後に出る鉄勒(てつろく)部族たり。突厥滅亡するや、けだし今の甘粛以西、ハミ、トルファン、カラサル、ウルムチ辺りを総称する西域の地に一半みな雪崩れ込む。この記述に註あり、ウイグル国は外蒙古オルホン河畔ハラ・バルガスンの都城廃墟を中心地としており、西城への移住は既存国倒壊(八四〇)後ゆえ、最初からウイグル人が東トルキスタンに居たかの如き誤解は正すよう補足している。日野が記述の裏付けは宋史「ウイグルは匈奴の別裔にして、初め鉄勒のちウイグルと呼ばれて、甘州以西、ハミ、トルファンに住す」と、五代史「甘州をウイグルの牙とす」ゆえ、以てトルキ遺族民のウイグル入りを知るとなる。以下も日野記と註記の併記三ヶ所あることを予め承知されたい。さて、他一半は西方タジク国へ奔り、次第に勢いを増すと、遂にインド一帯の地も包有せし、これも慢心絶頂に達すると、邦の勢い次第に衰え終に西遼の併呑する所となり。註いわく、ウイグル一部がセミレチェ地方のカルルク族の中へ逃げ込む事実はあるが、トルコ系カルルク族も西遼に帰属していてインド地域を包有する事実はないという。さて、未だ幾ばくの突厥さらにホルムズ(花刺子摸)地帯に起ち上がり、ペルシャを統一して国勢を復す、乃蛮(ナイマン)(外蒙古)部クチュルク(屈出律)族と諜じるや、西遼を亡ぼし、余勢は中央アジアとアフガニスタンを略取サマルカンドを都とす。
註いわく「幾ばくの突厥・・・」これ前記突厥国と関係ないトルコ系という。つまり、西暦一一世紀に建つセルジュークはペルシャを征服したトルコ系国家で、ホラズム県知事アヌーシュ・テギンの子孫は同一二世紀末セルジューク王朝を倒して、国名をホラズムに変更した。ナイマン族の王子クチュルクにより西遼の帝位掠奪(一二一一)は、ホラズム王スルターン・アラー・ウッ・ディーン・ムハンマドの援助によるもので、サマルカンドに遷都(一二一〇)したのはムハンマドという。さて、のちのカシガルに勃興せし回教徒ブグラ(布格拉)は、葱嶺を越えサマルカンドを征服その虜を引き連れ凱旋する。のち虜の大部を帰らしめすに際して、天山南路各地に土着の民あり、回語では遺種の義をもつトンガンここに起因せり。註いわく「ブグラ」とはセミレチェ地方カルルク王族サトック・ブグラハンで、カシガルを拠にトルコ系で初めてイスラム教徒となり(九四〇)、いわゆるカラハン朝から西トルキスタンのサーマーン朝(イラン系)と戦い死去する(九五五)。後年(九九九)サーマーン朝を亡ぼすカラハン朝は、西トルキスタンを支配したので、セルジューク朝やホラズム朝は時代が前の話であり、漢回との間には何の関係もないと補足がある。さて、のち同じ種族の漢回チンギスハンに従軍せし、これ支那に侵入せすとき、各地残留も少なからず、この回民みな清朝に帰服したり。これら言語、服装など悉く清人同様に改めしも、一に宗教のみは改めることなり、以来この種族は次第に蕃殖し来たりて、支那本土の各地ことに甘粛諸州から天山南北路の各地に広がり、現に清廷の兵役に服する装丁多数を占める。
東干すなわち漢回は常に清人と和せず。けだし宗教人種の異なるによる。その反目疾視から両者間に小事変(一八六二)が勃発これを契機として、東干叛旗を掲げ宋旨軍と称するや、清廷の官吏を屠り城邑を破りたり。ときに四方の東干一斉に蜂起して、その装丁戍兵(じゅへい)となる者みな変じて応ずるや、南北路諸城の纏頭回もまた倣いて、新疆全部は大修羅場と化していき、南北両路ついに悉く東干の手に落ちる。清朝の危機に左宗棠(さそうとう)が進軍(一八六六)、これ大いに振るうも平定(一八七七)まで険しい戦闘を強いられるをや。当時東干の勇武および戦略につき、やや見て足るもの少しとせず、知らず、現今の東干また当年の意気ありや。今この族の状貌を見るに他のトルコ種と比較すれば、大体同族と異ならざるも、ややキルギズもしくは蒙古族に類似が多くあり。これらから、東干を回鶻の子孫あるいはトルコの種族となすは、ただ彼らの祖先以来の運動経路を単に一面より見たる結果にすぎず。
●カザク(哈薩克)について①
日野はカザクを、トルコマン種に「ウズベック、スラブ」が混血して、蒙古族と深き関係ありと記すが、註は「カザクもウズベクもトルコ系だが、スラブの混血とはロシア系コサックで混同誤解あり」と補足する。され、蒙古(モンゴル)一支族たる北匈奴は漢に滅ぼされるやその過半降伏せしも、他は遠く西北に奔り、暫く裏海の浜に留まり、後に中央アジアとの間に突厥国を築き、次いで東西二派の分かれとなり、西突厥はペルシャを略し、その部族から突厥可薩(テュルクカザック)という派が生まれ、これが露国南方いわゆるロシア平原の中枢ドウネープル河辺に至りて遊牧のほか、他はキルギズ族と混合したり。註「可薩(ハザル)は西暦二世紀末から同一一世紀にかけて、コーカサスからヴォルガ河、ドン河の間に住んだ遊牧民ゆえ、トルコ系かイラン系かは不明で、カザクともコサックとも関係ない。またドニェプル河辺での定住はコサックである」と補足している。
註は註として、日野の渉猟を続けると、突厥可薩部はドウネープル河辺を永住地と定め、由来漂泊的剽掠(ひょうりゃく)を試みたり、あるいは付近の遊牧人種を指導誘掖しつつ、漸く土着の計を成す族カザクの祖先とす。ドウネープル河の下流は当時リシアニアと蒙古との境界たり。カザクはポーランドの虐政を厭うて遁逃を企てるリシアニア人の投来に対し、仮に与える避難地を設けたり。然れども、健躯豪胆のカザクは避難の条件として、常に急湍激流の中を渡渉せしめ勇気と胆力を予め試し、これに合格のリシアニア人を部下とせり。以後リシアニアの婦女またコーカサス、スラブの婦女も入れて妻や妾とし、年々その部族の増加せしも、後キルギズさらにカルマク(哈爾瑪克)などの蒙古族とも相混じりて、中央アジア広野の間を遊牧せり。註には「カルマクはモンゴル系オイラット族ことにヴォルガ河畔に移住とトルグート」とある。けだしシベリア地方の各カザク族は大凡この雑種族なるがゆえ、露人これを一体にキルギスまたカイザクと呼称したり。以下の日野「カザク」説は監修「コサック」説が正しいため、本稿ではコサックに改め参考に付す。
さて、平素巨木をえぐり、粗の船筏を作るコサックはドウネープルの急流を馳せるや黒海に浮かび、トルコの船舶らに掠奪を加えしが、のちドウネープル河よりはドン・ヴォルガの二大河畔を有利と見て転居したり。コサックは水上活動と同時に陸上活動も試みると、スラブ族を征服、一時は毎戸あたり栗鼠一頭の課税を施したり。当時露国は他方面に強敵が多かりしため、巧みにコサックの歓心を買いし程なれば、彼ら少しも他の制御を受けず宛然自由の国家を作りて、広大なる原野を放浪しつつ、残忍殺伐の気風を蒙古に習い、これと兵を交えるや、兵機謀略を学び取り剽悍なる騎兵隊も組織したり。爾来、露国の先駆となりて荒漠千里の平野に他の遊牧せる種族を逐攘、土着的人民の移住を助ける展開、さらに鹵莽(ろもう)未知の道路を拓く働きなど、露国の侵略尖兵としての貢献偉大なり。彼らシベリアの大河から黒竜江、ウスリ太平洋の沿岸に至るまで悉く勢力範囲に収めたり。海の海賊、陸の遊牧頭目として剽悍に土地探検と侵略に従事したり。露国が広大なるシベリアを拓殖し得たるはコサックに負うところ少なからざるべし。
現時、天山北路の山野に遊牧する約三〇万のカザクは、ドン、ヴォルガのコサックの模範たり。その所以を査するに、彼ら露国の宗教干渉と租税徴収に対して不快の感に堪えず。水草を追うて東に向かいシベリアに遊牧したりしが、漸次支那北境に来たりキルギズに帰属して、次にジュンガルに服従したるなり。斯くて新疆西北地方の水草豊富なるに加え清廷の寛大なる宗教の自由を知り、その故郷ドン、ヴォルガのカザクこれを伝え聞き、同胞を慕うや年々到来を増して子孫漸次蕃殖して現今の如き人口となりぬ。カザクは体躯やや大にして、細目隆準の瞼辺淡紅色を呈し、眉目秀明は艶容ある者少なからず実在したり。これをドンまたヴォルガのカザクに比するなら、肉色の点において少し異なる所あり。思うに彼ら新疆に来たる後、他種族と混血また気候風土で異なるの結果なるべし、彼ら言語文字は纏頭回と同じきも、談話を交わすと多少の訛りあり。けだし彼ら纏頭回と同一なるは、同じ宗教なるため自然接触が多く頻繁なりしによらん。性質は極めて素朴にして、これに接すれば仙人と交わるの感あり。彼らは年月を知らず、自己の年齢を弁ぜず、歩行するも遠近を解せず、全く数理的観念が欠如せる特質あり。然れども、ただ感嘆に堪えざるは次の如くなり。
彼ら老幼男女みな乗馬の術に長じて巧妙なるは多種族の企及すべからざる所。その遊牧たるも競馬のみ。彼らひとたび鞭を掲げ疾駆するや、鳥が空中を飛行する如く見えたり。地の険夷は更に眼中に置かざるなり。漢人は彼らを評して人を以て馬に膠着したるに同じといえり。吾人乗馬の技術において、如何ながら到底カザクの女子小児にも及ぶべからず。その乗馬は実に独特たり、世界無比というも過賞にあらざるべし。男子は馬鞍を製作する者のほか、他に何ら技工なしといえども、馬具製作は天下唯一の副技として最も相応しく、これまた独特の長技で金銀珠玉を鏤(ちりば)めたる馬鞍は美観その目を驚かすもの有りて、百金以上の価値を有する鞍に跨るは、敢えて珍しからざるなり。往昔鉄蹄亜欧の間を蹂躙したる、カザク当年の勇猛なる面影を現今また見るなくも、これを許すに足るべし。
ブルトはモンゴル人がキルギズ族を呼ぶ際に使い、往昔天山北路の烏孫国たりしとき、キルギズ高原より帰来混交せし民族とす。欧人これをカラキルギズと称する。カザクと言語習慣ほぼ同じくして、現今これら東西二派に分かれ営むが、大凡イリ西南イシクール湖辺に遊牧する者を東ブルトといい、カシガルの西およびヤルカンドの西南、葱嶺の山野に遊牧する者を西ブルトといえり。西暦一七五八年、清兵がイリからジュンガルを追い西南に入りしとき、東ブルトの酋長これ全所部を率いて帰服する。その衆は約七千余戸という。後清兵ヤルカンドとりプラニート(プルハーヌッディーン)を追うて、西葱嶺を超えるとき西ブルトも続いて、大凡その部族二〇万と註記される。然れども、後多くが露国に帰化して、現今南路の辺境山野に遊牧する種族その小部分に過ぎず。ブルトはカザクの如く肥満長大は少なくして、概して風采あがらず、女子はカザクの女子と同じく白布で頭部を包むも、高く纏うところが異なりとす。