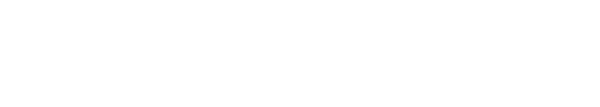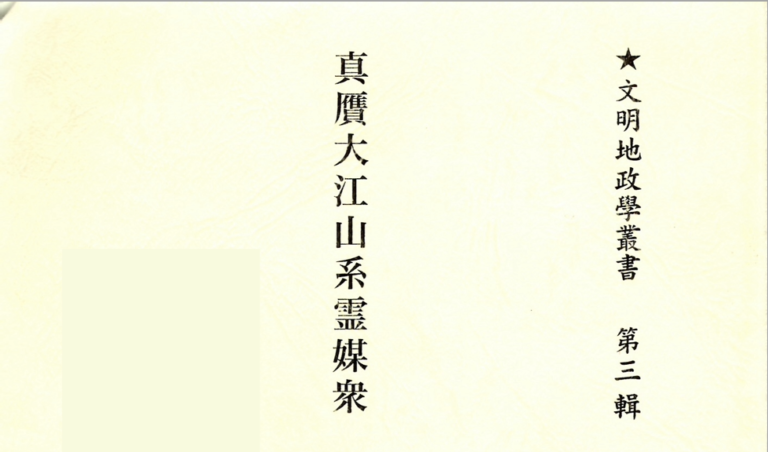●日野帰国までの概略
イリ惠遠城から寧遠城(クルジャ)まで達すると、伊犂副都統は日野に良馬を贈呈して、守備中尉馬高陞の率いる護衛兵一〇名と通訳一名を伴わせ、カラシャール到着まで便宜を尽くして日野を遇した。
それ以後、日野はクチャおよびアクスを経てカシガルに着くと、大谷光瑞の手配により、インド入りの世話になる英領インドの貿易事務官マカートニを訪ねたのである。
挨拶を終えた日野は光瑞に安堵の結果を打電するとともに、ウルムチの長庚や王樹枅にも電報で礼を述べた。次に行く地をヤルカンドに定めて、同地到着後はカラコルム超えの準備を整える。その絶頂を何とか超えて、インド側最終地点ラダック地区レーに辿り着く。そこでヤルカンドで雇用した人馬を犒い里に帰した。
カシミール首都スリナガルに入ると、中央アジア探検で世界に有名なサー・フランシス・エドワード・ヤングハズバンドがおり、同じ体験をした日野は表敬訪問を通じて意を交わした。またボンベイ(現ムンバイ)の日本領事館から派遣された原隺麿と、カルカッタ(現コルカタ)日本領事館の稲垣騎兵中佐の出迎えを受けた。ここに日野は主要任務を終えて、帰国の行程を刻むことになる。明治三九年(皇紀二五六六)九月七日に東京を出発してから、翌年一二月二五日に東京へ戻るまで、一年三ヶ月有余にも及ぶ日野強の伊犁紀行は以上の経路を踏破したのであるが、大江山系シャーマニズムと日野との関係は、これからが本番である。
因みに、日野の帰路について略述しておこう。明治四〇年(二五六七)一一月二三日カルカッタを出帆すると、上海に着くのが同年一二月七日、ここでイリからの従僕トクタと別れ、神戸に入港したのは一二月二四日だった。京都に大谷光瑞を訪ねたのち、翌二五日に東京着という調べが岡田の情報である。さらに岡田は、復命した日野が明治天皇に御前講演する栄を賜るとの伝聞について、それは翌年明治四一年(株二五六八)のことではないかと推測している。
日野強の踏査記録が『伊犁紀行』上下二巻として東京博文館から刊行されたのは、明治四二年五月二九日であった。同年六月二六日に日野は中佐に昇進し、続いて七月一日には近衛歩兵第二連帯附となる経歴を添えている。
●呉禄貞と升允について①
岡田英弘は袁世凱の軍事顧問を努めていたオーストラリア人のジョージョ・アーネスト・モリソンの記録も詳しく調べ、呉禄貞と升允の個人情報を書き加えている。呉が日野に同行するまでの経緯は前述の通りだが、問題は呉の同行が上原と異なっている点である。上原は日野の勧めで同行したのだが、呉は蘭州事件に遭遇するまで同じ道筋を歩んで途中から道連れとなったもので、呉が逮捕されるときに日野が居合わせたのが同行のきっかけとなった、と岡田説は言う。その根拠にモリソンの記録を採り上げている。どうあれ、日野の伊犁紀行に影響はないが、呉の個人情報も侮れないためここに書き添えて、歴史認識の一端に加えておく必要がある。
升允が施す配意によって北京に送還された呉は、韓国と間島帰属を巡って争いの渦中にある東三省総督の徐世昌に招聘されて瀋陽へ出向き、大役に就いたとの公式記録がある。すなわち、韓国統監府を設置(二五六五)した日本は大陸と半島の境界を巡る交渉を清国と行っている最中であり、徐は日本を知る呉を招いて間島を支那領域と認めさせる策を講じさせたのである。結果的に呉の献策『延吉辺努報告』(一九〇六)が功を奏して、呉は督弁吉林辺務大臣となり、皇紀二五七〇年(一九一〇)北京に戻ると、紅旗蒙古副都統の資格を得て、独仏両国の軍事訓練視察旅行に出ている。帰国すると革命同志が調達した銀二万両を慶親王に贈り、保定陸軍第六鎮の統制(師団長)に就任した。
明くる二五七一年(一九一一)一〇月一〇日の武昌革命は山西省都の太原でのクーデターに引火した。革命軍を率いて都督となる閻錫山は河北省境の娘子関に向け東進した。清朝は第六鎮の呉に山西へ進攻する命を発したが、石家荘から呉と閻は連絡を取り合って北京進攻を計画しつつ、武昌鎮圧に向かう清軍の補給路を抑え、清軍が漢口占領で行った虐殺を避難したうえ、その責任者である蔭昌(陸軍大臣)の罷免を要求した。万策つきた清朝は呉の部下である馬蕙田を買収し呉を暗殺した。呉禄貞、享年三二歳であった。
●呉禄貞と升允について②
当時、清朝は袁世凱を総理に任命しており、武昌革命の難局打開を袁世凱に託したが、河南省の彰徳(安陽)にいた袁は石塚荘領域を呉に抑えられ、北京に入れなかった。呉の部下である馬は標統(大佐)だったが、石家荘駅の駅長室で呉を暗殺した。
皇紀二五七一年(一九一一)に始まる辛亥革命が南京に中華民国臨時政府を樹立するのは翌年一月一日であり、二月一二日の宣統帝退位により清朝は幕を降ろすことになった。三月一〇日、北京で袁世凱が臨時大総統に就任すると、日野中佐は「貴官ハ陝西省方面ニ到リ諜報活動ニ従事シ、特ニ該方面ニ於ケル共和制反対党ノ動静ヲ偵知スルヲ勉ムベシ」という命令を下される。
この辞令が出たのが同年六月八日、このとき堀川辰吉郎は清朝廟に入城しており、支那側では宣統帝のほか孫文など一部の志士が準備を整えていた。それは後述するとし、ここでは升允の個人情報にも触れておく必要があり、当時の陝西情勢を改めて確認しなければならない。
武昌革命に呼応して西安でも新軍が蜂起し(一〇月ニニ日)、翌日の満城奪取で満洲人の大量虐殺が行われ、張鳳翽(のち都督)として、革命軍政府を樹立する場所が生まれる。
これより先の一九〇九年六月ニ三日、陝西総督だった升允は立憲制に反対の立場から免職され、総督は伊犂将軍の張庚に代わるも、先の読めない情勢が続くなか、升允は徹底して革命反対の立場を貫く。一九一一年一一月一七日、清朝が升允を再び陝西巡撫に起用すると、升は革命軍と戦うために、馬安良(寧夏総兵)のイスラム教徒兵三〇余営(大隊)と戦術を巡らせて、各方面から甘粛を経て陝西を進攻した。同年一ニ月一六日に長武占領を果たして、同年一九日に邠州を取ると、同月ニ九日には乾州攻囲までこぎつけ、翌年(一九一二)は西安すぐ西の威陽に迫り革命軍と昼夜三日の激戦を交えた。だが、宣統帝の退位で停戦が成立して、升は甘粛へ引き揚げざるを得なくなり、同年三月末に帰順した後は、モンゴル人の援助でシベリアに脱走した。翌年(一九一三)六月二〇日、升はウルガ(外モンゴル)から反民国声明を発し、また、日本滞在三年間の記録も刻んでいる。のち青島で恭親王に合流して、青島から青海に赴きラブラン等で滞在して、寧夏を廻り清朝復興運動に励みながら、青島に戻る足跡を刻んでいる。因みに、宣統帝の師傅に王国維を推薦した(一九二二)のは升允であった。一九二五年に宣統帝が北京を離れ日本租界(天津)に移ると、升も行動を共にしたが、一九三〇年一一月、七三歳の生涯を終えた。
●辛亥革命後の支那第二革命
皇紀二五七二年(一九一二)六月八日、四七歳の日野強中佐に再び特務の辞令が下り、陝西省方面での諜報に勤務して共和制反対党の情勢を偵知せよとあるのは、まさに升允の活動を指していた。辛亥革命を第一期革命とすれば、第二革命は一九一三年の江西都督李列鈞らによる反袁世凱運動が端緒となった。そこで、少し李の経歴に触れておこう。李は一八八二年の生まれ、江西省武寧県が出自で、江西武備学堂一期生として、一九〇四年日本に留学している。東京に支那人留学生のための士官予備校(振武学校)あり、ここに入校した李は革命派学生が集う同盟会に入り、一九〇六年に卒業すると、四国の砲兵第一二連隊で実習一年を過ごし、翌年一二月一日、陸軍士官学校第六期砲兵科に入学、同期生に閻錫山、孫伝芳らがいた。一九〇八年一一月二六日附でここを卒業すると江西に帰り雲南を行き交う軍務に服し、第一革命で江西都督の地位を得た。一九一三年二月、袁世凱が国民党幹部の宋教仁を暗殺した主犯に目されると、李は胡漢民(広東都督)、譚延闓(湖南都督)、柏文蔚(安徽都督)とともに袁の非難声明を発した。これに対して袁は李の解任を発表(六月九日)、自身が操る北洋陸軍を南下させた。李列鈞は上海にいた孫文を説得し、同年七月一二日に江西独立を宣言する。
●岡田史観と東亜先覚志士記伝
対袁宣戦で孫文の同意を得た李列鈞が江西の湖口で独立宣言を発すると、安徽、湖南、広東、福建、南京、上海、重慶も李に続いて袁糾弾に起ち上がる。だが、この第二革命は袁の北洋陸軍に打ち克つことができず、七月二五日には湖口を失い、翌八月一八日には南昌をも奪われた。
李列鈞の自伝には南昌を西南に抜けて、樟樹鎮、袁州、萍郷を経て湖南の長沙(省都)に達し日本領事館に身を寄せたとある。ここで譚延闓と相談のうえ、領事館用モーターボートを使い長沙を出ると、湘江を下り、洞庭湖を通過して大冶鉄山(長江南岸)に到着した。大冶鉄山の鉄鉱石は八幡製鉄所(現新日鐵)が買い占めており、日本の重工業を支える役割を有していた。当時ここに農商務省大冶鉄山出張所があり、駐在弁事(所長)は西沢公雄と思われるが、李は懇切なる扱いを受け、翌日の出発は汽船で長江を下りながら、北洋軍の手に落ちた九江や湖口を見て、日本へ向かうと自伝に記されている。
さて、『東亜先覚志士記伝』では、日野と李について、「第二革命の際、(日野は)李一派の革命派に同情して援助・・・、李が事敗れ窮地に陥るや、自己の寓居に隠匿して、・・・中略・・・、奇計を以て無事日本へ亡命せしめた・・・」と書いている。
また「(日野)は帰朝(一九一三)して、偕行社で支那事情の講演を試みた際、はしなくも上官と論争して平素の硬骨ぶりを発揮したのが災いし、間もなく大佐に進んで予備役にも編入され、のち山東に赴き、青島に居を構えて実業に従い、日支合弁の罐詰製造会社、煉瓦製造工場等を経営したが、支那問題に関する志は依然として盛んで、一方には宗社党の士と往来し、一方には革命の士と交わり、東亜大局のために画策し、支那人の間でも非常に信望が厚かった」と続けている。
この『記伝』に触れて、岡田史観は正確さを究めており、日野の個人情報について、齟齬を来さないよう自身の所見を詳らかにしている。
●日野中佐の昇進の予備役編入
岡田説は『記伝』中「・・・中略・・・」の部分すなわち「箪笥の底を打ち抜いて、その中で李を隠匿し」を有り得ないとし、前述の通り、華北の陝西に派遣された日野中佐が、突然江南の地に姿を現すのもおかしいし、日野は一貫して宗社党と関係していて李らの革命派には容れられそうにない。だから、『記伝』の逸話は一種の伝説に過ぎまい。また、職業軍人は佐官止まりで、定年後も勤務するには将官でなければならなず、偕行社事件がなくても、日野は遅かれ早かれ退役したであろう、と見解を明らかにする。
大江山系シャーマニズムを解く筆者にとり、両者の記は相互に立場の相違であり、記伝は含みを潜ませており、岡田説は真面目な学者の性癖をよく顕していて、ともに参考になるが、日野情報の奥行きは更なる深層があり、それを解かずに本稿の目的を達せられない。
次第はさておき、さらに続く岡田説は残り少ないので、最後まで記しておきたい。皇紀二五七四年(一九一四)八月二三日は日本がドイツに宣戦した日で、第一次世界大戦(大西洋戦争)に日本軍が参加して、まず青島を占領するが、この地を軍政下においたのは同年一一月七日である。以後八年間、つまり二五八二年(一九二二)八月に支那へ還付するまで青島は対支那特務工作の中心地となった。在留日本人の数は軍隊を除いても、占領前の数百人から二万人へと増大、新築家屋六〇〇棟、工場は大小六〇社、投資の総額も六〇〇〇万円と膨れ上がる。
前記の如く、多賀中佐が現地入りし、青島守備軍司令部附から青島軍政署附となり、上原多市も多賀に呼ばれた。日野と関係を深めた恭親王(宗社党)や升允らも青島に移住し、清朝の復興を期する運動に励んでいた。日野中佐は前の特務で大佐に昇進して、偕行社事件などあるも、予備役編入のフリーランサーとなり、青島入り後は宗社党や革命派と様々な画策に励んだ。
●日野晩年の大江山帰住
大正七年(二五七八)九月には寺内正毅内閣が崩れて原敬内閣に代わるが、同年一一月には欧州で休戦が決まり、翌年(一九一九)一月からパリ講和会議が開かれた。同会議において日本は山東のドイツ権益を日本へ無償譲渡するよう主張、それに支那は反対したが、結果的に青島を含む膠州湾租借権とその他ドイツが山東に保有した権益は日本に譲渡されることが決定した。これらの決定は同年四月三〇日の首相会議が決め手とされている。
この決定に憤激した北京の大学生は、五月四日に曹汝霖(交通総長)の家を焼き、通称五・四運動が始まる。以後、支那大陸に山東還附や日貨排斥の反日運動が広がって労働者まで巻き込む。さしもの親日派を標榜する段祺瑞政権も翌六月一〇日、パリ講和条約の山東関係条項においては調印を拒む方針を決定することになる。それでも支那全土のストライキは鎮まらず、在留邦人が抱える不安は増すばかりで、翌七月中旬には芳澤謙吉(外務省参事官)が青島に入り、一〇日に及ぶ現地滞在で、専管居留地か共同居留地かの現地調査をした。つまり、日本が青島の施政権を保持し続けるか支那に還附するかの問題について、膠済鉄道沿線の各都市を訪ね、在留する日本人から事情聴取したが、言うまでもなく専管居留地の設定が要望となる。
ところが日本国内の内田康哉外相の声明は現地要望を無視し、共同居留地設定が国益であり、この方針は久しく研究した末の自発的なものだとした。まだ芳澤が済南滞在中八月二日の声明ゆえ在留邦人は慌てふためき、直ちに陳情委員を選出し、同月一四日には第二回青島市民大会を、同月二二日には山東全線大会を開催して、委員二〇名の下で共同居留地反対運動に結集した。その経緯は青島新報に詳しいが、陳情委員の鬼頭玉汝(青島新報社長)は、他の委員とともに東京で田中義一陸相、床次竹二郎内相、内田外相、最後には原首相に面会して現地実情を訴えた。陳情団は京橋区木挽町二丁目の扶桑館に宿泊、同年九月八日付で鬼頭が出稿する『青島問題』なるパンフレットにこの間の事情を詳しく述べてある。
『記伝』もまた、「青島還附問題の際に、日野は在留邦人から推され、当局訪問の陳情委員長として帰朝した」と書いている。さらに「このころから(日野は)大本教の教旨に共鳴し、青島の事業をなげうち丹波綾部(現・京都府綾部市)に帰住、大本教の幹部として、新生涯に入るが綾部にて長逝(一九二〇)した。年五六」と続けている。
以上が『伊犁紀行』(芙蓉書房刊)に付記する岡田英弘の解説であるが、原文を損傷しないよう心掛けながら、筆者の取材も交え些かの私見を加えた。以下では伊犁紀行の原文から、日野と出口清吉の出会いを通じて、大江山系シャーマニズムに浸透していくエネルギーを明らかにしよう。
●日野著『伊犁紀行』の原本
明治四二年(二五六七)五月二九日博文館から発行された『伊犁紀行』は「日誌之部」(上巻)と「地誌之部」(下巻)で構成されている、昭和四八年(二六三八)に芙蓉書房から刊行された復刻版は、前述のように岡田英弘の解説が加えられている。
この著書二巻を編集するには、当然ながら原稿となる日野情報があって、日野本人の手記と意とは「その筋」に伝えられているはずである。
岡田英弘は「その筋」を参謀本部としたが、筆者が前稿『超克の型示し』にて明らかにしたように、光格天皇、仁孝天皇、孝明天皇と続く未来透徹は明治にも生きており、東京遷宮という暴挙を超克する型示しが京都に息づいていることは当然であり、明治天皇の神格が京都に宿るのも必然なのである。また神格の禊祓を通じ、閑院宮親王家が開国コスモポリタン跳梁に備えたことも歴史の真事で、大正天皇と意を同じくして、堀川辰吉郎が出現するのも必然である。
ひるがえって、跳梁する現代テレビ文明のなか、神格を人格に貶めて恥じない社会に天誅が降るのも必然なのである。
●新疆視察の出発準備
明治三九年(皇紀二五六六)の七月下旬,その筋より内命を受けて日野強少佐四二歳が目指した目的地の新疆は、かつて西戎と呼ばれる異民族が住んでいた支那大陸西域の地でゴビ(戈壁)の荒野が拡がっていた。ゴビとは砂漠の意であり、ゴビ砂漠と重合する言葉は現代の愚昧の証であり、似非教育の好例とも言えるが、「戎」と「戈」は外来漢語を霊言「あおうえい」に準え分子結合した文字である。当時の伝聞に従えば、「天に聳ゆる高山、常に雪を頂く峻峰、縦横の起伏、大小河川その間を縫うこと奔放、難路は相次ぎ険路を相望みて、虎や狼などの猛獣は山野に棲息して少なからず、気候は激変して、風土の伝染病は人を脅かし、旅客は常に行路難を嘆く」地とされる。
日野は命を投ずる覚悟なるも、大任遂行を完結せんと気負うほどに危惧も尽きず、事前の備えに万全を期す取材に挑んでいる。その子細は著書に詳しいが、北京では堀賢雄(本願寺僧侶)から、険しい嶺を超え天山南路を行く体験を聴き、天津在留英国駐屯隊長のハミルトンやボヴアからはカラコルム(喀喇崑崙)山の跋渉の聴き取りを重視して、伝授の文化性を必ず認識するよう努めてきたが、それは新しい命が自ら身に帯びる感性の鋭さを蘇らせる意の働きに役立つからだ。携帯薬品や護身用具の物質面も精微の備えを要するが、もっとも重大な素養は宗教に対する用心であり、宗教に比すれば、語学や路銀など大した対策を要せずとも何とかなるものだ。