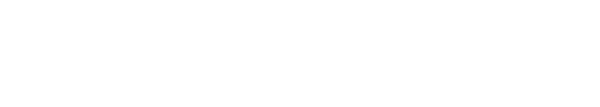GRS80=Geodetic Reference System 1980は、測地学における地球の重力ポテンシャルで地球楕円体のモデルの一つであります。一つの幾何学定数と三つの物理定数を基本に定義されています。現在世界の測地系で最もよく使われ、その長半径は6378137m、扁平率は1/298.257222101とされます。
なお、GPSで使う測地系=WGS84の準拠楕円体はGRS80にほぼ等しいのですが、ここで測地学に触れておく必要があります。
地球に固定した座標系を仮定し、その座標系を使い地球上の任意の点の位置を決定する方法や精度その背景にある地球力学的な諸問題を扱う分野が測地学だとされます。なんとも贅沢な学術だと思いますが、私は空恐ろしい支配力を覚えるとともに、とてつもない反発心に襲われています。
山と海その起伏に富んだ地球が完全な楕円体でない事は前述してきました。而して、平均海水面を等重力ポテンシャルとする仮想的な面が考え出されるのは学術の常套手段これをジオイドと呼ぶ事も前記しました。ジオイドの理想は回転楕円体との一致にありますが、実際の地球上は不均一性を含む物質の凹凸があるため、全体的な凹凸を均(なら)した後のジオイドが求められます。
形状がジオイド面に近い楕円体を求める試みは19世紀前半から行われたとされ、当初は地球規模に及ぶ楕円体の形状を決める方法がなかったので、地球ごとの子午線弧長の測量によって、楕円体が決せられ1841年の東アジア産ベッセル楕円体や1864年の北米産クラーク楕円体などの創出に活路を求めたようです。
以後これらの楕円体は、長半径や扁平率が微妙に異なるため1967年の国際測地学・地球物理学連合=IUGG総会で「IUGG1967」の決定をみますが、全地球で統一的な経緯度を獲得する結果には至りませんでした。IUGGが全世界統一の成果を定めた1980年は、人工衛星の周期を解析した結果から得た知見が主な事由とされています。(=GRS80)
1984年になると、アメリカ国防総省がWGS84と呼ぶ楕円体の決定を公表いたします。この楕円体はGRSに依拠するモノであり、扁平率の決定に当たっては、正規化された2次の帯調和重力係数から算出されるも、この重力係数計算の際に基となるGRS80の力学的形状係数J2の有効数字が8ケタで打ち切られているため、扁平率の値に差異が生じ、短半径がGRS80に比べ約0.104㎜長くなるが、実用上はGRS80との差はないと強弁されます。
地表上のある地点の緯度と経度を表現するためには、楕円体パラメータのほかに緯度と経度の絶対的な基準が必要になり、これを測地座標系と呼び日本では東京都港区麻布台に在る日本経緯度原点を基準に用いる事が普通とされています。
日本は過去のしがらみからベッセル楕円体を用いてきましたが、平成13年(2001)法律第53号「測量法および水路業務法の一部を改正する法律」の施行で2002年4月からGRS80楕円体とITRF座標系に基づく世界測地系での経緯度の表示を法制化する事が決められました。
現況の地球楕円体は準拠楕円体と呼ばれ、ジオイド面に最も近似された楕円体とされ、そのズレは水準測量や三角測量で求められ、近年は衛星測量によって制度が高められたと思われています。
ジオイド面は等ポテンシャル面である事から、精密な重力測定によっても求められます。地域的な重力の異常については、人工衛星の軌道解析から求める事も可とされています。
測地学の起源については、紀元前3世紀説が広まっており、古代エジプトのエラトステネスが地球の大きさを求めた事に始まると言われます。往時、夏至の日の正午にシエネ(現アスワン)の深井戸の底を太陽の光が照らすとされ、同日同時間エラトステネスは、アレキサンドリアにあった日時計の中央に垂直に立てられた棒の長さと、その陰の長さとの比をとることで、太陽は天頂から南に7.2度の所へ来る事が分かります。シエネとアレキサンドリアの間は5000スタディア(約920㎞)と知られており、地球の大きさに比較して太陽までの距離は非常に遠いことから、地球に降り注ぐ太陽光線は平行な光線と考えられるため、その関係式から計算したエラトステネスが決したのは地球の大きさだったとされます。その大きさから求めた地球の円周長は現況もっとも精緻とされる値に比べ違いが15%ほどだった事から、エラトステネスは『測地学の父』と呼ばれています。
測地学では地球楕円体とジオイドの違いをジオイドの高さと表現しています。要注意は地球表面が天体間の引力、特に月の潮汐力による弾性変形によって、常に数㎝から数十㎝の伸縮がある事を念に刻んでおくことです。
太陽系で最も密度の高い地球の質量は、万有引力定数と地心重力定数から計算し、体積と質量から平均密度を求めますが、それは水の5.5倍、花崗岩の2倍、鉄の0.7倍ほどに相当します。この密度に近い惑星は水星と金星ですが、逆に最も密度が低い惑星は土星とされています。
地球の構成物質の種類と分布を知るには、内部での圧力上昇によって圧縮される程度を考慮のうえ1気圧下の密度へ直す必要があります。これらの補正を加えた平均密度は約4100㎏/㎥とされ、地球以外では観測データがないのでモデルによる補正平均密度に依存しますが、その違いはそれほど大きくないとされており、水星が約5400㎏/㎥、金星が約4000㎏/㎥、火星は約3800㎏/㎥とされ、その違いは金属の含有量に反映されると仮想されています。
地球楕円体の近代的計算は1738年にピエール・ルイ・モーベルテュイの公表が初で、北極圏内トルネ谷における子午線弧長の測量結果によるとされ、この結果と突き合せた測量結果はフランスの扁球説ですが、測量誤差の影響から、現況値より扁平率の見積りが大きいとされます。
現代値に相当程度近い初期の測量は、インド地方の子午線弧長によるジョージ・エベレストの測量結果とされ1830年に公表されています。この楕円体構造により、地球の中心点からの距離が最も大きいのは、北緯28度・標高8848mのエベレスト山頂ではなく南緯01度・標高6267mの南米チンポラソ山頂と決せられました。因みに、アフリカ大陸の赤道直下に聳えるキリマンジャロは南緯03度・標高5895mで周知の事だと思います。
地球の構造は中心から①内核、②外核、③下部マントル、④上部マントル、⑤地殻、⑥地表という層に分けられますが、これらは断面構造として、組成、鉱物相、力学性質からの分類で成る一般論であります。また、地表からの距離に応じた境界領域の深度(高度)にある幅は、位置と時間から境界領域に変化が生じるからだとされています。ただし、地球内部の構造が地表面での観測で仮定し得る範囲であり、その最も優れた方法が地震波の分析とは誰もが認識するところでしょう。
地震波の解析によると、外側から、岩石質の地殻、岩石質の粘弾性体であるマントル、金属質の流体の外核、金属質固体の内核、と大まかな分け方が広く認識されています。ただし、岩石質も地殻とマントルでは化学組成に違いがあり、金属質も同様いずれにしても推定レベルにすぎません。
上部マントルには地表面からの深さ100㎞付近に、地震波が低速になる層(アセノスフェア)があり、この層は部分的に溶融していると考えられ、上部の相対的に冷たく硬い層とは物理的に区別の対象にされています。この層はアセノスフェアの上にあり、上部マントルの一部と地殻から成る岩石圏(リソスフェア)と言われ、プレートと呼ばれる10数枚の板に分かれています。
プレートは2種類あり、一つは大陸を含む大陸プレート、もう一つは海洋地域のみを含む海洋プレートを指します。海洋プレートは中央海嶺で生産され、マントル対流に運ばれて中央海嶺から離れますが、その間にも中央海嶺ではプレートの生産やむことがありません。
相対的な重さは大陸プレートが海洋プレートより軽いため、境界でぶつかるときは海洋プレートがマントル中に沈み込み日本海溝の如き帯を造りますが、海溝を伴う場合と伴わない場合があり、その違いは海洋底拡大期間の差異にあるという考えが有力であります。
海溝が在る場合は海洋底拡大が始まってからの年月が長いとみられています。海溝を伴うプレートは伴わないプレートより拡大速度が速いとされ、それはマントル対流のほかに沈み込んだプレートに引っ張られる効果が加わるからだそうです。
海洋底の年代は放射線元素による年代測定のもと2億年以内とみられます。即ち、同程度の期間を過ごした海洋プレートが地球内部へ潜り込むためで、対する大陸プレートは大部分が30億年前から形成されており、その歴史を通じた形成と成長の結果と考えられています。そして、特に古いモノは安定陸塊と呼ばれ、最も古い部分は約44億年前に形成されたと見積もられています。
中心核はコアとも言われ、外核と内核に分かれ、液相の外核半径は3480㎞、固相の内核半径は1220㎞と試算されております。外核主成分は推定で鉄とニッケルですが、軽元素とされる水素や炭素など10%以上の含有がなければ地震波速度と密度は説明が出来ない事になります。
一般的に知られる内核形成のプロセスは、地球内部の冷却に伴い、外核の鉄とニッケルが析出これ沈降して内核となりますが、中心部の気圧は推定400万、内核の気圧は推定320万、この環境は金属鉄の性質上固相になるのが通常であります。温度は物質組成とエネルギーの輸送過程に依存するため分かりませんが、推定5000Kから8000Kと公表されています。
なお、対流や自転などに起因する外核の金属流体運動から生じるのは電流であります。この電流が磁場を生じると考えられており、これら力学的な運動に結びつく磁場発生と維持機構の仕組みをダイナモ機構と呼んでいます。
次のマントルは地球体積の83%を占めており、珪酸塩鉱物を主成分に層は約2900㎞の深さを占めるとされます。とはいえ、全体の化学組成については多くが不明のままです。上部マントル層は橄欖(かんらん)岩または仮想岩パイロライトが占めるとの考え方を主流にしており、下部は輝石に近い組成とする説あるものの定着し得るまでには至っていません。
核に暖められるマントルですが、固相のマントルはゆっくり対流=プルームテクトニクスしながら地殻に熱を運ぶとし、それは自らの内部に熱源を持つからとの説もあります。ただし、地殻近辺にはマントル対流の相が見当たらず、地殻と一体化し得るごとき振る舞いはプレートテクトニクスの水平運動と読む見方もあり、未だマントルの動きは解明しきれずの観を実相としています。
一方、深度700㎞を超える内部では深発地震がほぼ生じない事から、対流運動は2層で独立する性質を有していると唱える説も出ましたが、観測技術の多様化によって深度900㎞付近に地震跡が判明したほか、岩石圏の沈み込みが核付近まで起こったとの報告もあり、地震学的トモグラフィー法等の盛んなる構造推定には多くの新説が浮き沈みしております。
モホロビチッチ不連続面(モホ面)すなわち地殻との境には地震波速度が不連続に変化する層ある説の事ですが、言い古されてきた事案なので省かせていただきます。
地表の固体相を地殻と言うことは今更ながらですが、主成分は珪酸塩とされ、地球内部の熱を運ぶシステムは熱伝導のみゆえに、マントルの対流に比べると低効率で、結果的に核やマントルの冷却を遅延させるとの考え方が一般化されています。
大陸と海洋の地殻分類は組成の差や構造によって仕分けされ、表面の55%を占める海洋の地殻は玄武岩質・厚さは平均6㎞・平均密度は3.0g/㎤で固化形成は2億年以内と言われます。対して大陸の地殻は花崗岩質・厚さは平均35㎞(20~70㎞)・平均密度は2.8g/㎤以下と厚いが軽いと言われます。表面の構造はプレート運動による造山運動や火山活動、大気と水による風化ほか浸食・堆積などによって決まります。
水圏に関しては、水そのものに関して私の自負する検証があること、矛盾だらけの通説では具体的論証が成り立たないため、別記のスペースを設けてから持論を展開いたします。
大気圏も右と同様の自負を有し、いわゆるハープに関連する情報は、いわゆる風評の如き無責任も極まる情報とは異なるため、同じく別記のスペースを設けるべく念じております。
磁気圏もまた同じ事案を抱えますので同様の措置といたします。
さて、これまでは太陽系における地球の動きと位置づけ、地球の物理的性質、地球の構造などから地球人が生かされている場の概要とともに、地球人が生きるために要する必須の時間について推定を含め大凡の環境に触れてまいりました。地球人が場所と時間を共有し得るために与えられるヒントは周期性であり、その周期性を絶対的に共有し得るのが場所と時間であります。
地球人の活動に必須の空間的構造や地域的特徴の解明を目標としている学術に地理学の一つとして人文地理学があり、出来事や変化を認識するために地球人の要する基礎的な概念が時間であることは言うまでもないところです。そして、これらの学術に伴う定義の実態は前述した通りですが、何度も見直されることや改められることは必然でして未だ学術は道半ばなのであります。
今や世界的かつ日常的に煽り立てられるデジタル化インターネットの炎上マツリは、テレビによるゾンビの養成に起因する狂気の沙汰にすぎませんが、この飽和状態を口火として必ずやビッグバンの展開ある事も歴史の訓えるところです。
場の概要と必須の時間に関する情報が不十分な事は承知していますが、これ以上に難解な諸議案を剖判して表現する能力を私は持ち合わせておりません。それゆえ、ウィキペディアの記事を私なりにアレンジのうえ先を急ぐとします。ただし、既に味わったと思いますが、眠気にさそわれ読み飛ばす横着をすると、これまで忍耐した事が元の木阿弥となります。
(つづく)