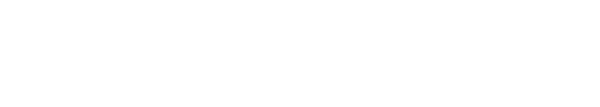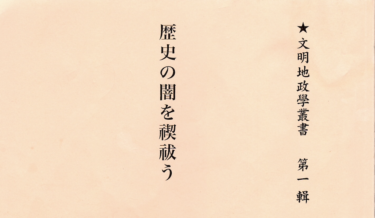さて、愛国婦人会の活動内容に触れておきたい。
当初は戦没将兵の遺族と退役兵士の生活救護に尽くしたが、大正六年(一九一七)に欽定改変して他の救護事業にも当たれるようにした。
関東大震災後の救済その他の救護施設を建設すること、婦人の職業あっせん所、結婚相談所などの広範囲に及ぶ活動を展開していった。また機関紙『愛国婦人』を発刊して識字率の向上をはかりつつ講演活動も盛んに行っている。
初期の会員は皇族はじめハイクラスの婦人が大半を占めたが、日露戦争(一九〇五―六)時を機に大衆化が促進され、その数四十六万人に達する日本最大規模の婦人団体に変貌していった。各府県の支部長には知事夫人が就任するなど、今なら人寄せパンダとも呼ばれるセレブもおり、その会員数は更なる増加を予測させたが、会員間の格差が問題化しないかの懸念も生じてくる。
それは第一次世界大戦末期のデモクラシーで表面化するが、愛国婦人会は新たに農村託児所などの社会事業を取り入れる事で対策を怠らなかった。
現代テレビ文明のごとき暇暮らしの世相になると、愚にもつかない格差論議で税金を無駄遣いする国会と同じように、人が頽落していく兆しはスキャンダルを弄ぶ事に始まるともいえよう。
昭和期の愛国婦人会は支部活動も盛んになり、女子教育のため各種学校(法律に基づき公立は都道府県の教育委員会が、私立は知事が認可している)と同じ扱いの講習科を設置する支部もあり、秋田令和高等学校のように学校として存続する実例もみられる。しかし、満州事変(一九三一)以降にはファッショ体制推進や婦人報国運動そして愛国子女団の結成など政治利用が強まってくる。
昭和七年(一九三二)大阪で大日本国防婦人会が結成され、会員数では愛国婦人会を上回る政府の御用団体が旋風を巻き起こしていく。高額会費で慈善活動に傾注する愛国婦人会に対して、見せかけ低額の会費で兵士に手厚い世話をする大日本国防婦人会の登場により、以降は「お定まり」の戦争へ突入していく路線のもと、すべての善意は雲散霧消へのコースを余儀なくされていく。
それはさて、賀屋興宣と澁澤敬三から私一八歳が学んだ政界の深層構造に触れるとする。賀屋から発せられた最初の言は「君と面談するにあたり、何ゆえ澁澤さんに同席を請うたかの答は真っすぐな性格と聞く君に対する礼であるが、実は澁澤さん自身が同席を望んだのだよ」であった。
私は高松宮様から「自ら会っておきたいと思う人の初対面には場の比重が大きい」との訓戒を賜り現在に至るも私の心に深く刻まれている。初の「お目通り」で賜ったお言葉であったが、当時は意味不明で自宅に持ち帰りつつ、一週間かけて導き出した私の認識では「統一場の理論」に基づく剖判のメカニズムを指すものと自負している。
それは真の触媒作用とは何かを意味するが、平たく言えば「ナミが止まればツブとなり、粒が動けば波となる」天理の法則を指しており、見えない世界を透かせる奥義に通じている。
宮様の言う「場」とは単純に場所を指すのではなく「空気」を指しており、澱みのない空気に人が交わる事で生じる変化とは何かを覚ること、つまり、初対面の人と人が出会った時に見えない空気の場に生じた変化を感じる心、その心は出会う前の心に戻す事が出来るか否かであり、出会う前の心に戻せなければ、その出会いに働く触媒作用にバイアスが掛っているのは必然というわけである。
正体は同じなのに、波の時は見えないけれど粒の時は見える、情報の時は味わえないけれど現物の時は味わえる、情報を媒介するメディアは触媒作用に加担しているため、次の事に心しなければ必ず世に不幸をもたらすことになる。現代テレビ文明の落とし穴であるが媒体は恥じるを知らない。
BではないAと、AではないBが接合するとき、AでもBでもないCが媒介したとしよう。接合を終えたAとBが剖れたとき、AとBは元のAと元のBに戻る事が出来たであろうか、接合した部分に媒介したCがAやBに付着していたり、傷痕を残していたり、すればAとBは元のAと元のBに戻り得た事にはならない。この事はAとBとCすべてが自覚を必要とする事項なのである。
すなわち、触媒とは接合に必須の存在でありながら、自ら完全に消滅し得る実在でもあるのだ。
そうでないと、澱みのない空気に人が交わる事で生じる変化を覚る訓練にはならないのである。
宮様に「お目通り」したとき、賀屋そして澁澤の御両人と初対面したとき、その場所も空気も同じ条件だった事が私にリラックスを与えてくださった。
澁澤家は栄一翁の代すでに陛下の御下問を賜る存在であって、その家督を継いだ孫の敬三にしても天皇家との関係は何ら変わってはいない。昭和十七年(一九四二)戦時中の課題として軍費の調達は火中の栗を拾うよりも厄介であり、誰もが責務を果たす事できない難問であった。そんな折り敬三に持ち込まれた依頼が日銀副総裁就任の要請であり、敬三ならば政府の要請を回避する方策は幾らでも持ち合わせたが、その依頼人が賀屋で三拝九拝となれば非情になりきれない。時に賀屋もまた敬三の立場は充分に心得ており、本来なら敬三に持ち込むべき筋でない事は承知のうえであった。
このとき賀屋の職責は東条内閣における大蔵大臣で再入閣しており、これもまた本人が回避したい役職であったが、戦場に散る英霊の命に鑑みると私情を持ち込むなど自ら許さない人でもある。
戦争回避が不能の局面に陥ると、政府も軍も否すべての分野に内紛が生じるのは、世界共通の行動原理だから仕方ないが、そうした場合の資金調達に伴うリスクは命の保障がないことである。一方がプラスになれば、もう一方に同じ分量のマイナスが生じる、それは生きるか死ぬかの分岐点ともなる重大事だから財政担当には死ぬ覚悟が求められる。
賀屋の遠祖は赤松則村である。則村の法名は法雲寺月漳円心。護良親王の令旨で反幕府勢力として挙兵している。円心の弟円光の妻は楠木正成の姉だから、円心は正成の従兄にあたる。
賀屋興宣の要請で日銀副総裁に就任した澁澤敬三は同十九年(一九四四)総裁になり、戦争末期の殺伐たる通貨管理の最高責任者として奮迅の働きに追われる。翌年の空襲で自邸一部を焼失したのち十月九日に組閣された幣原喜重郎政権の大蔵大臣を引き受けて日銀総裁を辞任している。
澁澤の蔵相就任一か月前に、賀屋は理不尽で不当なA級戦犯に指定され身柄を拘束される。
賀屋が初体験の選挙を経て国会議員として初登庁するのは同三十三年(一九五八)のこと、澁澤が外務省移動大使として中南米各国を歴訪したのが前年(一九五七)そして旅先の熊本で病魔に襲われ東大付属病院へ入院するのが同三十五年(一九六〇)である。
私との面談は同三十四年(一九五九)賀屋の代議士二年目にあたり、澁澤が外務省の仕事を終えて骨休めに一息ついている頃にあたる。
御両人の話は私が自身のタブーと決めて、長期間封印してきたコトガラであるが、既に落合先生が自身の造語で明かして下さった「國體と政体の二元性」こそが御両人の話の核心になっていた。
澁澤の開口一番は「わが家系の血洗島(現埼玉県深谷市)と島村(現群馬県佐波郡)の栗原家とは姻戚関係にあるが、君は存知しているかな」との発言であった。
私は「我が家との関係は遠くなりますが、甲斐武田一一代信成四男が早世した兄の名乗る栗原姓を継ぎ山梨郡と信濃に領地を得たあと、伊予道後の栗原姓や上野(コウズケ)島村の栗原姓などに分布入植したと聞いております」と、澁澤の問いに答えた記憶がよみがえる。
澁澤と賀屋は顔を見合わせ親しげな笑みを浮かべた。
笑顔の澁澤から「喜作ジイさまの名は知っていますか」との問いが続けられた。
私は「栄一翁の従兄(二歳上)で成一朗様のこと、成一朗様の系譜が島村の栗原家と婚姻の関係を結んだと聞いております」と、定かではないが同じ趣の返事をしたはず…。
澁澤からバトンタッチされた賀屋の問いは天皇制に関する事が二つ三つ続けられた。
あとは私が知りたいコトガラを御両人が解りやすい説明で教えてくださった。
その解説と薫陶は私が知らなかったコトガラばかりで、特に強く印象づけられたのは世界中に分布散在する修験の実在であり、ワンワールドの深層構造に対するヒントの連打であった。
ここに御両人の薫陶の中から抜粋して、私の主観に変え伝えておきたいことがある。
それは御両人が透かした戦後社会の推移が、見事に的中していたコトガラへの訓示にもなりえる。
大東亜の事変は植民地化されたアジア全域の解放を目標としていた。当時、植民地化を免れたのは日本だけ、日本が世界戦へ打って出た犠牲によって、その目標は一応の成果を得たが、戦後は成果を得た植民地解放の分量すべてが日本社会へ異動したにすぎない皮相が生じている。
たとえば、在日外国人のほとんどを植民と認識しなければ植民地化は解放された事にならない。
その現実と真正面から向き合う責めを負うのが戦後日本の政治であるが、その責任は政官業言らの工作によって掩蔽=矮小化されており、日本社会の現状は植民地化が更に浸透したと考えるべきだ。
特にメディアの媒介が著しいのは、戦後テレビ文明の下で魑魅魍魎が跳梁跋扈することである。
魑魅魍魎の特色は何でも千切り取ること、早口でまくし立てること、大声で吠えること、それしか知力を持ち合わせないからである。制作陣は視聴率の呪縛に身も心も奪われている。
跳梁跋扈の特色は何でも出しゃばること、恥じらいを知らないこと、他を威圧すること、それしか体力を持ち合わせないからである。営業陣は広告料の増減に身も心も奪われている。
魑魅魍魎の跳梁跋扈を操るのが経営陣なら、経営陣を操るのは国際政治、その国際政治を操るのが電波法なら、電波法を操るのはワンワールド・ミリタリーすなわち世界統一連合軍となる。
新時代の電子を使う端末機器を操るのも世界統一連合軍に集束されている。
テレビはストレス・ウイルスの放出とともに、そのワクチンの接種もリピートするため、視聴者はテレビの中毒症状から逃れられなくなり、モニターを見る見ないに拘わらず、スイッチ・オンのまま放置が続くことで、しだいに自覚機能が欠如していき、認知症の改良に免疫力は見当たらない。
戦後テレビ文明の体制づくりは、古来日本の文化に根差す「テキヤ」がモデルになっている。
たとえば、映画『男はつらいよ「寅さん」シリーズ』のように、テキヤに扮したフーテンの演劇が安定した興行成績すなわち視聴率を記録している。むろん、ヒットの要素は多岐に及ぼうが、全体を通して貫かれるのはテキヤの持ち味であり、テキヤを真似ることが高視聴率の要因になっている。
テレビ・メディアは基準以上の視聴率を保持する事によって成り立つビジネスである。
テレビ界の成り立ちは経営体制を企画する初期の段階からテキヤをモデルに起ち上げた。
而して、少しテキヤの歴史に触れておきたい。
テキヤの発祥は神事の「まつりごと」へ奉仕するボランティアに始まっている。当然、奈良時代の前から自然発生した群れ社会の非日常性が起源であり、それが「姓(カバネ)の世」に一種の業態へ進展すると、社寺祭礼に音が奏でられたり、謡が伴うようになるなど、しだいに雅楽の古典ともなる原型が形成されていった。その雅楽に伴う芸能として猿楽が市民権を得るようになる。
猿楽は神事の形態模写や舞踊で人をなごませ、非日常的な慶弔の定番に組み入れられていった。
その猿楽から派生した芸能が能や狂言であり、それらの発展には二つの分流があり、一つは社寺に所属した芸能として、もう一つは公家の庇護下に置かれた芸能として、姓の世から「司(ツカサ)の世」へ移る絆の役を果たしている。つまり、猿楽は絶え間ない継続の力を示す芸能なのである。
社寺祭礼は喜怒哀楽の本義を示すもの、猿楽は涙を誘うペーソスとともに、笑いを誘うコミックを演じるもの、この社寺祭礼の下働きが奉公すなわちボランティアの発祥であるが、その際に生まれた猿楽を全国へ広めるために、テキヤの生き方にも大きな転機が生じていた。
社寺の祭祀は宮司や僧侶が執り行うが、その例祭に集う人たちにとっては、非日常的な中で神仏と触れ合う安らぎの場にもなりえる。そこに自然発生したのが猿楽であり、その例祭縁日の下働きから生じたボランティアのネットワークがテキヤである。
社寺に仕える氏子や檀家と異なり、テキヤは例祭縁日を仕切るプロフェッショナルであり、社寺の宮司や僧侶そして氏子や檀家では賄えない仕事一切を仕上げる職人である。社領地や寺領地の清掃や整備を行うことから、その地の環境に見合う露店の配置を定めたり、例祭縁日に集う人々を日常から解放しつつストレスをとりのぞき、経験則を活かした社寺への奉仕は猿楽に勝るとも劣らない。
旧暦七月十五日の盂蘭盆会(ウラボンエ)では、ハスの葉の上に旬の食物を供えて、迎え火と送り火で祖先のミタマに接しては冥福を祈り、供物は餓鬼へ施すという慣わしが今に伝わっている。
テキヤは社寺から託宣あるとき、縁起物を振る舞う慣習があり、時には社寺からの祝儀を拝受する事もあるが、そうした際にはハスの葉がボン替りに使われたこともある。なお供え物には旬の野菜や海産の魚貝あるいは昆布などあり、ヤマゴなどの特区では獣肉が供え物の定番とされている。
テキヤの奉仕に営利が伴うようになるのは、時流に連動した時代の産物にすぎないのだ。
今やハスの葉を見ること少なくなったが、テレビの通販ビジネスに使われているとのこと…。
いかさま(カラクリ)師とコンビのサクラ(販促ヘルパー)もテレビに流用されている…。
例祭縁日に集う人たちを楽しませるため、テキヤは啖呵売(タンカバイ)という口上販売の芸能を広めている。まず「さぁ!お立合い」にはじまり、勘どころで「買ったぁ!」の芝居がかった販売もテキヤの一芸であり、今やテレビ通販のタレントは自らの下手な物まねに酔っている…。
テキヤの口上は大道芸も含め多くの形態を有するが、(啖呵を含む)博徒の口上も多岐にわたって訛り言葉もにぎやかであった。現行テレビ番組のアナウンスやコメントにしても、テキヤ・バクトの口上に肖るものの、トークそのものに余裕がないため面白くないとのこと…。
テキヤの「やらせ」は必ずカラクリを明らかにするが、テレビの「やらせ」はひた隠しにするため陰湿きわまりなく被害は大きくなるばかり、どちらが反社会勢力か治安当局はだんまりのみ…。
テキヤは香具師(ヤシ)とも言われ、野師・野士・弥四などの文字で表現された。
神名(カナ)を主語とせず、ルビ(フリガナ)に扱う時代となっては、香具師を的屋の源流と言い的屋を神農と言うが、香具師とはケシが発する香の効果に関連して、香具を扱う薬師が薬や毒の功と罪を追及して、経験則から調合した秘薬の運び役をテキヤに託す事由から生じている。
とび職も植木屋も発祥はテキヤである。
鳶は植林にはじまり、高木から高木へ飛び移る軽業のほか、樹木の病を診断診療するなどの特殊な能力を培っている。それらは時代の推移で建築分野の骨組みはじめ、火災の延焼や家屋の倒壊に備え解体のイロハを身に帯びた技量にも活かされている。
縁起物としては、防火や消防への祈りを込める酉の市の守り熊手とか、新年に備える注連縄(シメナワ)や門松あるいは松飾りの普及に寄与貢献している。
つまり、季節の風物詩は社寺の託宣に仕えたテキヤによって日本全土に広まったのである。猿楽と同様に社寺の「まつりごと」には舞台装置が必要であり、その骨組みから解体を行うまでの大道具や小道具はテキヤをモデルとして、現行テレビがそっくり真似している事にすぎないのだ。
平安期の楊弓(座したまま放つ矢を的に当て得点を競う遊び)は公家の戯れとされるが、テキヤは祭り弓と矢を楊弓に模して、景品付きの射的遊戯に替え庶民の間に広めた。この射的遊戯場のことをマトヤ(的屋)あるいはヤシ(矢師)とも言うが、その遊具は吹矢・弓矢そしてハジキ(玩具銃)に変じるなど時代の流れを反映している。
銃をハジキと呼んだり、商品名を記した回転盤をブンマワシと言ったり、日本版ルーレットの事をトッコイトッコイやドッコイドッコイと名付けたのもテキヤであり、マトヤをヤバ(矢場)と名付け矢玉が飛び交う危ない場からヤバイの語源が生じている。このヤバイ現場を舞うように駆け回る芸を演じるヤトリメ(矢取り女)などは、現行テレビに映るレポーターの先駆けでもある。
神事の一つにミソギやハラエがあり、その場に仕えるワタリミコ(渡り巫女)がおり、俗世一般の法律とは別の戒律(治外法権)に服していた。社寺や縁起に係る場をニワバ(庭場)と言い、遊女を囲うニワバはユウカク(遊郭)と呼ばれ、結界の一つと考えられ、テキヤに近接した場であった。
遊郭を単なる売春窟と蔑むのは大きな誤りであり、伊勢詣でや富士詣での要所には宿場町があって飯盛り女が遊女になったりする。それらの女性をミソギやハラエと考えた時代もあった。それは旅の途中であっても「お参り」と考える思想であって、温泉街にヤバが設けられヤバのメ(女)と呼んだ遊女も出現している。
猿楽の流れを踏むクグツ(傀儡=カイライ)師は定住を嫌って、流浪の旅先で見世物芸を演じては祝儀などの施しを得たが、その中には社寺お抱えとなり、間諜と呼ばれたスパイとして、全国に根を張ったグループも多く輩出されていった。男性は主に剣舞を舞うなどして、女性はクグツ回しという唄に合わせて操り人形を動かしたのでクグツメとも呼ばれた。
井原西鶴が著した遊女はハスのハメと言い、上層階級を常連客に遊ぶ芸達者でスパイもおり、その呼び名の由来はテキヤが使ったハスの葉に通じている。路傍の遊女と言われるコロビも諜報員でゴザ(茣蓙)を抱え遊び人を誘ったとされるが、テキヤが露店で商う際にゴザの上に売り物を並べる事に通じており、コロビとの情報交換を装うなど多くは優れたレポーターともいえる。
サンズン(三寸)は渡世人の「軒先サンズン借り受けまして」など、仁義を切る口上に使われたがテキヤは舌先サンズンで商う際に使用しており、胸先サンズンも値切りの際に使う言葉である。
テキヤが商う場はタカイチ(高市)あるいはタカマチ(高街)と呼ばれるが、多数の人を動員する仮設の構築物をタカモノ(高物)と呼んで、総合プロデュースのサーカスから芝居小屋まで小規模な商いとは異なる興行もテキヤが手掛ける範疇に含まれる。たとえば、お化け屋敷ほか、軽業や手品の類が使用するテントなど、これら施設構築の設計施工は土木建設の業界にも深く浸透している。
コミセ(小店)で使う売物台の高さは一尺三寸(約四十センチメートル)とされて、テキヤの規格基準には様々な「モノサシ」が利用されている。たとえば、ゴザは売場の標準面積とされたり、縄をモノサシに使うなどあり、移動式の組立型店舗はトコミセと呼ばれている。
近代の興行を代表するものは、オリンピック&パラリンピックであろうが、その先駆を為したのはテキヤであり、海外のタレントを呼ぶ際にはヒッパリ(引張り)の隠語が今も使われている。
口上売りの一つにオオジメ(大占め)があり、ネタ(手品)やゴト(曲芸)、サクラ(仕掛け)を仕込むなど大掛かりな商いのこと、またガマの油売りやバナナの叩き売り、南京玉すだれなど、人の耳目を集めるガイダンスは商いと言うより、奉仕のオピニオンリーダーをも思わせる。
ハジキ(弾き)は射的のほか、パチンコ、スマートボール、コリントゲーなどあり、ボク(木)はハボク(葉木)とも言って、植木専門の商いを指すが、朝顔市や七夕の竹笹、酉の市から新年お飾り羽子板市など、風土風習に見合った四季折々の生活に密着している。
いずれも互助活動のひな型であり、テキヤが形成してきたネットワークは、各分野のモデルとされ土木建設から港湾荷役さらに海運陸送などの団体の構成に役立っている。
キリがないため、きりあげるが、テレビ・メディアのやっていることは、どれもこれもテキヤから学んだモノゴトばかりで、どれだけ多くのテキヤを失業者へ陥れたかテレビは省みるべきである。
私は賀屋そして澁澤の御両人から学んだ日本の深層構造を洞察するとき、落合先生ならではの洞察史観が御両人を一層きわだてた事に敬服の念を深めるばかりである。
後学の立場にある私は、先哲の恩人たちから学んだ事を明日の自分に活かさなければ、恩人に礼を返す事にはならないと自負している。
私のごときを導いてくれた先哲の恩人たちが遺したタマコト(霊言)は、とても私ごときの浅学に起草し得るコトガラではないが、心しているコトガラは「自分の主観にすぎないのに」たとえば出版業界が『昭和天皇の独白録』のごとき売文を行う卑劣に断じて与しないという信条である。
筆舌の常とう句に「誰が何して何とやら」があって、誰それからの伝聞として自らの発言に変える事例は尽きないが、その伝聞はその時点で伝者の主観になっている。つまり、「誰がこう言った」は自分の主観は「こう受け入れた」というわけで、それを第三者へ告げた場合は「誰それの言葉を自分はこのように受け入れた」のであって、第三者も「伝聞は発言者の主観であって、誰それの主観とは言えない」と捉えるべきである。
私が自分自身の経験則で認識するのは、メディア全体へ共通して言えるのが「これら主観を客観とフェイクして恥じない無責任な習慣」これこそが煽り暴発の温床になっているのだ。
(続く)