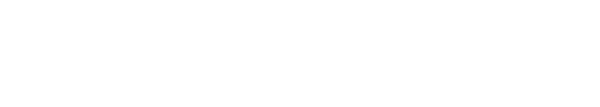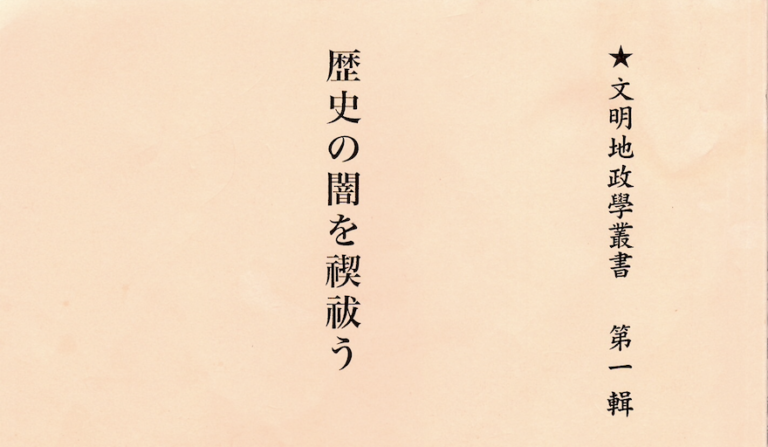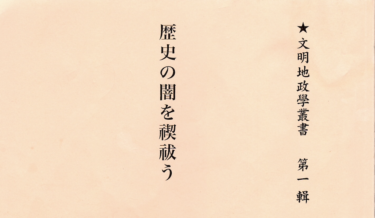●「東方礼儀之国」の内実
さて、本題に関わる朝鮮の歴史について概略を確認しておきたい。
高麗王三四代目として恭譲王(一三四五〜九四)を擁立即位(一三八九)させた李成桂は一三九二年に譲位を迫り自ら王位を簒奪する。李は翌年すぐ支那の明王朝に届け出て権知朝鮮国事つまり実質的な朝鮮王(代理)の称号を許されると、新生国号を朝鮮と定め先王一家を皆殺しにする。明の冊封(支那皇帝との君臣関係証明文書)の下で正式な朝鮮国王の名乗りが成立する時代は、李朝三代目に当たる五男(芳遠)の太宗一四〇一年から始まる。この間に起こる内訌を王子の乱といい、第一次と第二次とがある。明の皇帝を唯一の天子と敬う李氏朝鮮の思想は、自国を「東方礼儀之国」と呼ぶものの朝貢を常とし皇帝の使節を迎えるため迎思門を築き歓待することを余儀なくされていた。当初の首都は現在の非武装地帯にある板門店に近い京畿道の開城を使用、何度か漢城(現在ソウル特別市)との間を往来しながら、太宗による漢陽(漢城)遷都で落ち着いた。自らを中華思想の皇帝に次ぐ最高位の王侯と位置づけ他の国や民族に対しては服従と朝貢を求め、日本に対しても倭館と称する居留地を設けて倭館内の居住を義務づけ、厳しい取り締まりで備えた。
すなわち、倭館は富山浦(釜山)と乃而浦(鎮海)、塩浦(蔚山)の三浦をして三浦倭館と称したが、後に乱を呼び起こすなどあったため釜山一港に限定される。半島北部に住んだ女真という族を「胡」あるいは「オランケ」と呼んで蔑視の対象とし、交易は朝貢に等しい儀礼関係を強要したため明にも服属した女真の嘆願により朝鮮が明から咎められる時期もある。因みに、刀伊の入寇(一〇一九)と呼ばれる九州侵攻を行い、太宰府官軍に逆襲された侵入者の主体は女真だとされている。
明の滅亡は女真系を主力とする後金つまり後の清の台頭によりもたらされ、正式に清王朝が成立(一六四四)すると朝鮮の小中華思想は完全に破壊された。その間に明との断交に晒されることになる。朝鮮二六代目高宗(在位一八六三〜一九〇七)を最期に李氏朝鮮の血統は断絶する。それはまた現行北朝鮮の始まりでもあった。
もとより王政社会における王権の弱体化と復古は天皇制を除けば洋の東西を問わず歴史の常道であって、朝鮮のように最初から冊封体制のもと王子が後継を争って殺し合う国家に自律性はありえない。一二歳の高宗即位も幼い王子を利用して王后を送り込む外戚と王系一族の権力闘争であり、安東系の金氏による五九年の独裁政治に対する反抗しかない。
●両班制と本貫
そもそもの元凶は両班(官僚機構)制度にある。両班は高麗・李氏朝鮮の時代に支配構造を担う官僚機構の身分階級であるが、本貫というものが認識されないと意味が通じまい。本貫とは同一氏族のルーツつまり姓を確定する発祥地を表す言葉である。姓が同じ場合でも、本貫が違えば、氏族は別と見なされる。朝鮮の姓はおよそ二五〇と少なく、大姓五種は金・李・朴・崔・鄭で、姓に本貫を関することにより互いを区別してきた。
金姓を例とすれば、同じ金氏でも、金海迦耶(駕洛国)王族系と新羅王族系では、血統がまったく異なる。歴史的に先祖の中で広く知られる者を始祖として、この始祖もしくはその子孫が住み着いた土地または封じられた場所を本貫とするのが朝鮮半島の慣わしと伝わる。また、中興の祖を中始祖とも呼んでいる。複数の始祖を持つ本貫もあれば、始祖から何代目と数えることも多く、始祖の違いや中始祖が異なる場合は流派を付して区別する。さらに同じ本貫でも、明らかに異なる場合は別本貫としたり、本貫の変更を講じるケースもあり、およそ朝鮮の氏姓鑑識は不可能と思われる。
その理由はすべて半島に特有の歴史事情に由るが、詳細はさておき、次は両班の認識を改めておく必要がある。
両班は文班(文官)と武班(武官)つまり両は二を意味し、二つの班からなる官僚機構のことを指す。もともと支那唐・宋朝の階級制度の最上位を占める貴族階級が両班である。この両班の資格は実力だけでは得られず本貫を管理する族譜による証明がなければ登竜門に立つことさえできない。両班の族譜は命よりも大事で、天災・人災に際して何よりも真っ先に族譜を持ち出したことからも窺えよう。
水原白氏が作成(一四〇三)したという族譜は序文しかなく消滅か隠匿か不明であるが、一般に族譜作成が本格化するのは一六世紀以降である。本貫の多くは新羅王族系や新羅統一に貢献した迦耶王族系、新羅豪族・貴族系、高麗巧臣、支那渡来系などからなり、隆盛を誇る家系には新たな本貫を設け分家も立てられた。
例えば、新羅王族の慶州金氏の場合は五六代目敬順王(新羅最後の王)長男系は絶え、二男系は羅州金氏を号し、三男と四男の系は慶州金氏、五男系は義城金氏、六男系は洪州金氏、七男系は彦陽金氏、八男系は三陟金氏、九男系は蔚山金氏に分かれている。
この金氏と血統が全く異なる前記の金海氏(金官迦耶)王族の場合は初代首露王系(駕洛国)ほか沙也可(雑賀衆説を軸に諸説あり)など祖とする贈金海金氏(友鹿)、首露王と王妃許氏の子一〇人の男子のうち二人が金海許氏を名乗り本貫を同じくしている。こうした本貫の基本認識に通じなければ、北朝鮮建国の父である金日成を釈くことは到底できまい。
●安東金氏と金日成・正日
ところで一八六三年の高宗即位まで五九年間政権を握って半島を支配した安東金氏には、新羅王族末裔を称する旧安東金氏と高麗(九一八〜一三九二)建国の巧臣を祖とする新安東金氏とがある。旧安東金氏の祖は、前記の敬順王四男の系から出現しているが、厄介なのは後に金寧氏と改称し血統のまったく異なる金海を本貫とする敬順王四男が祖という大族である。
ただし、戸籍売買は歴史の常であり、天皇制の如く明らかな痕跡を刻む氏姓鑑識の禊祓を怠らなければ、究明は不可能でない。他の本貫は省略し、少し両班の要点を絞り込んでおきたい。
支那の科挙制度を模した高麗の両班制度に遡らないと、何ゆえ李氏朝鮮が出現したのか理解しえないであろう。ましてや金日成・金正日の正体を剖判する何ぞは理屈さえ成り立たず、主体思想はおろか、何ゆえ盲腸にも等しい存在が列強諸国の政府を振り回せるのかは理解しようもない。
唐・宋の科挙制度で新規採用された文官らは当初から上級官僚の貴族化を目指すが、半島では新羅以来の郷里、つまり土着的地方共同体が多く存在し中央に多くの官吏を送り込んでいた。官僚が入り込めない郷里制度の残滓はすでに高麗の貴族と多くの門閥を形成しており、武官の世襲制も加え私兵化の根を広げていた。王族と貴族でなる高麗文官の支配は武官を両班と見なさない事実上の一頭政治となっていた。ここに武官クーデター(一一七〇)が起こり新王を擁立した武官政治が始まる。これを崔氏政権といい軍の私兵化と軍閥化と王の廃位まで行なう暴走のもと、結局は元王朝(支那)の支配に屈する運命に晒される。代わりに台頭したのが中小地主層を中心とする階級である。これら地方両班が高麗末期を支えたが、他方で武官に抑え込まれた文官から新興儒臣という新たな勢力も出現する。在地両班と違って、収入源である田地を持たない新興儒臣たちは高麗王に田地の提供を求めたが受け容れられない。そこで不満を募らせた急進派は李成桂を王に擁立する。すなわち李氏朝鮮の誕生である。
●李氏朝鮮の両班制度
以下、朝鮮の両班制度を検証する。
李成桂はまず新羅・高麗の残滓である郷里の権力追放を手掛けて科挙の受験資格を大幅に制限する身分制度を開始する。すなわち科挙(文科と武科)の受験資格を有する身分を両班に限定する思想であり、科挙の構成は三年に一度の見直しを行なうことにした。実質上の科挙は経済力を必要とし、逆にまた実力を備えても両班階級に属さないと受験資格さえ得られないのが実態であった。翻訳・医学・陰陽などの技術的職能を雑科と位置づけて中人階級に定め、農民を常人と称し、この三位を良民と呼び、最高位に両班を据えた。この下の身分階級は賤民と呼ばれた。良民から落ちて再び戻るチャンスを得られる奴婢(ノビ)とチャンスのない白丁(ペクチョン)があり居住・職業・結婚など制限された。この外に僧侶・巫堂(ムーダン)・妓生(キーセン)らも賤民に含まれ、奴婢には国有の公奴婢と私奴婢がおり、市場で売買された。
朝鮮の国学は儒教で固められ、両班は儒教の教えに従って労働行為を忌み嫌った。一例を引けば、自分で転んでも他に起こされるまで起ち上がらないとか、箸や本より重い物は持たないなどと揶揄されるほど、儒教思想に呪縛されたのである。両班の占める人口割合は当初三%とされているが、明と朝鮮を相手に秀吉が出兵する慶長の役(一五九八)や後金の胡乱を契機に身分制度が流動化し、国民の大半が両班階級だとする記録が現在に伝わっている。
その象徴的な証明は現存する在日の総連・民団メンバーに聞けば明らかだ。彼らは総じて自らの祖を両班というであろう。朝鮮王朝の法令史料にも両班の身分に定義はなく、世襲する両班の嫡子は自動的に両班を継ぎ、中人から昇格したり族譜売買など時代が末期に向かうほど流動化が激しくなる。特権階級の文官は兵役免除や刑の減免、地租以外の徴税・賦役の免除を当然とし、常民は両班に道や宿泊を譲り、家宅・衣服・墳墓・葬礼など生活全般に比較しようもない格差社会を形成した。
●安東金氏の勢道政治
さて、高宗即位の前後を繙くには、歴王三代を傀儡とし絶対的権力を行使する安東金氏に対立して、高宗の父(興宣大院君)と先々王(二四代憲宗(フンジョン))の生母(神貞王后)とが連携クーデターを計画する段まで遡る必要がある。大院君とは直系と違う国王の父に与えられる称号であるが、本稿では興宣(李是応一八二〇〜九八)を指すものとしたい。
憲宗(一八二七〜四九)、在位一八三四〜四九)つまり即位八歳、行年二三歳の生母は神貞王后(趙万永の娘)であるが、夫(孝明世子)は早世し憲宗は祖父(純祖二三代)を継ぐ幼年の即位である。
安東金氏の専横を勢道政治と呼ぶが、勢道政治の出現する前の歴史は王権による蕩平策が政局を混乱に陥れ、政争はカトリックの流入を招いて儒教との確執を呼び起こし外交問題を燻ぶらせていた。純祖一〇歳の即位(一八〇〇)に際して執政権を代行した貞純王后(純祖の祖父英祖(ヨンジュ)の第二王后で金漠の娘)は蕩平支持派を大量殺戮しながらカトリックの弾圧も徹底させた。貞純没(一八〇五)後は純祖王妃(純元)の父(金祖淳)が人事権を掌握し本貫を同じくする安東金氏一門で政権内を固める。追放された両班による大規模な反乱が続くも鎮圧され(一八一二)、その後は憲宗さらに哲宗(チョルジョン)(一八三一〜六三、在位一八四九〜六三)と繋ぐが、哲宗は正祖二二代(一七五二〜一八〇〇、在位一七七六〜一八〇〇)の弟(恩彦君)の孫である。因みに、高宗は恩彦君の弟(恩信君)の曾孫であり、正祖三兄弟の父(荘献世子(ザンホンセザ))英祖二一代目の二男で、英祖が行なう蕩平政治から生じる老論・少論の少論派として成長すると老論主流派と対立する。王権を強めて政治を安定させた英祖であるが、両班抗争に巻き込まれた荘献世子を怒り平民に落として餓死させている。詳細の記述は紙面の無駄なので、今後の展開にて察せられたい。
安東金氏の勢道政治を倒すために、大院君はまず相手を油断させる策に出て安東金氏一門を訪ねて物を乞い回り哀れを誘う企みを実践する。すでに大院君二男(命福のち高宗)の籍は神貞王后の手配により早世した孝明世子(翼宗)の養子としてある。何ゆえに二男かは長男が既婚者だからであり、何ゆえ翼宗の籍かは憲宗がすでに物故しており、翼宗・憲宗の系が王家本流だったからである。
少し前記のお浚いをしておきたい。すなわち王政復古を果たす英祖二一代の長男は夭折また二男(荘献世子)は前記の通りの悲運で、英祖は自らの後継を失う失敗をするが、荘献世子には男子三人が遺されて救われた。孫が成人するまで頑張り長生きした英祖の跡は直流(正祖二二代目)が継ぐも、嫡流の純祖二三代は即位(一八〇〇)一〇歳で、英祖第二王后(神純)が執政して内外多難な状況に大鉈を振るうが程なく没する。(一八〇五)。
この執政を受け継いで政権内を占めるのが安東金氏一門である。純祖一五歳の治世を代行し純祖の子(孝明世子=翼宗)は即位の前に没した。翼宗の子(憲宗)も即位八歳ゆえ、趙氏一門から出た生母(神貞)には後盾がなく安東金氏の専横に打つ手などなかった。ただし、憲宗までは何とか嫡男本流で王位を繋いできたが、憲宗が二三歳で没する(一八四九)と嗣子が絶えて、神貞王后の居場所も不安定となる。
荘献世子二男(恩彦君)の孫(哲宗二五代目)も即位一九歳であり、安東金氏の専横は止まず、汚職もますます蔓延する。哲宗の子五人はすべて夭折し、残るは荘献世子三男(恩信君)を継ぐ大院君の系だけで、父(南延君)は養子入した仁祖一六代目八世孫で大院君は四男として生まれた。仁祖は先王(光海君一五代目)の甥に当たり、先々王(宣祖一四代目)の庶子五男(定遠君)をの長男、クーデターによる即位だった。
●大院君の改革
遺伝子から生ずる本能的属性は歴史的環境の振子現象に遭遇すると、突如として芽吹いて因果応報という操作に支配されるという物理の原則がある。この原理を大院君は知らなかった。
病がちな哲宗が重体に陥ると大院君は命福(のち高宗)の聡明さを噂する流言を仕掛け、神貞(趙万永の娘)とのタッグを強めて直流と傍流を一本化させる。この作戦は哲宗を継ぐ高宗の即位で見事に成就するが、本番は安東金氏が占める両班の人事一掃にある。神貞を高宗一一歳の後見役として立場を安定させると同時に大院君(尊号)は摂政の地位を固めるため、まず安東金氏に蔓延する汚職を暴いて表沙汰とする一方、党派問閥を問わず風紀一掃に取り組む両班を採用した。安東金氏を追放し両班にも税を課すことで民心を掌握しつつ迫りくる西洋列強に対しては儒教による強硬な攘夷・鎖国思想で対峙することを決する。カトリック信徒を弾圧、殺害(一八六六〜七二)八千人にも及ぶ改革を断交した。その大量殺害は神父殺害を名目に軍船七隻を派遣して江華島を占領(一八六六)した仏軍を撃退する過程で発生した。また、仏軍侵攻二ヶ月前に米国商船ゼネラル・シャーマン号が通商を求めたときにも朝鮮軍は同船を沈没させ、後に賠償交渉のため米国の軍船五隻が来朝(一八七一)しても有無を云わざす撤退させるほどで、儒教の攘夷思想は苛烈を極めた。大院君の急ピッチな仕事ぶりは思想同根といえども、儒教(朝鮮)と儒学(日本)の違いを証明する重要な問題を含むことを史家は認識する必要がある。朝鮮半島の南北両断と再統一に巻き込まれざるを得ない日本の核心はこの時代より本格化するが、旧史を認識し得ない史観には論外の証と映るのであろう。
前記の通り大院君は祖父が荘献世子(平民に降格)三男(恩信君)、父は仁祖(インジョ)一六代目の八世孫が養子入りした南延君であり、その四男として生まれ、二男が高宗である。大院君の夫人は、驪興を本貫とする閔氏とされるが、父も本人も名が不明で、本貫を含め子細は確かめる必要もあるまい。なぜなら族譜不明の家系は歴史に埋没するのが必然であり、過去と未来に連続一貫しない徒花としか成り得ないからである。大院君の子は三男三女であり、長男の完興君(一八四五〜一九一二)は高宗に嫁いだ閔氏致禄の娘(閔妃)を担ぐ同族一派から国王廃位の陰謀という嫌疑のもと流刑一〇年と判決され喬桐島に流されている。庶子三男(高宗の弟)李載先も同罪で、済州島へ配流のうえ薬殺刑に処された。長女は趙慶鎬に嫁ぎ、二女は趙鼎九に嫁いで、両者とも夫君は日本政府が子爵に叙す痕跡を刻んでおり、三女(庶子)は李完用の兄(李允用)に嫁ぎ、同じく夫君は男爵である。
略記を要するのは李完用であるが、初期には高宗のため反日親露の重鎮となるも日露戦争後は親日派に転向して最終的に同じく侯爵まで昇ることは、史家なら誰でも知るところだろう。
問題の閔氏一門が王宮へ入る契機は大院君夫人の推挙を聞き入れ高宗即位三年目(一八六六)に閔妃を迎え入れた大院君の判断とされるが、皮肉というより莫迦げた史観である。神貞との連携クーデターは絶対条件であり作戦は見事的中したが、安東金氏一掃と儒教思想の攘夷鎖国を急ぐあまり肝心要の王政復古が天皇制のよう整備されていない。高宗には王后となる閔妃のほかに側室六人がおり、閔妃は二人の子を産むが、第一子夭逝(一八七一)、二子(坧)が成長し純宗と改名する。側室の中の李氏淑媛が産む子(墡のち完和君)は母子ともに変死(一八八〇)、また嚴氏徳安宮の産む子(垠)が英親王、さらに張氏宮人が産む子(堈のち義親王)などいるが、他は省略する。大院君が高宗第一子(完和君)つまり初孫の生誕を慶ぶのは当然としても、閔妃第一子が数日で死去(一八七一)するという閔氏一族の悲運に如何なる配慮を示したかは判らない。摂政辞任(一八七三)により高宗二二歳の親政が始まると、大院君は京畿道揚州へ隠居して高所から王権運営を見守ろうとした。
●閔妃傾国と列強による支那蚕食
すると、閔氏一門は直ちに王宮を支配する強行策を発動させる。大院君派の追放・流刑・処刑に並行して、自らの族である官吏三〇数名をすべて高官に昇格させ内堀また外堀を閔氏一門で固める常套手段は半島の歴史に繰り返される宿痾で、ここにおいて鎖国の舵は急転し開国に回される。
まず開国路線の成功例として羅針盤が示したのは日本だった。江華島条約のもと日本の顧問を迎え軍事的近代化を図ろうとする。ただし、付焼刃は寿命が短く、多大な損傷を被る日本政府は征韓論(正しくは征朝論)を抑え込むことでさらに損害を大きくする。
儒教の信奉集団は閔妃殺害を企てるが、危急存亡に際し閔妃は朝鮮に駐屯中の袁世凱を頼り、単なる生き残りに身を預ける。袁世凱は大院君を軍乱の首謀者と決めつけて、支那天津へ連行(一八八二)のうえ三年間幽閉する。その帰国(一八八五・一〇)に重要な役割を果たす日本の内閣制発足も見逃せない。
一八八四年一二月に清国の傀儡国に陥れた閔氏の暴走政治から日本居留民の安全を確保するため、軍は王宮を占領したが、脱出に成功した閔妃を確認する袁世凱は日本の公使館と居留民へ向けて軍を差し向けた。再び政権を奪還した閔氏政治に今度は金玉均ら開化派が攻略するも三日天下に終わって、彼らは日本へ逃亡して潜伏する。
翌一八八五年一月に日本代表特使の井上馨と、慶州が本貫で大院君派に属し開化派も率いる金弘集(首相格)との間で漢城条約が締結される。また、四月には日本側代表伊藤博文と清王朝幕僚李鴻章が天津に会談し、大院君の帰国と朝鮮からの両軍撤退を決する条約に調印した。ところが袁世凱は身分を駐箚(駐在)朝鮮総理交渉通商事宣として居残り、清王朝を背景に朝鮮を支配する目的で駐留した。
明治一八年(一八八五)は維新政治が内閣制を発足させた(一二月二二日)年であり、初代首相は伊藤博文、また初代外相は井上馨であった。漢城条約相手方の金弘集は大院君そして高宗の時代を通じて政治の首班格として国家を担った人物。また、李鴻章は西太后の信任暑く洋務運動(欧州文明導入)を担う首相格だった。
こうした朝鮮史の在り方を検証していけば、もとより原点が支那との冊封体制にあることは歴然であり、問題は朝鮮自体よりも支那事情にあることを認識する必要がある。明王朝の皇帝を唯一の天子と仰ぎ女真を蔑視しながら日本との交易にも倭館制度を強行した朝鮮は、女真を主体とする後金に明国が崩され清国が成立すると小中華思想も現実となる。
これに比して日本からの出兵では、秀吉のときも古くは神功皇后のときも朝鮮半島の悪しき制度が修理されこそすれ、民族自体は何一つ破壊されず、また日本に渡来し頑張る筋には帰化も認めている。にも拘らず、唯一神を奉じる朝鮮の悪しき性癖は現在に至るも改まらず、北では主体思想を南ではキリスト教を奉じている。その思想の陥穽に自ら気付くのを俟つほかない。
次第はともかく、支那の洋務運動に伴って最悪の病魔アヘンが侵攻を開始する。ここに内政問題は形を変え外交政治にも影響を及ぼし、朝鮮を支配する必要性とも絡んでくるのである。
第二次アヘン戦争とも呼ばれているアロー号事件(一八五六)は、結果的に清国が英仏を相手とする戦争(一八五七〜六〇)に発展した。その結果は露国も巻き込む北京条約の締結となり、清は列強国の格好の餌食にされ、支那大陸の割譲を現実のものとする。
支那は始め北京から遠く離れた香港・広東・厦門・福州・寧波・上海などの治外法権を軽視したとしか思えない迂闊を犯している。ようやく事の深刻さに気付くのは、列強の欧・米・露が治外法権の地を舞台に火祭りを恒例化し鞘を当て合う展開を見せ始めてからである。とくに、北京条約の調停役を売物とした露国の南下は支那の脅威となり、閔氏王宮の不安定な動向を実感して自らの反省をも加えれば、朝鮮史における重大な転換点だったといわなければなるまい。
征韓論を罰した明治政府も、傲慢な支那と不安定な朝鮮半島の状況が日本に如何なる影響をもたらすか、改めて思いしらされる現実に遭遇する。欧米視察団を機に流行する諸国の留学情報にしても、露国の脅威を含めて列強の覇道主義が如何なる現実を含むのか、その再認識は新たな悩みのタネを撒き散らすこととなった。
朝鮮の農民層に巣立つ東学は儒教・仏教・道教を雑炊の如く仕上げてあるため、飢えに苦しむ地方公務員にとり何よりも活性剤となっていたが、この東学を核として蹶起したのが一八九四年の東学党の乱であった。