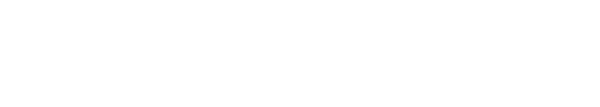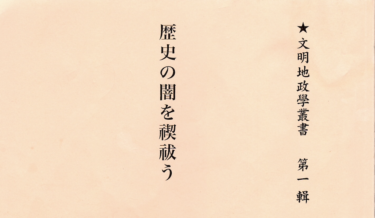さて、ここまでを省みておきたい。
栗原常吉は出生後しばらくして古来伝承のシンジケートに認められ、本人が気づかないまま、ごく普通の環境下で養育され、自覚が芽生える幼年期になると、気づいた時には石鎚山の修験道場に通う事が当たり前のような少年に成長していた。やがて石鎚山に籠るようになり、親元にもどると、親の言いつけで京都へ使いに出された。
常吉は目前で生じる事象に自力で対応する青年になっていた。目前の事象には目を逸らさず、自ら関与すべきか否かは瞬時に判断したようで、他の力を頼った覚えはないようだった。このことは父も私も一貫してきたから、身に染みて常吉の自然体が理解できるのであり、自ら関与した場合は結果が生死を賭ける事でも退かない、それが父と私の絆で断ち切る事は不可能なのである。
常吉と秀孝と私を結ぶ絆で異なるのは、遭遇した時代の結び目が違うだけで、他の状況は落合本が説くように、歴史の相似象を理解する力がつけば明らかにわかる。今様の「夢は適う」とか「やればできる」などの戯言は人心を蝕むだけ、タバコの煙害と変わらない。明日や未来を知りたいなら落合史観を学ぶことが何よりも先決だろうと私は思っている。
常吉の時代は自力を強化しても、妻帯して子に恵まれても、その養育と命を護ることなど、どんな対策を講じても保証は不可能と思うほかない。而して、常吉は流れに逆らわず、侠友の妻子の保護を目的に自身が戸主となり、未亡人と娘を養子に迎え娘の嫁入りまで為しえたのである。常吉は侠友の妻子を離れの間に住まわせており、夫婦縁組は養子を迎えるための体裁のみ、万端を整えたのち家督継承に見合う養子を迎え入れたにすぎない。
栗原常吉の家系が相応の養子縁組で継続されると、修験継承に相応しい秀孝が生まれ、その資質が錬磨に適うか否かを試すため、常吉は幼い秀孝を伴い石鎚山に籠ってみた。見込んだ通りだったので両親の許しを得たのち、人生の終活を秀孝へ託すことに決めている。すなわち、四国の栗原系本流は家督継承を実兄が担うことになり、分家常吉流は真鍋系栗原家に継がれ、常吉流修験は真鍋系秀孝に継承され、分家秀孝流は私が継いだことになるが、私は修験子でしかないと自認している。
ここに念のため、家督に触れておきたい。現代のごときゾンビすなわち甦った屍の跳梁が全世界へ拡がると、移り変わる日々の変化に行き場を見失ったゾンビの跋扈が止まらない。ゾンビを鎮魂して安置する事は急務であるが容易に成就する問題ではない。たとえば、矛盾と非合理を放置して、枝葉末節を事実といつわり、小賢しいコメントを売り捌くのが学術とうそぶくテレビ、その影響はコロナ型ウイルスをはるかに上回る毒を有する。事実は氷山の一角にすぎないため、真実を知るには氷山の全貌を解剖しなければ、事実は妄想を拡散するのみ、これがテレビ社会の怖さである。
学術の重要性を広げる最強の兵器は文字で、文字は一神教というミサイルを放って久しい。やがて文字は映像化されテレビを生みだした。かくして全世界に蔓延したのが認知症ということになる。
すべては損得勘定の誤解から生じている。家督は通貨に替えて計れるものではない。通貨に両替が可能な遺産は家督の一部でしかなく、計り知れない信用こそが家督の大半を占めるのである。
平城京そして平安京を造営した叡知は、落合史観の通り、ウバイドの丘に発祥した情報が古代エジプトの本位財を路銀に替えたのち、西の極と東の極に本拠を定めてはじまる。東方の陽いずる場には貧富に関心が薄い温和な縄文人が暮らし、柔和な渡来民とは混交も辞さないために、他と競い争って富を奪い合う征服民には、日本列島が魅力ある場と思えなかった。この縄文人こそがウバイドの情報ネットワークが求めた理想であり、列島は文化文明の発展が託せる期待の場となった。
通史のシュメール文明は発祥がウバイドに背乗りしたもので、落合史観こそが正史でオリエントの場は競い争う征圧の坩堝だったのである。太安万侶が撰録した記紀には「アメツチのハジメ、タカマノハラに成りませる神の名はミナカヌシとタカミムスビとカミムスビ、このミハシラは独り神ニ成りましてミミヲ隠しタマヒキ」そのあと「ウマシアシカビヒコヂとアメのトコタチ、このフタハシラも独り神ニ成りましてミミヲ隠しタマヒキ。上のクダリ、イツハシラの神コトアマツカミ」とある。
つまり、ウバイドは独り神で身を隠すのが本質ゆえに、現世の原初に開示されたのは、文字でなく基礎語五十一音すなわち「あいうえお」~「ん」までの音で編む言葉を指しており、世界中の言葉が流入してくる終着地が日本だから、日本で整理された言葉が最も確かな意味を伝えるはず。なぜならオリエントにも日本の基礎的用語は多くあり、世界中の神話にも日本の語源になっている神々の名が少なからず散見されている。
私は津田元一郎(一九二五~)著『日本語はどこから来たか』人文書院の本を使っている。領土の拡張に文字が役立つようになると、征服民の動向は競い争って広範へ及ぶようになり、やがて日本も征服民のターゲットにされるのはさけられない。縄文人の温和性を案じたウバイドの杞憂はいやが上にも増してくる、縄文社会の強化は専守防衛でなければならない。もとより、勤労勤勉の習慣を身に帯びた民族性はすでに強靭な身体力と叡知を備えていた。
人類で最大最強の情報ネットワークを築いていたウバイドは、選抜された縄文人の演習地に適した羅津(ラジン)港と日本の港を結ぶ往来ルートの整備に着手していた。羅津については落合と津田の著書から全容がイメージしやすい、現在の豆満江を要に大連とハバロフスクを結ぶ緩いカーブ線から成る扇型と思ってもらえば大凡は適合しえよう。騎馬を使い最先端の武具を用いる世界無比の兵法はウバイドの情報ネットワークから生まれ、その時代は皇紀暦を編む数世紀も前との口伝が今を生きる修験の世界に行き交っている。
すなわち、神武天皇の即位はるか前にウバイドは縄文人と交流しており、縄文人の選抜組が日本と羅津を往来するようになったとき、その選抜組に対応したウバイドの玉(天皇)は御簾を間に対面の儀に及んだのである。これが記紀の冒頭「独り神になりまして身を隠し賜ひき」の意味であり、欠史八代の段で温和な縄文の大和撫子と初めて結ばれたのかもしれない。
どうあれ、必須を欠かせないのは落合本と津田本の読書を薦めるほかない。記紀については、神の名(仮名=神名)を基本語五十一音に置き換えること、それらを修験は「タマコト=霊言」と言って最も重要な口伝に使用しており、太安万侶が重用した稗田阿礼の旧事口伝も同類と聞いている。
古代エジプトの神官が権勢を長く保持しえたのは、文字の発明と開発が主因とされるため、第一に重要視されたのが書記官の養成であった事は容易に察しがつくところ、遺跡に刻まれた絵文字を創め文字の筆記媒体に使ったパピルスの加工も上代の賜物といえよう。神の世を紙の代と伝える伝承とて単なる洒落と笑い飛ばすだけではすまされない。
少し羅津に触れておきたい。霊言でラ=羅は輝き・栄光・利益・更新などの意味を有して、ラ音と他音との組合せには、アラ・カラ・サラ・タラ・ナラ・ハラ・ワラのように、上代の謎を解くためのキーワードが多数あって、エジプトでは太陽神をラァと表現しており、ナイル河のナイルを意味する言葉は輝ける生命の泉と解釈されている。
ジン=津(ツ)は著者の姓にも用いられるが、日本の上代では「チ=血」をも包括する精液全体を指す言葉とされる。ツはすべての内的連関をもつ言葉であり、ツ音に宿した玄義には、宇宙と生命に関わる深い秘儀が隠されている。ツバキ=唾液はシンエキ=津液とも言われる。
(続く)