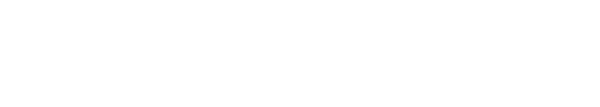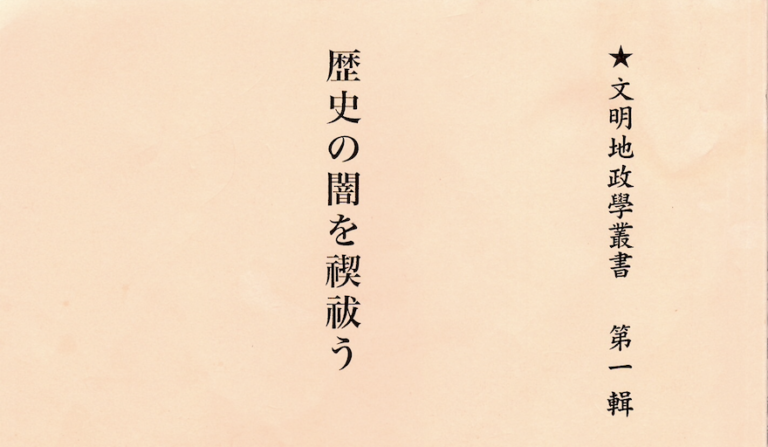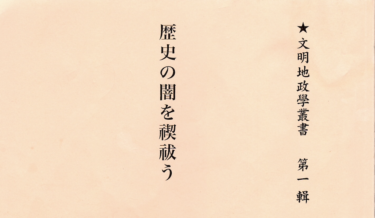●朝鮮亡国の経緯
東学党の乱(一八九四)そのものは歴史の一通過点にすぎないが、過去と未来の連続性を抜きにして単に歴史を千切り取るのは史観ではない。
金玉均(一八五一〜九四)は科挙文科の合格(一八七二)を機に開化思想に目覚めて日本へ遊学(一八八二)し福沢諭吉らの支援を受けたという。再度の来日には、大隈らに朝鮮近代化のため借款交渉を申し入れ、相応の手応えをつかんで帰国(一八八四・四)すると、高宗の一本釣りを達成する。
同年一二月の三日天下は前記の通りで、日本へ亡命して復権運動を展開、さらに上海へ渡るも刺客に暗殺(一八九四・三・二八)される。その遺体を朝鮮に運んだのは清国籍の軍船で、凌遅刑つまり支那の重罰処刑法で遺体がバラバラに斬り離された状態だった。首級は京畿道竹山に曝され胴体は川に遺棄、片手片足は慶尚道に、もう片方は咸鏡道に曝されたと伝えられている。このように遺体各部を半島の中央部・南方部・北方部に晒すには相応の意味がある。すなわち、玉均の本貫がどこか、清国も閔氏も鑑識できないようにすること、半島最大の大姓である金氏の復権を封じること、このためである。現在の北京政府が金王朝に振り回されるのも玉均の遺体を陵辱した因果応報なのかもしれない。
因みに、玉均亡命の際は父が死刑、母が自殺、弟が獄死という非命に晒され、妻(愈氏)は奴婢に売られるも、副島種臣の手配で買い取られて日本に保護されている。
一八九四年八月一日に日本側の宣戦布告で始まる日清戦争の記録は他の資料に委ねるが、その開戦に当たり閔氏の有力者はすべて誅殺された。翌一八九五年四月一七日の下関条約で戦争は終結するが、独・仏・露の三国干渉(同年五月四日)により閔妃はロシアの傀儡に移し変えられる。
再び閔妃を傀儡とするロシア系朝鮮が成立すると、日本政府は三浦梧楼を駐箚朝鮮公使として着任(九月一日)させる。
こうした経過において軽視できない出来事が玄洋社の設立(一八九一)で、閔妃暗殺(一八九五・一〇・八)にも無関係とはいえない。金玉均の亡命に際し最大の理解と支援を実証したのは玄洋社であり、玉均らの運動を辿れば福岡藩と重なり、神の計らいと通ずるものがある。
閔妃暗殺の嫌疑首謀として公使解任(後任は小村寿太郎)され裁判に服す三浦梧楼(一八四七〜一九二六)は、萩藩士家に生まれ、陸軍士官学校長を務め山形有朋ら主流と対立、関係者全員が無罪となるが、いみじくも明治四三年の朝鮮総督府が設置された年に枢密顧問官となる。その後も反骨の遺伝子は健在で、在野のフィクサーとして朝鮮問題に取り組んでいる。
閔妃暗殺の翌月一一月二八日には、春正門(王宮禁門)破りが勃発した。これは金弘集(首相)の暗殺を企てたクーデターと伝わるが、本筋は李氏が同族高宗を頼って自作の案を勅とするよう望む行為としか思えない。何よりの証は、襲撃の混成部隊が王宮門番の親衛隊長に説得されて退き親ロシア派と親アメリカ派を標榜しつつ露・米の大使館にこもって保身を図る日和見の態度に見ることができる。何れにせよ、閔氏に屈して高宗を救い出すこともできず、高齢の大院君にも及ばぬ為体だから、反日派を唱えても痛くも痒くもない存在だろう。
以後、露・米を軸として反日を煽動する謀略戦が展開される。翌年二月に警務庁前で金弘集ら要人の惨殺が発生すると、大院君派の粛清が本格化し、再び責任不明を装う傀儡政権が組み立てられる。朝鮮問題をめぐって、日露議定書が一次二次と調印される段階においては、すでに金鉱採掘や鉄道敷設など利権に結び付く権益はことごとく露・米の手に帰していた。
因みに、金弘集殺害の同じ日に高宗は家族らとともにロシア大使館に確保されて、慶雲宮に還るのは翌一八九七年、つまり一年後である。同年一〇月一二日に国号は大韓帝国に改まるも、実態はロシアとの傀儡政権で、ロシアは半島を拠点に虎視眈々と獲物を狙う目で日本を睨み付ける有り様となる。
日露開戦前の日本の動向は前記の通りであるが、朝鮮では独立協会(一八九六〜九八)という団体が存在した。立憲君主制の下の開花を標榜する運動に始まり、創設には李完用も関わり後に李承晩も加わるというが、日清戦争のあと独立門まで築きながら、清国冊封からの解放を生かし切れていない。
この運動を引き継ぐのが慶尚道尚州を本貫とする李容九(一八六八〜一九一二)ら両班門閥が設立した一進会だとされるが、実体は日露開戦に際して反日から親日へと豹変した転向組である。伊藤博文の没後に韓日合邦を要求する声明書は一進会の建議書として純宗、李完用首相、韓国統監曾禰荒助に提出された。一九一〇年八月二二日の日韓併合後に一進会は解散する。
●大陸プレートに翻弄される半島の宿命
ロシアはオスマントルコと露土戦争(一八七七〜七八)を戦って勝利すると南下を本格化させる。西洋に築かれた利権を東洋にまで広げるため支那を利用し朝鮮半島に布陣したのである。通説では不凍港を求めての南下政策ということになるが、すべては支那の失政から生ずるものであり、彼らの史観が如何に傲慢であるかの証であろう。
日露戦争についても詳しくは触れず朝鮮に焦点を絞ることにするが、現在の半島両断はロシアにおける第一革命(一九〇五)に起因しよう。もとより封建的専制政治に対する不満はロシアに限らず人の本能的属性に発するものだから、時代の趨勢により革新は必ず起こり得るものである。問題は為政を司る立場が自らを禊祓できるか否かであり、自らを禊祓できなければ御破算で願いまするの戦争を繰り返すほかなく、これが歴史の宿痾だろう、
その火種は富裕と貧困の格差不公正を理屈とするが、実態は単なる理屈であって、理屈は思想を刺激して宗教や哲学を生み出しはするが、情知が独り歩きしていくだけの話でしかない。
ツアーリズムもナロードニキも所詮は人が高度の雑食生物たることを知らない野生もしくは畜生の本能的属性にすぎず、資本論など唯物主義に至れば単なる暴動スイッチにしかならない。後年ボルシェヴィキなる政府がロシアに出現するも、その中身はスペイン・ポルトガルによる大航海時代の掠奪・破壊活動と何ら変わらない。
され、時代を一気に超えて、金日成が出現する当然の帰結を本筋から剖判していこう。日露戦争で覇道という既定路線に乗らなければ現在の日本はなかったであろうし、歴史にifを唱えても、善し悪しを決定するのは勝者しかいない。
日露開戦(一九〇五・九・五)に際しては第二次日韓協約(保護条約)が結ばれた。その年末一二月二〇日に統監府が設置される、一九一〇年八月二二日の日韓併合条約で一〇年余(一八九七〜一九一〇)続いた大韓帝国の国号は消滅し再び朝鮮に戻って日本の保護下に自らの命運を託することになる。
すでに支那の国権機能は不全体質に陥っていて、歴史をタイムスリップすれば、さながら五代十国時代(九〇七〜六〇)に戻ったかの如き様相となる。
この余韻が朝鮮半島に及ぶとき激甚の災害を呼び起こす必然性こそ、大陸プレートのメカニズムである。支那(惑う星)を君主と定めて自らの立場を衛る星と契り約したのは李氏朝鮮であり、日本は古代から一貫して自主独立の軌道を保ち得てきた。支那や朝鮮に如何なる作用・反作用が起ころうと、常に日本は禊祓のもと決して他の国家の傀儡に陥ることはなかった。支那は自らの巨体を持て余し、自らの臓器に間厄(アヘン)を取り込んで精神まで病んでしまう。身体には本来備わっているはずの自浄作用が機能不全に陥っていることを見過ごしたからである。朝鮮は自ら尊厳を失って、国王は駐在ロシア大使館に逃げ込んだ。瓦解した朝鮮の志士は日本に救いを求め再生への運動を展開する。大西洋圏域で発生した乱戦が何ゆえ支那大陸に持ち込まれたのか。御破算で願いまするという本能的属性の千切り取りで説明できるほど、歴史は単純ではない。
大東亜に漂う暗雲が自然に晴れるのを待つことのできないのが政治的本能であり、嵩が個人情報を抉り出しても意味がないのは承知だが、反吐の出る苦しみを堪えて記述を進める。
英霊に殉ずるなら筆者が戦記を記す何ぞは許される訳もないので、戦記は他の作り話を参照されたい。大東亜の暗雲に限らず北半球から南半球の一部まで覆い尽くした地球人類の環境破壊は、日本に落とした原爆がキノコ雲を舞い挙げる形で決着する。このことの意味をとくと認識しなければならない。すなわちそれは、日本以外に地球・生類を救うことのできる聖地は存在せず、世界史が日本史に集束することの証なのである。
●マッチ・ポンプの国際労働者組織
第一次世界大戦という言葉は第二次に及んで初めて意味をもつものであり、戦禍が大東亜戦争に及ばない限りは単なる大西洋戦争にすぎない。北半球に暗雲を漂わせたアイスランドのラキ火山の噴火は北米大陸アメリカ一三合衆国の独立を脅かす欧州フランス革命の下で世界統一(ワンワールド)思想の夢想が独り歩きする。その火種は第一インターナショナル(一八六二)という国際労働者協会を立ち上げて政策瓦解を自ら招いた権力の自らの生き残りを謀るため火の粉を飛ばしたことに始まる。さらに、パリ・コミューン(一八七一)において、ドイツで失敗したプロレタリアによる革命(一八四八)を焼き直すため理屈論争するも同じく消炭の如く終わる。第二インターナショナル(一八八九〜一九一四)も小火と消火というマッチ・ポンプの繰り返しで、第三インターナショナル(コミンテルン)に至っては第二インターナショナル(一九三八)こそ世界社会主義という理屈を暴力に仕上げる火遊びである。その実体は、表をナポレオン三世とすれば、裏はロスチャイルドらの利権に蝟集する集団であり、フリーメイソンや米国リンカーン大統領の奴隷解放宣言(一八六三)を利用して始まったが、所詮は少数の富裕層が多数の貧困層を操るため如何に上手く御破算を願うかの設計でしかない。
この設計段階で歴史の犠牲に晒されている粗忽者こそカール・ハインリヒ・マルクス(一八一八〜八三)であり、ここでも少し触れておく必要がある。ユダヤ系神祇官(ラビ)を歴代つなぐ支族に生まれたが、父ヒルシェル・ハレヴィ・マルクスはキリスト教プロテスタントに改宗し上告裁判所付弁護士となる。母アンリエットはオランダに生まれたユダヤ人で、父よりユダヤの血が濃く日常生活にイディッシュ語を使用したと伝わっている。姉ソフィは六歳で洗礼(プロテスタント)を受け、後に無神論者となる。マルクスは高校時代を熱烈にルソー崇拝する校長の下で育ち、思想はヘーゲルに始まりベルリン大学に進むが、二一歳のとき父が没する。姉の友人イエニー・フォン・ヴェストファーレン二二歳と婚約するのは一八歳のときであるが結婚は八年後。前々年の一八四一年にイエナ大学への学位請求論文で哲学博士号を二四歳で取得した。その翌年に出会うフリードリヒ・エンゲルス(一八二〇〜九五)が後にマルクスに遺稿『資本論』二〜三巻を編集・出版することになる。
つまり資本論は第一巻だけがマルクスの自作であり、遺稿は時代が設計する苗床に利用され第一巻も哲学を市場化するという時代ニーズに合致しただけの夢想にすぎない。
ここで、リヒャルト・ゾルゲ(一八九五〜一九四四)の伝記を繙きつつ、その足跡を加えながら時代を透かして、大戦終結のあと朝鮮半島に出現した金王朝の核心に迫ることにする。
ゾルゲが生まれたのは、カスピ海を臨むアゼルバイジャンの首都バクーである。父は鉱山技師ヴィルヘルムで、母はロシア人ニナだった。この夫婦には九人の子供が授けられ、ゾルゲ三歳のころ家族と一緒にベルリンに移住したという。マルクスの秘書にゾルゲの伯(叔)父がいたというが、ゾルゲはマルクス没一二年後の生まれだから、如何なる計算をしようと祖父の代より後になることはありえず、作り話はすぐに崩れたる。重箱の隅を突くような趣味はないが、大物スパイが背負う運命は歴史を弄ぶ興行の好餌ゆえ、史家ならこのような些事も看過できないのだ。ゾルゲ生誕年をエンゲルス没年とし、死刑判決を下す日本の行政がゾルゲの所属を労農赤軍参謀本部第四局に定めたのも暗黙の国際慣行があり、スパイの消息はすべての黙示録的マニュアルで処理される。すなわち、新約中の一書「ヨハネ黙示録」がそのマニュアルで、キリスト教への迫害を背景に協会宛の手紙七通と幻視的啓示七つから成る。神の子イエスがサタンと戦うという図式がスパイを裁く模型になっているのである。
因みに、マルクスとバクーニンとが争うパリ・コミューン(一八七一)を目の当たりにするのは西園寺公望(一八四九〜一九四〇)で、その見聞が後の民権思想に反映することになるが、孫(公一)がゾルゲの仲間になるのは歴史の因縁というべきだろう。また、前記の通り、筆者は長與稱吉(一八六六〜一九一〇)がドイツ留学中に現地女性との間に設けた子をゾルゲであると断定している。
●長與稱吉のドイツ・オランダ留学
明治四年(一八七一)から六年まで欧米視察する岩倉使節団は留学生四三名を米・英・仏・独・蘭などに派遣の形を残している。前記の通り米国留学は金子ほか牧野伸顕、鳥居忠文、津田梅子、山川捨松、永井(瓜生)繁子ら、英国には中江兆民、鍋島直大、前田利嗣、毛利元敏ら、ドイツには平田東助、長与専斎らが滞在している。これらの留学生が帰国してかあ如何なる事跡を刻んだかを検証すれば、ミイラ取りがミイラになったのか否かが判然とする。その識別は史家の本領を問われることになる。文献史家には不可思議極まるのが私奴婢(スパイ)の世界である。これらの経歴に相関していく前提を心得ず千切り取るだけのゾルゲ論などは意味なく、スパイの存在を抜きにした史観は政府御用達の作り話にすぎないことを銘記すべきである。
個人情報を持って史観とする作り話を信用しない筆者の根拠は、個人情報には目先の立身出世を急ぐあまり危険を安全に置き換える実績を何一つ持たない詐欺が通用するからである。
例えば、金子賢太郎が父一代の限定士分を若くして自ら永代士分へと昇格させたことは危険を安全に置き換える実績と称すべく、金子は時代の激変に応じた身の処し方で日露開戦と同時に後始末のために動いている。いわば、金子は父子二代にわたる私奴婢身分を一代で仕上げたあと、維新政府に爪弾きされた主家を代表して明治・大正・昭和の荒波に立ち向かったといえよう。もちろん福岡藩の浪人らが背景に存在したことはいうまでもない。ただし、何ゆえ金子が主君の随行に選ばれ米国に留学したのか、さらにはこの人事を行使したのが如何なる存在かを勘案する必要もあるにはあるのだが・・・・。
長与専斎がドイツとオランダに留学して帰国(一八七三)、翌年に文部省医務局長に就任、東大医学部の前身という医学校の校長を兼務後すぐ内務省衛生局の初代局長に就任(一八七五)した経歴はすでに述べた。
東京帝大設立時(一八七七)に同時に設置された医学部を卒業する専斎の長男(稱吉)は留学のため明治二二年(一八八九)二四歳から同二九年三一歳まで七年間ドイツに滞在した。
この間に起こる日本側の重大事象は、徴兵猶予制の廃止、憲法発布と施行、第一回総選挙、教育勅語発布、大津事件、教科書検定制の施行、大本営条例の公布、国家「君が代」制定、日清戦争と講和、三国干渉、台湾の台北占領、高宗ロシア大使館における政権運営、台湾総督府条例の公布、勧銀法の公布などが挙げられる。後藤新平のドイツ遊歴も明治二三年から二五年までで、稱吉留学と重なっている。明治二四年に訪日中のロシア皇太子が警備の日本人巡査津田三蔵に斬りつけられるのが大津事件である。
この時代にヨーロッパで再び起こった第二インターナショナル騒動(一八八九〜一九一四)を通説では国際組織の社会主義運動と称しマルクス主義運動とも呼ぶが、マルクス本人はとっくに没した(一八八三)後の話だ。パリ・コミューン(一八七一)後にマルクスが書いたレポートや、没する一年前に出版した『資本論』を根拠にマルクスの名前を使うのであれば、本人も文句を言えまい。だが、本人が出版したのは資本論の第一巻だけである。以後の第二巻、第三巻はエンゲルスが勝手に訳した本で、その後も政権の都合次第で書き換えられるのだから、マルクスは単なる被害者である。
どうあれ、筆者には興味のない理屈だが、注目するのはマルクスの名を借りて出現する第四インターナショナルに相乗りして立身出世を企む私利私欲が何ゆえ日本社会に芽生えたかである。この根源を掘り起こさない限り金王朝に振り回される現実は解消さず、また北朝鮮を通常路線に乗せる道も得られない。
●第二インターナショナル大会始末
第二インターナショナル・パリ大会(一八八九)の議事は社会主義思想の統一、就労八時間制、常備軍避難と民兵制推進、社会主義が参加できる政治、メーデーを休日になどの議題をめぐり進行した。一八九一年のブリュッセル大会では労働法の制定と国際的労組の創設が決議され、またチューリヒ大会(一八九三)では正統派マルクス主義と称する団体が方針とする政治行動による条件改善が支持される。一八九六年のロンドン大会では党派間の確執でアナーキストの排除が問題になった。排除されたアナーキストは独自に黒色インターナショナルを形成して、第二インターを日和見主義と批判し影響力を強める。このとき統制力と組織力を整えたドイツが全インターをリードする立場に浮上してくる。再びパリ大会(一九〇〇)に戻るとフランスの組織がブルジョア政党と妥協し入閣する是非を問う討議があり、例外措置として認められる。これらを受けて初めて全インター事務局が設置され、その会議で決まる方針に全体が従うという決定権付与が議決された。
一九〇四年八月、日露戦争の只中で開かれたアムステルダム大会の冒頭で、日本代表片山潜と、ナロードニキから国外逃亡した転向組のプレハーノフがロシアを代表して握手を交わし国際的な結束力を誇るアピールが行われる。片山潜(一八五九〜一九三三)は美作国粂郡羽出木村(現岡山県久米郡久米南町)の庄屋だった藪木家の次男に生まれ、親戚の片山幾太郎家に養子入りしたのは兵役回避のためとも伝わっている。
それはともかくシュトゥットガルト大会(一九〇七)はロシアのレーニン(一八七〇〜一九二四)やポーランドに生まれてドイツで活躍したローザ・ルクセンブルグ女史(一八七一〜一九一九)など歴史に聞こえる大物が参加したという。ヘーゲルの出生地として知られるドイツの都市での大会では、小委員会一四部会を設けて長文の決議を作成したが、「平和攻勢」とか「反戦抗争」など意味不明な言葉の羅列ばかりで労働者の希望を述べたにすぎない大会ともいわれる。具体的な行動指針も示されない支離滅裂の大会だった。
一九一〇年のコペンハーゲン大会は英国労働党が自国の軍事予算を認めたことから、ドイツ社会民主党との間で論争が起こり、結局ゼネ・ストの主張だけで閉会されたという。
バーゼル大会(一九一二)は臨時開催となった。つまり、第一次バルカン戦争を受けて招集されたが、前二大会の決議を再確認だけに終わった。
同じスイスで一九一三年に開かれたベルン大会は一貫して軍事予算に反対してきたドイツが内部分裂を起こし、是認派が出現する。第一次世界大戦の勃発(一九一四)で反戦会議を開くが、大会を開催する計画を決定したのみで何ら具体的な抑止策も示されないまま終わっている。
激化の進む戦時下でフランスの雄弁家として知られたジャン・ジョレスが暗殺されたり、第二インターを牽引してきたドイツ社会民主党が参戦を支持し、それにフランスやオーストリアも同調するに至っては、第二インターという名の社会主義思想は、もはや通用しなくなっていたのである。社会主義思想が再び世界に姿を見せるときは、「共産主義思想」と名前を変えていた。