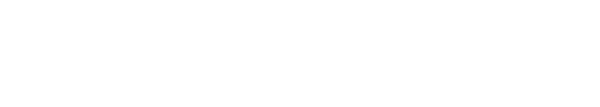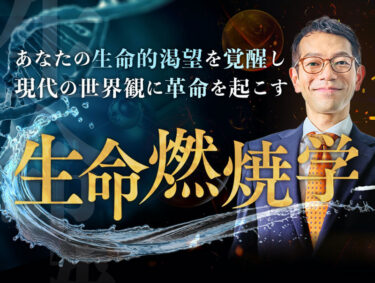こんにちは。
戦略思想研究所 中森です。
【ツラン論考3】では、
「オスマントルコの正体」が、
「金一族六流のうち二流」であることの
考察の一部をお届けしました。
テュルク系民族は、学説は確立されていないとしても、
匈奴やフン族が自分たちの先祖だと考えていることから、
匈奴出身の金日磾(じつてい)の系譜が、
落合史観が新羅のルーツと洞察するフン族に
合流する流れを記述することで、
ひとつの仮説を打ち立てようとした考察です。
その仮説とは、
「匈奴とフン族に潜入したスキタイが、
匈奴の金一族、フン族の金一族を養成した」
とするものです。
ここで、スキタイについて述べる必要があるものの、
「スキタイとは修験であり世界最高の傭兵派遣企業」
と伺っていると述べるにとどめ、
詳細は別の機会に譲ることとします。
企業では民間軍事会社のようなイメージとなりますので、
「機構」と表現した方が適切かもしれません。
さらに、国家に従属する機構ではなく、
ワンワールド史の本拠たる中央アジア、
即ちワンワールド・キャビネットの構成員
「マギ」の拠点たるヒンドゥークシュ山脈
に従属する機構です。
したがって、スキタイとは、
「ワンワールド傭兵派遣機構」
であると仮に表現しておきます。
そうなれば、ツランについてもまた、
「古代の大規模事業を支えたワンワールド職能機構」
であると仮に表現できそうです。
今後の論考の中で表現が変わることもありますが、
ツランおよびスキタイについては、
通説の認識を白紙にして頂いたうえで、
血統的民族としてよりも機構として認識することで、
ここから先を進めたいと思います。
さて、今回は、
東大寺教学部が編集する『シルクロード往来人物辞典』から、
ワンワールド史のロードマップの一部を描くこととします。
同書では、
インド・中央アジア等西方より中国へ渡来した物として、
金日磾(じつてい)を巻頭に紹介していました。
逆に、
中国(朝鮮を含む)よりインド等西方に往来した者として、
張騫を巻頭に紹介しています。
以上を念頭に、
同書から中央アジアに関する記述の一部を引用します。
(以下、引用)
——————————–
ひとの往来という歴史の一側面において、
インドや中央アジアと中国との関係からみると、
それはけっして相互対等ではない。
中国が、
あるいは中国のひとが西に向う動きには、
意図がある。
政府の使節とか、赴任する役人、軍隊、
それに仏教の僧たちの熱烈な求法といったように、
大なり小なりそれなりに積極性がある。
これに対して西からの意図的な動きはない。
中国に対する意識は至って低いのである。
(中略)
インドや中央アジアと中国との関わり方や、
ひとの動きの傾向を、上のように理解するとして、
つぎに指摘しておかなければならない点は、
こういった事実をよく示してくれる情報源のことである。
つまりそこにいちじるしい偏りがあることである。
この偏りこそは、
中国の西側に対する対応の仕方と、
西側の中国に対する意識とのあいだに横たわる
大きな違いを浮き彫りにするからである。
中国が記録をよく残す国、
インドが記録を残さない国としては
しばしばいわれることであるが、
いまこのことを措くとしても、
中国に来往したひとに関する記録は、
いうまでもなく中国側で残った記録しか存在しない。
この辞典の各項目ごとに与えられた出典を
みていただくとおわかりのように、
すべて中国側の資料である。
インドや中央アジアでは中国に関する記録はもとより、
中国に渡ったひとに関する記録などはまったくないのである。
記録が残っていないのではなく、
はなから存在しないのである。
(中略)
いろいろな種類の人が中国へ来訪したことは事実である。
やってきてそのまま居座ったひと、
そこで代々居住してしまったひと、
短期の滞在の後に再び戻っていったひと、
関わり方もさまざまであった、
その人たちによって実際にインドや中央アジアの文化が、
目に見えるものも見えないものも届き、
そこで取捨選択が行われて、
中国の文化形成に役割をはたしたのである。
しかし一方の中央アジアやインドでは、
中国文明の余滴すら受け止めた証拠はない
といってよいのである。
——————————–
(以上、引用)
ツラン論考シリーズは、
中央アジアを起点として、
壮大なワンワールド史の変遷を帯びる擬似体験を
お届けしようという試みです。
古代中央アジアのロードマップは、
メソポタミア文明からインダス文明までを包含し、
古代ツラン民族のロードマップとなれば、
古代中央アジアに加え地中海から古代エジプトまでも
包含することになります。
さらには、
ツランとは縄文ヒノモトの義兄弟であるとも
伺っています。
これら壮大なワンワールド史の本拠は、
「マギ」の拠点たるヒンドゥークシュ山脈です。
上記引用は、
ワンワールド史の本拠が中央アジアであることの
ひとつの証左であるといえましょう。
次に、
中国のひとが「積極的」に向かった
中央アジアのロードマップについて、
同書から引用します。
(以下、引用)
——————————–
それにしても張騫・甘父主従に同行した300人はいわずもがな、
本書の性格上、好ましくないとして除外された幾多の将軍や
無名戦士にいたるまで、シルクロードの歴史に彩りを添えた
人々の裾野は広い。
『史記』大宛伝に
初めて酒泉郡を置き、以て西北の国ぐにと通ず。
因って益ます使いを発し、
安息(パルティア)、奄蔡(アース)、犂軒(アレクサンドリア)、
条支(シリア)、身毒国(インド)に抵(いた)らしむ。
而して天子(武帝)は宛(フェルガナ)の馬を好み、
使者は道に相い望めり。
諸もろの外国に使いするもの
一輩(グループ)の大なるものは数百、
少なきものも百余人。(中略)
率(おおむ)ね一歳中に使いの多きとしは十余、
少なきとしは五・六輩(グループ)。
遠きものは八・九歳、
近きものは数歳にして反(かえ)る。
と記しており、
張騫の遠征に刺激されて帰属してきた聖域諸国が、
中国側の輜重の調達や道案内のために恐慌をきたすほど
使節派遣が頻繁に行われたという。
当然、一攫千金を夢みた商人たちも足しげく西方へ
旅立って行ったに違いないが、
彼らは仄かに陰影を残すのみである。
——————————–
(以上、引用)
上記で紹介されている中国側の使節派遣地は、
ワンワールド史で重視すべきロードマップです。
その中でも、
犂軒を現タジキスタン北部と比定するか、
または現アフガニスタン北部と比定するか、
どちらにしても、
アレクサンドロス3世東征のロードマップと重なります。
現アフガニスタン北部のアレクサンドリア・オクシアナであれば、
バクトリアにも比定され、バクトリア豪族オクシュアルテスの娘
ロクサネはアレクサンドロス3世に嫁いでいます。
現アフガニスタン北部のマザーリシャリーフもまた、
アレクサンドロス3世東征のロードマップであり、
玄奘三蔵が訪れた縛喝国(バルク国)があったとされます。
マザーリシャリーフは、
ヒンドゥークシュ山脈とアムダリヤ川の間に挟まれた
平野部であり、ツランの故地として注視すべきでしょう。
奄蔡はアオルソイで現ドン川流域に比定され、
スキタイ故地である黒海クリミア半島近傍です。
身毒国を現インドではなく、
パキスタン北部からアフガニスタンの一部に
かけて広がっていたガンダーラに比定すれば、
そこはヒンドゥークシュ山脈です。
パキスタンとアフガニスタンの境界は、
ヒンドゥークシュ山脈を縦断するデュアランド線を基に
決められているとされます。
現在、デュアランド線が
世界で最も危険な地域と呼ばれていてることには、
ワンワールド・キャビネットの深謀遠慮を垣間見る
ことができそうです。
このように、
ワンワールド史のロードマップを描くことは、
当たり前ではありますが、
たった一度のメルマガでは不可能です。
一方、
分かりやすく図示できる実力を持ち合わせていないため、
コツコツと【ツラン論考】シリーズを続けながら、
相当の実力を身につけていきたいと思います。
それでは、また。
戦略思想研究所 中森護
P.S .
ワンワールド・キャビネットの深謀遠慮とは何かと
気になって仕方がない方もいらっしゃるかと思います。
それは私が垣間見ることができると思うだけですので、
気になさらないでください。
ただ、その深謀遠慮に対して、
中村哲は最前線で奮闘して応えきりましたが、
天皇陛下を戴く私たち日本人はどこにあっても、
すべからく応えるべきであるとも思っています。
今まさに国政選挙の真っ最中。
私自身、神武天皇即位の詔は、
専守防衛即ち競わず、争わずであることを、
皇紀歴の理念実践を戒めとして、
投票所に向かう所存です。