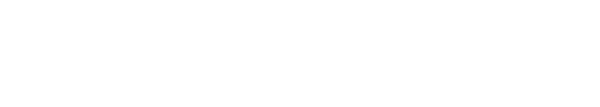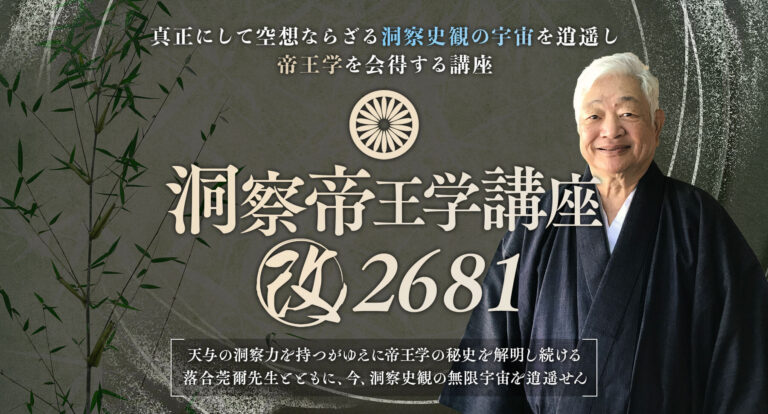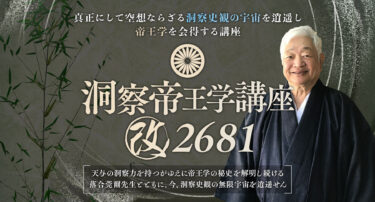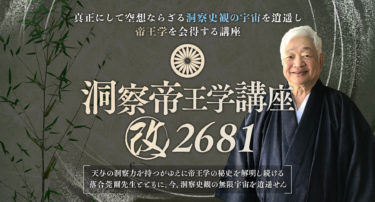※本文の内容は、
洞察帝王学講座第49回(2019年12月撮影)の文字起こしを改訂したものです。
皆さま、あけましておめでとうございます。
令和2年の正月でございます。
もっとも、撮影しておりますのは旧臘12月26日でございます、
その点はご容赦ください。
撮影は令和元年12月26日でございますが、
私はこのお宮(加太春日神社)を初めて訪れたのは、
今から5年前、平成26年10月5日でございます。
はっきりとその日のことを覚えております。
たまたま知人と話している間に、
この加太春日神社の話をしましたところ
「そこはよく知っている、連れて行ってやろうか」
ということでお連れ頂きました。
知人が「御祭神は」と尋ねるので、私は内心、
春日神社に来て御祭神を尋ねるなんてあほなことがあるかと
思っていたのですが、
驚いたのは、その時に応対に出られた事務長の井関さんが
「三殿ございまして。一つは春日三神、天照大御神、
さらに第三殿は空殿でございまして、
そこに護良親王をお祀りしております」
と言われた時は、びっくりしましたね。
というのも、
数年前から私は海南の大野庄の春日神社にお参りしておりまして。
それは自分の祖先を調べろという命令がさるところからありましたから。
それを調べている間に、海南の春日神社に行き着いたのです。
元弘2年の正月元旦、
大野の春日明神の社頭に大野十番頭という地侍が集められて、
護良親王から南朝に協力してくれぬかとの宣旨を賜り、
快くお受けしたところから、
南北朝の騒乱が始まったのでございます。
これは南北朝について書いたと言われている『太平記』の記述とは
だいぶ違っているのです。
太平記では正月だったかは忘れましたが、
切目王子に行った護良親王がこれから熊野権現にお参りして
助力加勢を願うということを言って拝むと、
童子が夢に出て
「あそこへ行ったら危ない、新宮の別当は裏切った。
親王の身に懸賞金と荘園をかけている、そんなところへ行くな」
と言われ、大和の国の野迫川のほうへ山道を向かい、
17日かけて野迫川へ着き、そこから云々という。
『太平記』に書いている話ですから、
ここでは詳しく述べませんが、そうなっているのです。
私がおかしいなと思ったのは、
野迫川で知り合った竹原八郎に言われた護良親王が紀南のほうへ隠れていた、
その間に戦争が終わっているのです。そんなことで南北朝戦などと言えるのか。
おかしいなと思っていました。
調べて行くと笠置山から落ちてきたということが分かりました。
天皇と護良親王は別れ、後醍醐天皇は万里小路藤原藤房ほか2、3名と、
楠木正成のいる河内を目指して落ちていくわけです。
これに対して護良親王は村上という、今参議院の村上正邦さんのご先祖、
村上彦四郎とか赤松入道などとともに5、6人で落ち、高野山へ行って、
高野山から「ご協力できない、うちも北条から触れが回っているので」
と言われ、紀の川筋をさして落ちていくわけでございます。
紀の川筋を下りて行くと、
必然的に河口のあたりに行きますので。
当時の加太はまだ海岸で、
紀州の紀の川の河口は大きな砂浜になっています。
和田湊があり、その北側に加太があるわけです。
加太の春日神社に頼って来たのは当然なのです。
護良親王は天台の座主でありました。
そのときは降りていて弟に譲っていましたが。
天台の座主というのは青蓮院を管轄し、
青蓮院の配下に天台山伏がいるわけです。
天台山伏は和泉葛城の二十八宿を管理というか、
本拠にしていました。
霊場のゼロ番が友ヶ島、これが根本霊場で、
それから法華経の数にちなんで28宿ございますが、
加太寺が1番でした。今は加太寺というのはないのですよ。
その先の南海鉄道加太線の加太駅の上の山にあったと言われています。
当時は両部神道で、加太寺は当然天台宗、
両部神道の修験でございますから、
そこにあった当社の前身にあたるお社が鎮守です。
両部神道は鎮守と奥の院のセットでございますが、
奥の院にあたるのが加太寺で、
鎮守にあたるのが加太春日神社だったわけです。
加太春日神社がここに設けられる由縁については
いろいろありますが、今回は鏡が主体ですので、
そこは略します。そういう因縁があったわけでございます。
笠置から落ちて来られた護良親王一行は、
なんと加太春日神社にお泊りになっていたというのです。
加太寺の向井坊という、ロッジのオーナーみたいなものの、
向井さんが面倒をみていたということは、
紛れもないことです。
『太平記』に載っていないところから実証史学とかいう
今の日本の歴史学が全く認めていないので、
とんでもない方向へ行ってしまっているのです。
今の史学界というのは半分が共産党みたいなものですから、
やむを得ないですが、やがて一掃されます。
令和2年になってこんなものは存在しなくなりますから、
そのつもりでお聞きください。
私がここで驚いたのは、
海南の春日神社に元弘2年元旦に現れた護良親王がどこから来たか、
それまでどこに居たか。
海南大野春日神社の伝承では、
その時に大野十番頭という地侍の一人に、
井口壱岐守というのがいる。
井口の頭文字に因んで壱岐の守ではなかったかと思われますが、
約束手形のように、その日が来たら
「お前に壱岐の国をやる、お前は因幡の国だ、お前はここだ」
と言い、それぞれ名前に官職名、受領名を記して配った。
そのために井口壱岐守になるわけですが、
その兄弟に井口左近というのがいて、これが調月村、
今は紀の川市か那賀郡の桃山町になっていますか、
一時は覚えても最近よく変わるので、
私は江戸時代以前の国名、町名で覚えています。
最近になって行政側が変えた地名にいちいち付いて行くことは
あほらしくてできませんから。
紀ノ國那賀郡吉仲荘の調月村の井口左近という郷士がおり、
井口壱岐守の兄弟なのでしょう。
そこに娘がおり、
親王が井口左近の家に泊まっている間に娘が子どもを生みます。
産んだ子供のことは、ほかには書いていません。
私がさるところから聞いたのですが、
生まれた子は敵方の(本当は敵ではないのだけれど)、
歴史学者は敵だと言っています。
その敵方の光厳天皇の第一皇子ということにいたしました。
もちろん光厳天皇も十分諒解の上でその子にして、
北朝の天皇にしたわけです。
従って南朝の護良親王の王子が北朝の天皇になるわけですから、
ここで南北の区別は実質的になくなった。
これが日本史最大の秘密の一つであります。
こういう一連の政略を私は「大塔政略」と名付けました。
私がこれを知ったのは、ちょうどスカイツリーが出来た年です。
私は最初、別の名前で呼んでいましたが、さるところから
「本年はスカイツリーが出来た年でもあり、大塔政略としてはどうか」
と、「しろ」とは言わない「してはいかがであろうか」と。
おっしゃる通り大塔政略と名付けたのです。
大塔政略が功を奏します。表には出ていませんよ。
南北朝はやがて合一するのですが、
それは明徳の和約で1392年、大塔政略がたてられた1334年からなんと60年後です。
その間は南北朝が両立していた関係で、世に吉野時代とか南北朝時代といいます。
鏡の話をするのに長くなってしまいましたが、以上の事が分かりました。
なぜ私がここへ来たかというと、
その直前に桐蔭高校の数学の若林先生、
時期が異なりますから師弟関係はありませんが、
たまたま中華料理店で会ったところ、
母校の桐蔭高校の話になりました。
「君は知っているか、桐蔭高校のスタンドで、
最初に野球をご覧になったのは皇族が初めで、
今の前の天皇、つまり昭和天皇が和歌山中学で
野球をご覧になったことを。
これが皇族の野球台覧のはじめである」
とおっしゃった。その次に
「その前に、加太の春日神社に参ったことを知っているか」
と言うから、知るはずもないので「えっ」と驚きまして、
そこから調べたところ、
確かに大正11年12月1日に摂政皇太子裕仁親王殿下が、
加太を訪れて和歌山へ入っているのです。
その時は加太春日神社へは、
裕仁親王のちの昭和天皇自らは参拝せず、
婚約の相手方である久邇宮良子女王の兄、
朝融王、親王の子ですから王ですね、
同じ年ですが早生まれだから学年は昭和天皇の一つ上なのです。
海軍少尉であったその方が供奉してきて、
単独でここへお参りになったのです。
摂政宮は、祭祀以外は天皇と同等の権限があります。
政治には天皇の権限を持っていますから和歌山市長、県知事等に会い、
最後に夕方、和歌浦の御手洗池のそばにある、
双青寮という紀州徳川の別邸に入られたわけであります。
夕方4時半ごろ、徒歩で朝融王が現れた。
徒歩というのは、馬に乗ってはいないという意味で、
タクシーか知りませんが、とりあえず4時半ごろ現れたのです。
お二人で明朝は和歌山市山東という地区にある農業教員研修所へ行き、
いろいろ見たあと、かねて用意してあった小松をご植樹になりました。
さらにクスノキの種を蒔かれました。
12月2日のことですから、
種蒔きの時期ではないので、おそらく箱にでも入れておいた。
それが芽を出し、なんと加太春日神社の社務所に植えられたのです。
その時の小松も一緒に植えられたそうですが、
このあたりを荒らし回ったマツノザイセンチュウにやられて、
残念なことに一本もないのです。
クスノキはそこに残っています。
樹齢100年近いわりに大きくはないけれど
ずっと刈り込んで来たからだと思います。
うちのクスノキは20年も経たないのに、
亭々たる大木になっていますので、それから見るとこれは。
でもこれは確かに昭和天皇お手植えのクスノキです。
そこまで聞いたら疑うことではないですよね、
太平記にはないが、太平記には背いているけれど、
海南の大野十番頭の伝承といい、ここの伝承といい。
元弘2年、本当は元年12月31日に幡川の禅林寺に姿を現すまでは、
護良親王はここにおられたのです。
向こうで大野十番頭等の世話になって、南朝の旗をあげて、おそらく、
それからしばらく井口左近のところに逗留していろいろしていたのでしょう。
それがまたここ加太へ戻って来たということだと思います。
なぜかというと、親王のもっとも強力な同盟の相手は楠木正成です。
正成は岸和田が本拠で、
そこから堺とか、海辺に基地を置いていたわけです。加太は海ですから、
そこから船を出せば一番速いのです。馬で行くよりも遥かに速い。
当然、ここにいたわけです。
ここは天台修験の本拠ですから、
天台修験のネットワークで情報が伝達できるし、
各地を偵察した情報も入る。ここは要地です。
ここにいて、向こうの内陸というか、
南のほうでは大野十番頭が旗をあげていよいよ南北朝というか、
北条幕府との戦いが始まったのです。
最初のその時、足利はまだ敵ではないのですよ。
その話は鏡に関係ないので、どうでもいいのですが。
私がここへ来た日、初めてここにお伺いしたにもかかわらず、
ご神宝のうちの鏡を見せていただきました。
その中の13番とあったのが、これです。読めますか。
12に分けて6つが菊、あと6字彫ってある。
「衣冠を整え、瞻視を尊く」とあるが、
「瞻」の字が難しくて鋳つぶれているから読めなくてもいいですよ。
衣冠を正しくして、瞻視というのは物の見方、特殊なものの見方。
そういうことで君主は自分に威厳を付けろという話です。
鏡にこの字を掘るのは鏡を見るたびにこれを思い出して、
きちんとしろよ、ということではないかと思います。
ここに菊を彫っています。
菊は、おかしなことに、普通は16ですが20くらいある。
なんで、日本人が作った菊、こういうのは16になるのです。
14の場合もありますが、20くらいあるのでおかしいですね。
とりあえず、この詮索はあとで致します。
これを藤房鏡だとおっしゃって、
万里小路藤房朝臣に関係があるということを聞きましたが、
それ以上は分からない。
ところが藤房という人は、先ほど言ったように、
後醍醐天皇が笠置山を落ちのびる時にご一緒した4、5人の一人なのです。
大変な活躍をして、建武の新政が始まると雑訴決断所や評定所など、
最も重要な機関の長になり、建武新政の中心になった人物なのです。
その人物の鏡ですから、ここにあるのは当然なのですが。
後ほど私がこれについて、高松宮妃殿下の関係に伺ったところ、
藤房は護良親王の恩賞の乱発というと言葉が悪いですが、
恩賞の宣旨、お前はよく頑張ったこれだけの恩賞をやるという宣旨。
私の直接の先祖の井口氏も壱岐の国の一国をもらったのです。
そういう約束を乱発したので、もちろん口約束ではなく一筆書く。
書き過ぎたということで、親王はあとで罪に問われるわけですが。
そのため宣旨を回収して代わりに鏡を置いて回ったという話を聞きました。
正しくは聞いていませんから正確には存じ上げません。
とすると、この種の鏡は各所にあるはずだと思いますが、
果たして、各所にあるそうです。
まず明治35年、風山広雄という方が『下野神社沿革誌』という本を書いています。
その中に上都賀郡菊沢村大字見野というところに鎮座する喜久沢神社は、
祭神が万里小路藤房朝臣で、宝物として古鏡一面、一個という意味です。
「表に興国四年1343辛巳三月 祖父資通冥福父宣房□福不二行者授翁外に經文あり」
と書いています。
ほかに経文等がある、経文というのは銘文のことで
「寳祚興久一字三禮一品一銭とあり 裏に 整衣冠尊瞻視 の六字あり」
というので同じというか、同じ物ではないが同じ形式の鏡だと思います。
これを藤原藤房の鏡と呼んでいるのは、
ここにある「不二行者授翁」という名前を書いて、
不二行者授翁が
「祖父資通冥福父宣房の□福を祈った」
と書いてあるのです。
資通というのは万里小路資通、宣房というのは万里小路宣房でございまして、
父、祖父と書いているので、
その子どもである授翁がこれを作って納めたという意味です。
ほかに経筒とかあり、経筒をおさめた一連の者です。
この授翁が生まれた年が藤房と同じ、
父も同じ、生まれた年も同じですから、
名前は違うが同一人物であるというのが、誰が見ても常識です。
ところが、今の歴史学会はそうは言っていないのです。
おかしなことです、あとで申しますが。
1767年に長光寺境内の獲竜山という山腹が崩壊して、
山の中から藤房鏡とか、いろいろ出てきました。
その銘文から明確に不二行者授翁が父と祖父の冥福を祈るために
奉納したものであるということが分かり、全国に広まりました。
幕末には本家の万里小路家から藤房の、
多分画像ですが、絵を寄進されて、それとともに一社を建てます。
これが明治5年だったか、新政府によって正式に神社の許可を得ます。
それから7年には県社に任命されます。
県社というのは社格が高いのですよ。
一番高いのは官幣大社、国弊大社とかありますが、
県社というのは次の次でなかなか高いのです。
村社、郷社、いろいろありますが、早くも県社に指定された。
小さなお宮が出来たばかりの時です。
それほどの社格になったというのは、寄進者の藤房というのが偉いからです。
喜久沢神社は鏡を祀ったのではなく、藤房の霊を祀っているのですよ。
ご神宝がこの鏡。表に字が鐫刻してあるのです。
ツルツルに磨いて、錫を張って、顔が映らなければいけないのですが、
メッキが剝げてくると映らなくなる。
この表面にどうも線で彫ってあったみたいです。
その時はこれと同一物ではないが全く同じ形だったと思います。
手書きで彫ったのです。
こういうものは全部藤房鏡なのです。
彫ってあるのもあるし、彫っていないのもある。
これを授翁の鏡とは言わずに本名の藤房鏡と言われてご神宝になっております。
では授翁の説明をしなければいけません。
万里小路藤房は正二位中納言まで行き、建武政権の中心人物であったのですが。
その最中、1334年、にわか出家したと書いています。ドロンする。
歴史学者はこれを恩賞の決め方に不満があった、
自分が決めた恩賞の決め方と後醍醐天皇の方針が違い、
えこひいきばかりして、これでは武将はおさまるまい、
自分は恩賞決断所のかしらとして耐えられないと言って辞めたのだとか、
言いますが後講釈で、本当はそんなものではなかった。
護良親王を守るために、ある大きなことをしていた、
つまりにわか出家したとして海外へ行っていたのです。
これが1334年ですが、20年後に姿を現す。
僧になり、不二行者授翁という名前の坊主になります。
坊主の実績をどこで積んだのか、
もちろん海外へ行っていたことは言いませんが、
これに関していろいろな伝説が出ているのです。
一つは秋田県出羽の国の補陀寺というお寺、
曹洞宗の大きなお寺があるのです。
この寺の二世で無等良雄という坊さんが藤房その人であったと。
結構大きなお寺ですよ。
そういう説もありますし、
江戸の芝浜に流れ着いた藤房が、
周りの漁民があまりに下品粗野であるので、
これを教育して礼儀を教えたとか。
そんな話がたくさんあります。
貴族ですが、従兄弟が高野山の住職をしていて、
そこへ身を寄せて暮らしたとか。
こんな説がたくさんあります。
ということはどこにもいない、日本にいなかったのだから、
その間を説明しようと思っていろいろ、
相手の顔色を見ながらわかりやすい話を流した人がいるのです。
明治35年のこの本、上野の神社史に載っているのですが。
高橋健自という、わが国の考古学の祖とされる人物がおります。
この方がその9年後、明治44年に藤房鏡のことについて書いています。
「世に藤原藤房の鏡とて名高き柄鏡あり、
そは内区に菊花紋を六箇所に配し、
その間に『整衣冠尊瞻視』の六文字を一字づつ置きたるものにして」
まさにこの通りです。
十二に分けて、菊花紋を6か所に散らし、衣冠を整え、の六文字を置く。
先ほど言ったように全く同じ、多分これと同じ形式だと思います。
「鏡面には宝祚長久云々の銘あり」
とは字を彫りつけたのです。
彫り付けた字が違うから別の鏡とはいえ、形式は同じだと思います。
「下野の国長光寺境内喜久沢にて発掘されたるものなり」と。
長光寺という大きなお寺の境内の山が崩れて出てきた、
経塚から出て来たと。
そういうものです。修験というものは経塚と関係があるのです。
この近くの加太寺のあととか、
二の宿、三の宿、二十八宿には全部経塚があります。
不二行者というからには、
藤房は天台修験になったのではないでしょうか。
それがなぜ禅宗の坊主になって出てくるのかは分かりませんが、
何かあるのでしょう。
というわけで考古学の大先輩、下野神社沿革史の9年後に発表した『鏡と剣と玉』という本の中で、
「されどこの銘を以て、その藤房の遺品たるを證せむとするは早計を免れざるのみならず、事枝葉に渉れるを以て茲に論ぜざるべし。予は唯この種の鏡を以て湖州鏡輸入以後の時代に於て支那より多く傳來せしものなるべきを信ずるものなり」
湖州鏡とは平安時代以降日本にいくらでも来た、
浙江省の湖州というところで作った鏡です。
それが平安から日本に随分輸入されたので、
湖州鏡というのです。蘇州とかの近くです。
そこで作られたもので湖州鏡の輸入がやんだあとにおいても、
シナより多く伝来してきた鏡であると。
要するにこんな物はどこにもあり、大したものではない、
という言い方をこの方はしたのです。
それはなぜか。後場で説明いたします。前場はここまで。
(後半につづく)